
 トラクターの運転も大好きです
トラクターの運転も大好きです
管理本部技術支援部 中央技術支援センター つくば第4業務科
鈴木 莉奈 科員

なぜ農研機構へ?
栃木の実家は兼業農家で、お米を作っています。子どもの頃から父を手伝い、自分もプランターで植物を育てているうちに「自分の手で作り、育ててみたい」と思うようになりました。高校は普通科でしたが、進路について両親に相談すると「農業大学校というのがあるよ」と教えてくれ、施設園芸コースへ入学しました。農業大学校では、主にトマトの栽培を学んでいました。卒業後の進路として就農する学生がほとんどなのですが、農業大学校での実習を通じて私は「サポートする方が向いている」と感じ、先生に相談したところ、農研機構を紹介していただきました。栃木県那須塩原市にも農研機構の研究拠点があって、農業の研究機関であることは知っていました。
仕事の内容
半年の研修後、業務科に配属され、研究部門の支援を担当しています。具体的には、研究に使うイネや大豆、野菜などを育てています。また、トラクターに乗っての農作業からイネほ場の土壌中のメタン測定まで業務は多岐にわたります。配属後の1年は先輩や上司に教わりながら仕事を覚えていき、4年目の今年からは研究室の依頼でイネの登熟歩合の調査をメインで任せてもらえるようになりました。同時に後輩に自分が教える機会も増えてきました。やりがいもありますが、どうしたら上手く教えられるか、自分が1年目だった頃を思い出して、先輩たちが教えてくれたように上手く教えられるよう試行錯誤しています。今の課題は、機械の整備をもっと学んで、壊れても修理ができるくらいになりたいです。
農研機構について
入る前は研究機関ということで、堅いイメージでした。入ってみたら、全国に職員がいることに驚きました。業務においてもいろんな考え方があって、しかも柔軟な発想で、「おもしろいな」と思いましたし、「入ってよかったな」と思います。お休みも計画的に取れるところもいいところです。
メッセージ
入ってから学び、身につけていくことができます。不安なこともやってみることで、不安がなくなります。迷わず飛び込んできてください!

職場の皆さん

業務に関する質問にも丁寧に答える
長田直輝 科員(左)、富山 班長(中)

上司 富山浩和 班長、先輩 大中見咲 科員、後輩 牟田裕貴 科員
 官能検査の様子
官能検査の様子
管理本部技術支援部 中央技術支援センター
つくば第6業務科 金谷技術チーム(静岡)
倉橋 慶伍 チーム員

なぜ農研機構へ?
鹿児島県・種子島の出身です。地元は農業や漁業が盛んな地域で、高校は農業学科に入学しました。畜産や安納芋やさとうきびについて学んでいて、農業に対してすごく興味を持ったのです。それで農業大学校に入ろうと思いました。その時にせっかくなのでやったことのないことをやってみようと飛び込んだのが茶業の世界でした。
仕事の内容
ほ場の管理、製茶、官能審査をしたり、未来の茶業を担う研修生を指導したりしています。また、研究員さんとメーカーさんとの共同試験の調査に同行したり、金谷拠点のプロジェクトの成果発表等の説明や撮影もやります。一番茶の時期は枕崎拠点に一週間ほど技術支援にも行きます。
思い出
農業大学校では茶園実習があり、生産者さんのお茶にかける思い・技術の高さを目の当たりにして、奮起しました。毎日茶園を朝一番に見に行って、製茶だけではない栽培のことも学びました。進んで掃除もし、きついこともいろいろありました。「どういうふうにしたら良いものができるんだろう」とひたすら追い求めた2年間があって、今があります。職場の先輩や同僚・同期、農業大学校で出会った方々、すべての皆さんに感謝しています。
農研機構について
キャリアを自分で作っていくことができます。人生設計がすごく立てやすい職場だと思います。例えば自分が今いる職場で、どういうふうにやっていきたいというビジョンが固まれば、それに応じたキャリアパスが作れると思います。そして、全国に拠点があるからこそできることもありますし、人材を育てようとしてくれる農研機構に入ってよかったなと思います。
メッセージ
ありのままで入って、ありのままの自分から成長していけば良いと思います。
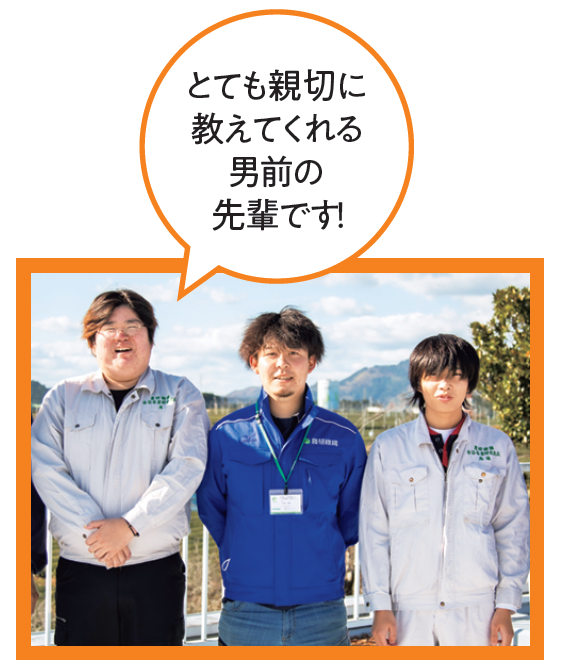
業務科研修生 (右)角さん/筑後市出身、(左)馬場さん/八女市出身

大上 猛 金谷技術チーム長

研修生を指導する様子
ほ場



研究体制、職場環境を整える縁の下の力持ち。物品などの契約手続きを行う部署、研究成果を正しく管理する部署、栽培技術などの発明や品種などに必要な手続きを整える部署、情報発信を行う部署など、その業務は多岐にわたります。
