
PERSON
地域の農業試験場での研究経歴が長く、研究成果の現場への還元を実感した時にやりがいを感じるそう。

農業環境研究部門 土壌環境管理研究領域
久保寺 秀夫 領域長
PERSON
日本の土壌分類を推し進め、その土台を築いてきた土壌研究の第一人者。

農業環境研究部門 土壌環境管理研究領域
小原 洋 さん
科学×経験の掛け算で農業をよりよく
土壌は地球の表面を覆う、ごく薄い膜程度の層です。食料生産の基盤であり、さまざまな物質の循環の場、生物(動物・植物・微生物)のすみかでもあります。土壌は全ての生物の生存に欠かせないものであり、人類にとっても農業生産を行うための重要な資源だといえるでしょう。人は古くから土壌と向き合い、経験的にその土壌に適した作物を生産し、管理を行ってきました。農研機構では、その先人の経験知に科学的な知見を取り入れ、より最適な農業技術の開発を行っています。土壌という貴重な資源を活用し、健全で効率的・持続的な農業生産を行うため、土壌研究を通して農業の発展に貢献することを目指しています
持続的な農業を支える農研機構の土壌研究
農研機構が取り組む研究の一つが、土壌図の高精細度化です。日本で近代的な土壌図の整備が進められたのは1950年代頃。それを誰でも簡単にアクセスできるよう、本機構が2010年頃にデジタル化しました。スマート農業に注目が集まり、より細やかな土壌情報のニーズが高まる昨今。デジタル土壌図をさらに高精度化していくべく研究を重ねています。
さらに、土壌の調査技術の開発にも取り組んでいます。現場で土壌分類などに活用できるスマートフォンアプリの開発やドローンなどを用いた広範囲の観測など、より効率的で詳細な調査方法を開発することで、土壌研究の深化を図っています。
明治時代に起源を持ち、多様な土壌の知見を蓄積してきた本機構だからこそ、膨大なデータをさまざまな分野とリンクさせながら最先端の研究を進めることが可能です。今後もICTなどを取り入れながら、環境保全と農業生産を両立し、健全な土壌づくりに取り組んでいきます。
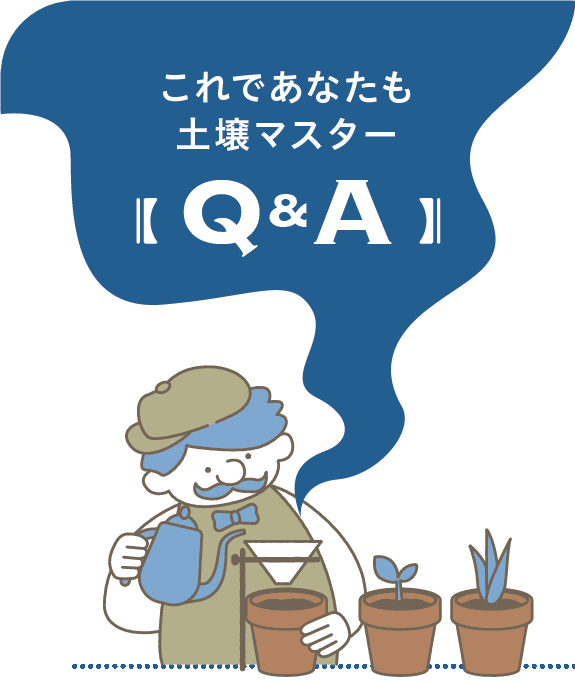
【Q1】
なんで土壌を調べるの?
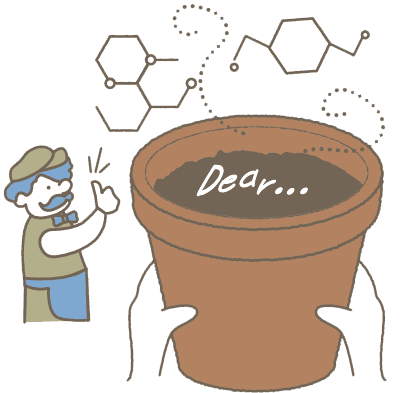
A. 土壌にはたくさんのメッセージが込められているから!
土壌は全ての食料生産の起点となる資源です。土壌にはさまざまな種類があり、それぞれの特性に合った作物や管理方法が存在します。土壌の生成要因は主に気候・植生・地形・母岩※・時間・人為の6要素。それらがどう作用しているのかを研究することで、土壌の特性を詳細に解き明かし、最適な農業生産を行うための足がかりにしています。
※土壌のもととなる岩石のこと。
【Q2】
どうやって土壌を調べるの?
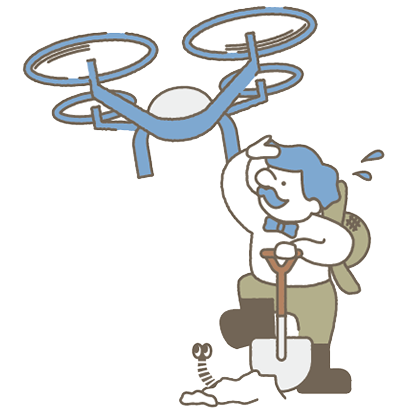
A. 土を掘って分析する地道な作業。でもゆくゆくは…
土壌調査は、現地に赴き土壌を採取・分析するのが基本で何よりも正確です。しかし労力や時間がかかるので全国の土壌を全て調査することはできません。そこで今後は、より効率的に広範囲な調査を行えるよう、ドローンや衛星の活用、AIによる土壌の情報の推測などの新しい手法の開発にも力を注いでいきます。
【Q3】
調べたデータはどう活用しているの?
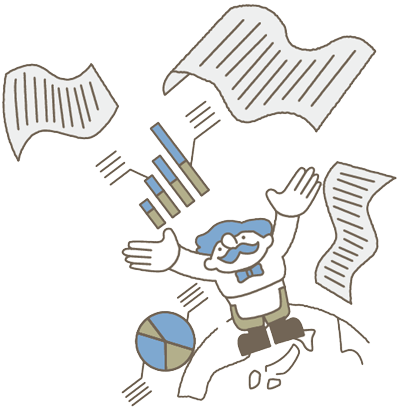
A. 全世界に公開し、各地で農業に活用
土壌データはインターネットで公開され、全国で農耕地の管理の基礎として活用されています。土壌図にアプリを連携させ、各地点の詳細な土壌の様子や管理に関する情報を掲載するなど、機能を強化しています。また、病害虫対策や作物の高付加価値化といった分野とも結び付け、より多様な視点での土壌研究が進められています。
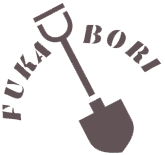
未来の土壌を支えるキーワード
みどりの食料システム戦略
食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現することを目指し農林水産省により策定された方針。農研機構では、持続可能な土壌づくりにおいて、化学肥料などによる土壌への過度な影響を抑え、環境保全と両立する生産を実現するべく全力で取り組んでいます。
Soil Health
近年、欧米の土壌政策の柱となっているSoil Health(土壌の健康)。日本でも、「土壌の健康とは何か?」という議論は今後ますます活発になっていきます。生産性や環境負荷低減だけでなく、健康で持続可能な土壌を実現するため、農研機構では現在、日本における「土壌の健康」の定義や評価手法について検討を進めています。
- 詳しく知りたい方は
農業環境研究部門HP をチェック!
