
東北発
乾直最前線で課題解決に挑む
農研機構東北農業研究センター
水田輪作研究領域 ICT活用技術グループ
研究員篠遠 善哉SHINOTO Yoshiya
筑波大学大学院生命環境科学研究科博士前期課程修了後、2014年農研機構へ。
博士(農学)、日本作物学会員 、根研究学会員。
2014年4月 - 2016年3月 生産基盤研究領域農業機械グループ
2016年4月 - 2021年3月 生産基盤研究領域栽培技術グループ
2021年4月 - 現在 農研機構東北農業研究センター 水田輪作研究領域ICT活用技術グループ
「面白そうだから」と農学部に行こうと決めたのは高校生の時。環境問題に興味をもち、大学院では「少ない水でトウモロコシを栽培する研究」にエジプトやタイで取り組んだ篠遠善哉研究員が、プラウ耕鎮圧乾田直播栽培技術(以下、乾直)を武器に、農業課題の解決に挑んでいます。
まさかの東北配属!
大学院の後期課程に進学予定だったのですが、農研機構が職員採用をしていることを知り、チャンスと思い応募しました。採用されて配属されたのは、それまで一度も行ったことのない岩手県の農研機構東北農業研究センター(以下、東北研)。ちょうど東日本大震災の津波被害による震災復興に宮城県の名取市で取り組んでいる最中で、配属されて8日目から現場に連れて行ってもらいました。
入ってすぐの頃、「プロ農家と話せるようになりなさい」と言われたことが心に残っています。
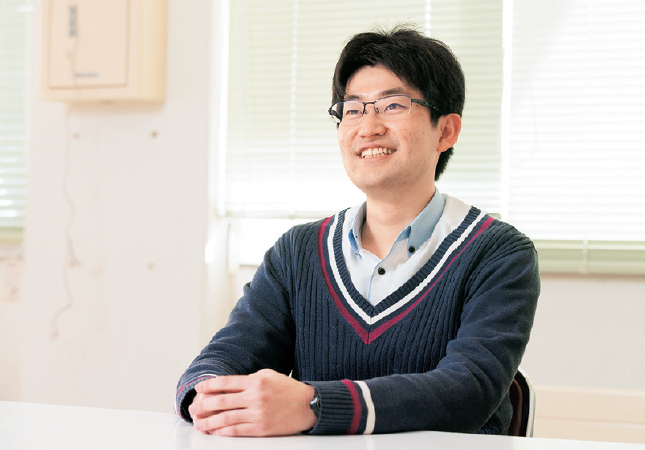
足でかせぐ研究者
研究機関にいながら僕は今の仕事をあまり研究と捉えていなくて、技術開発の一つだと思っています。ここでは研究をどのように社会に生かしていくのかというよりも、「必要とされているものから逆算して技術を開発する」ことが求められていると思います。何を求められているのかを知るために、現場に行って農家さんと話して課題を見つける。基礎研究は別として、僕らのような現場で使う技術を開発する人にとってそれが重要だと思います。
プラウ耕乾田直播を一つの大きな武器に、麦や大豆、子実トウモロコシを入れた輪作、水田農業の未来、日本の農業を続けていくために、僕らができる技術開発は何なのかを考えて取り組んでいます。僕にとって研究はあくまでも手段の一つで、生産現場の課題解決こそが自分の仕事ではないかと考えています。
配属当初の上司大谷さん(直播栽培技術・こぼれ話参照)から「現場に行けば課題はゴロゴロ転がってる」と言われたことがあります。でも最初はその意味が正直よくわからなくて。今では、何度も現場に行くとだんだん課題がわかってきて、今すぐやらないといけない課題を少しずつですが拾えるようになってきたかなと思います。
乾直普及の最前線にいて
僕の仕事はあくまでデータを取ることなんですよね。取ったデータは、現場の農家さんへの説明に使えますし、行政の方には制度などの仕組み作りの参考データとして使っていただけます。そういったことに自分のデータが使われていると思うと、プレッシャーも感じますが、やりがいも感じます。その自分のモチベーションの源泉は何かといえば、現場に足を運び、農業を生業としているプロ農家の方々と新しいことに取り組んで、一言「良かった」と言ってもらえること。農家の方たちの頑張りに貢献しなければと思います。往復4、5時間かけて現地まで行き、調査したり話をしたりするのはせいぜい1時間なんてこともありますが、顔と顔を突き合わせて話すことで信頼関係が築けると思っています。
連携が生み出す力
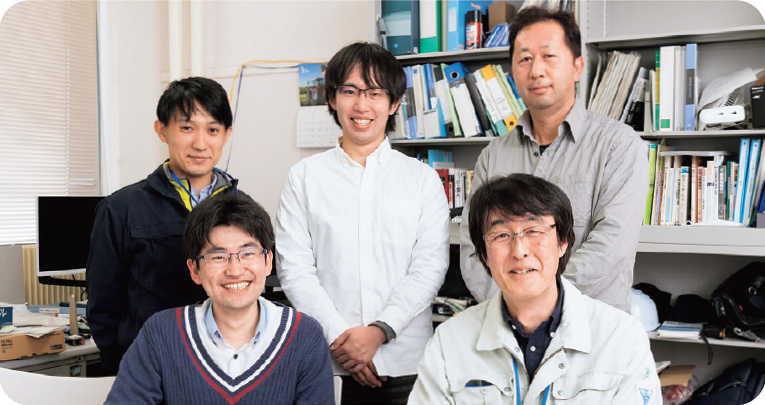
研究仲間の皆さん
(後列左から)田邊大さん、兒玉巽さん、古畑昌巳さん
(前列左から)篠遠善哉さん、冠秀昭グループ長
農業の未来のために
今年、宮城県では、数ヘクタールから始まった子実トウモロコシ栽培が150ヘクタール以上という面積まで広がります。「10年先の地域の農業の未来」を考えて決断された農家さんたちがいて、僕ら研究者や農協、行政、普及センター、メーカーが同じ方向を向いて「未来のために」という熱い思いで一緒に取り組んでいます。熱い思いのある人たちが集まれば、1+1+1は3じゃなく、5にも10にもなり、ダイナミックに物事が動いていきます。結局は「人」のつながりが重要で、変化が速い今の時代に大きな物事を始めてやり遂げるまでには、人と人との連携で生み出される大きなエネルギーが必要だと実感しています。
乾直の技術の普及に日々取り組んでいますが、いま、最高にワクワクしています。東北研に配属された偶然に感謝しています。

Message
農研機構に必要なものは、「やる気」「体力」と、「コミュニケーション能力」ですね。この3つはあったほうが良いです(笑)。
篠遠さんの研究活動の一つ
「水稲直播および子実用トウモロコシ普及促進会」活動
篠遠さんって
こんな人

水田輪作研究領域 ICT活用技術グループ
冠 秀昭 グループ長
篠遠くんは、ある意味(声が大きいので)存在感があります(笑)。研究室の外でも、農家さんとすぐに仲良くなれる抜群のコミュニケーション能力があります。思いついたことはすぐにやる行動力、失敗を恐れない精神力。研究だけでなく農業経営なども含めた全体を俯瞰して考える新しいタイプの研究者だと思います。彼の後に続く若手の育成にも期待しています。
