国際共同研究プロジェクト
遺伝資源を訪ねて
農研機構は、日本と共同研究国の双方にとって重要性が高い野菜や穀類を対象として、植物遺伝資源の共同調査に参画しています。それに関連し、研究者が共同研究国を直接訪ね、遺伝資源の探索収集も行います。ここでは、実際に探索に携わった研究者の活動を通して、国と国の境を超えて、遺伝資源を守ることの意義を考えます。

なぜ今、遺伝資源の探索が必要なのか
昨今の地球温暖化問題や病虫害等への対応として、国内農業の強化策のひとつに新品種の開発があります。そして新品種を開発するためには、育種素材となる多様な遺伝資源の確保が重要です。しかし、日本の新品種開発において重要な植物遺伝資源を多数保有するアジア地域の途上国では都市開発が進み、農業のグローバル化もあって在来種に代わって改良品種が広く普及するなどの傾向が見られます。その結果、地域の環境に適応した在来の遺伝資源が急速に失われつつあるのです。また一方で、途上国を中心に遺伝資源に対する権利保護の機運が高まり、海外から遺伝資源を導入することが難しくなってきています。
国際共同研究プロジェクト
PGRAsiaとは
そこで、農林水産省の委託プロジェクト「PGRAsia」が2014年度から始まりました。共同研究を通じて、海外から遺伝資源を日本に導入するという試みです。このプロジェクトでは共同研究相手国において、遺伝資源を相手国の研究者と共同で探索収集することに加え、収集遺伝資源の特性調査を行ったり、相手国との育種素材共同開発、遺伝資源情報のネットワーク化を進めています。また相手国の研究者を受け入れ、研修なども行っています。共同研究相手国としては、2014年度当時はベトナム、ラオス、カンボジアの3カ国でスタートしました。2015年度からはネパール(2016年度で終了)とミャンマーが、2019年度から新たにキルギスが加わっています。
プロジェクトメンバー、資源探索を語る。
農研機構はPGRAsiaの代表機関として、毎年共同研究国に研究者を派遣しています。そこで今回はプロジェクトに参加し、遺伝資源探索に携わってきた農研機構 野菜花き研究部門所属の5人に、探索収集活動の現状や資源探索の意義などを語ってもらいました。
【Vietnam, Cambodia】土地の人への聞き取りを重視
ウリ科・イチゴユニット 川頭 洋一
KAWAZU Yoichi
2016年にベトナム、2019年にカンボジアに探索に行きました。ベトナムではキュウリ、カボチャ、アマランサスを中心に、カンボジアではメロン、キュウリ、カボチャなどの在来野菜を収集。両国とも改良品種が入ってきているという現状があり、育種での活用が期待される在来種を見つけるため「いつから栽培しているか」など現地の人への聞き取りを重視しています。

【Cambodia,Vietnam】辛くない希少なトウガラシを探して
ナス科ユニット 松永 啓
MATSUNAGA Hiroshi
2014~2018年の5年間にわたりカンボジアへ、2019年にはベトナムに行き、計6回の探索となります。対象野菜は主にトウガラシを中心とした、ナスなどの野菜を収集しています。最近、トウガラシの辛み成分が注目されていますが、辛すぎると大量には摂取できません。「辛み成分がありながら辛くない」トウガラシを探索活動で見つけるのが現在の目標です。

【Laos】在来品種を保護するということ
ナス科ユニット 宮武 宏治
MIYATAKE Koji
2017年から3回にわたるラオス探索で、ナスを基本に収集しました。ラオスでは近年の温暖化の影響か毎年洪水が起こっています。このままでは在来種が洪水で流され、二度と育てられないということになりかねない。このプロジェクトに参画することで、現地の研究機関の方にも種を集めて保存することの重要性を理解してもらえるのではないかと思っています。
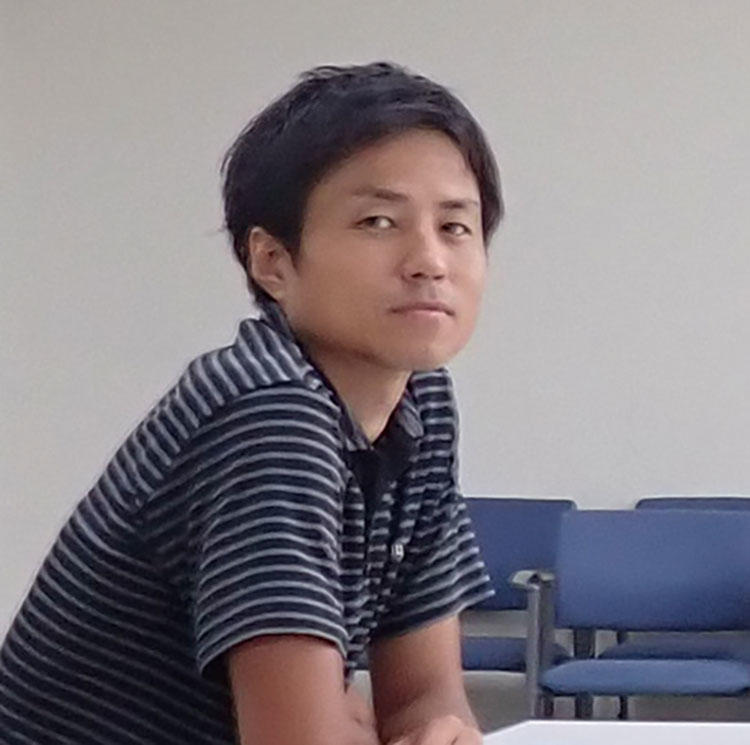
【Vietnam,Nepal,Myanmar】野生のキュウリとの出会いに感動
ウリ科・イチゴユニット 下村 晃一郎
SHIMOMURA Koichiro
2015、2017年にベトナム、2016年はネパール、2019年はミャンマーに行きました。キュウリやメロン、カボチャ、トウガンやスイカなどのウリ科をメインに収集しました。キュウリの起源地と言われるネパールで、博物学の権威、中尾佐助先生が1950年代に収集してきたものと同じ野生のキュウリを見つけた時は感慨深かったです。
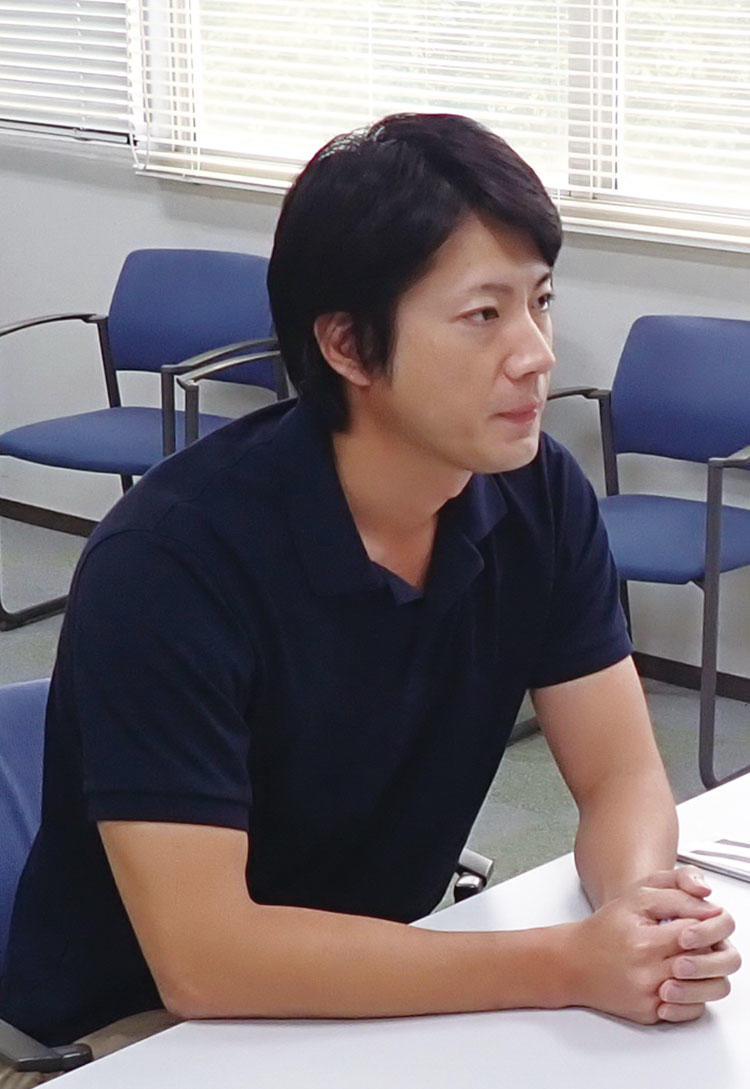
【Kyrgyz】葉根菜類の野生種を収集
アブラナ科ユニット 柿崎 智博
KAKIZAKI Tomohiro
2019年にキルギスへ探索に行き、品目はアブラナ科、レタスなどの仲間のキク科、ネギの仲間のユリ科といった葉根菜類を中心に近縁の野生種を収集しました。探索収集活動を通して、近年国内で問題になっている病害のひとつ、黒斑細菌病(*1)に抵抗性を示すものがないかどうか、これから調べていこうと思っています。

*1 黒斑細菌病:ハクサイやキャベツ、ダイコンなどアブラナ科全般に発生。中でもダイコンは根の中に黒い斑点ができるため、加工の段階まで気づかれないことが問題となっている。
遺伝資源が育種の未来を創る~PGRAsiaプロジェクトメンバー座談会~

資源収集の決め手は 在来種かどうか
―各国に探索収集に行かれたみなさんですが、実際の資源探索はどのように行われるのでしょうか。
川頭●「こういう資源を収集したい」というこちらの要望に応じ、現地の植物に詳しい研究者らがカウンターパートとなって、事前調査をします。その調査をもとに、目的の種を持っていそうな農家の方のところに連れて行ってもらいます。
柿崎●キルギスは遊牧民がつくった国のため、農耕があまり盛んではないんです。目的の葉根菜類は農家を訪ねても種がないだろうとのことで、道ばたや山の斜面などに生えている野生種の収集を行いました。


下村●資源を収集するかどうかの決め手のひとつは、在来種であることです。カウンターパートや現地語の通訳を介し、「この植物がいつからここにあるのか」「種をいつから取っているのか」といったことを現地の人への聞き取りで調査します。
―在来種を重視する理由は?
松永●例えば南米原産のトウガラシは東南アジアで幅広く分化したとされ、青枯病(*2)に抵抗性のあるものが多いことで知られています。東南アジアのトウガラシは、上の方の収穫が終われば枝を切り戻し、下の方から枝を出させるという方法で何十年も同じ場所で栽培されています。枯れることなく長年同じ場所に植わっているのは、それだけ病気に強いと考えられるわけです。
宮武●ラオスで裏庭に植わっているようなナスに、青枯症状で枯れているものは見たことがなかったんです。ところがラオスでも改良品種の農園では青枯症状が出ているので、それなりに強いものが選ばれ、在来種として維持されているんですね。

*2 青枯病:植物病原細菌の一種である青枯病菌(Ralstonia solanacearum)の感染により起こる病気。主に根から侵入した青枯病菌に感染した植物では、導管(水分などが通る組織)のなかで菌が増殖し、水分の吸い上げができなくなることなどによって葉や茎の地上部が萎れてしまい、最終的に枯死する。
質問の仕方にひと工夫
現地の研究者の協力も欠かせない
―改良品種と在来品種の特定はどのように行われるのですか。
松永●トウガラシの場合、改良品種はかなり見た目がきれいなんです。在来種は極端に大きかったり小さかったり、デコボコだったり。でも農家さんはそんなことは知らないので、改良品種でも「ずっと前から育てている」と言うんです。1年前からも5年前からでも、ずっと前(笑)
下村●それで僕らは前回の探索時にちょっと質問の仕方を工夫して、その土地のおじいさんに「子どもの頃からこの野菜はありましたか?」って聞いたんです。おじいさんが「食べていた」と答えたものは50年はあると判断できるかと。なるべく確度の高い確かめ方を心がけています。
川頭●話を聞く相手は英語も現地の公用語もわからない、少数民族の言葉しか話せない人も多いので、欲しい品目の果実の写真や、植物体の写真をあらかじめ用意しています。

―探索時に各国の文化の違いを感じることはありましたか?
松永●カンボジアでは、比較的簡単に収集の許可が下ります。それに対しベトナムでは、探索地域を主管する関係機関すべてに顔見せをし、今回の探索の目的をそれぞれに説明してはじめて収集の許可がもらえます。お国柄だと思いますが、厳格なルールを守ることで、目的の場所での収集がスムーズにできるんです。
川頭●ベトナムは経済的に発展しているイメージがありますが、探索で訪れる地方は道や衛生状態も悪く、水牛とか家畜が道を歩き回っているようなところ。お酒で外国人を歓迎してくれる文化があり、お酒に弱い私にはきつかったです(笑)。
宮武●ラオスの人はナスをよく食べるので、どの家にも裏庭にナスが植えられています。そういう裏庭に現地の人が気づいていない価値ある資源があったりするので、くまなくすべての家を回るようにしています。

柿崎●肉食文化のキルギスでは、現地の食事に使われている葉根菜類はタマネギやニンニクなど数品目でした。栽培面積も限られるため、種の保存も難しいという現状があります。
―都市開発やインフラ整備、相手国の環境も時とともに変化します。
松永●カンボジアも最初は在来種が集めやすかったんですが、道が年々整備され、改良品種やその後代が出回りつつあります。そうなると裏庭で長年植えられているようなもの、本来そこにあるはずの在来種が年々集めにくくなっている印象です。
宮武●ラオスは在来のものを今も作り続けている印象ですが、近隣の国から種を買ったという農家さんもいて、ここ数年で在来種から改良品種に一気に作り変えられてしまうということもあるなと危惧しています。

肌感覚で学んだことが 今後の研究に生きてくる
―探索収集活動の持つ意義がますます大きくなりますね。
川頭●そうですね。例えばいろんな作物に新しい病気が発生し、それに対して抵抗性を持つ植物を作りたいと考えます。そのときに探索などで得られた多様な遺伝資源があれば、欲しい素材が見つかる可能性が高くなります。そういう意味でなるべくたくさんの遺伝資源を保有することが非常に重要になりますね。
下村●農家さんが植えたり、野生のものでも、自然環境下でセレクションが行われ、我々の想定していない遺伝子を持っているかもしれません。育種の際に何が有用かはわかりませんが、遺伝資源を持っていることが重要です。またこんなに寒いところでキュウリが育つとか、論文では生育しないと言われている場所にこんな植物があるとか、探索時に肌感覚で学んだことも今後の研究に生きてくるのではないかと思います。
宮武●肌感覚は確かにありますね。真夏のラオスは、日本では経験したことのない灼けるような暑さなんです。こういう場所で生き長らえた種は、涼しいところで育つ種とは持っているものが違うだろうと現地を訪れて感じるものがありました。
―ご自身が収集したものが将来の育種に使われると良いですね。
柿崎●先日私のアブラナ科の研究で欲しい形質を持った遺伝資源を探していたところ、所属ユニットに20年以上前に在籍していた大先輩が集めてきたものの中に、すごい特性を持つものが出てきました。今回のキルギスで収集したものの中に、何十年後、私が死んだ後かもしれませんが(笑)、そのときの育種の情勢に沿った、有用な形質をもつ系統があったらうれしいなと思いますね。

