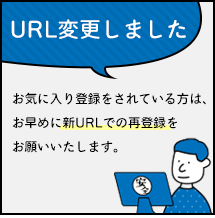活用してもらえるマニュアルとは
R3年9月 志藤 博克
従業員を雇用する農場では、農作業事故を防ぐための手順書やマニュアルを作られているかと思います。しかし、せっかく苦労して作ったのに活用されない、という悩みを抱えられている方も少なくないのではないでしょうか?
手順書やマニュアルに書かれる項目には、事故を起こさないために必要な理由がそれぞれあります。理由は、木に例えると幹の部分に当たり、各項目は枝葉となります。まず、幹をしっかり見定めることができれば、木全体の形が把握でき、どのあたりに枝葉が付いているのかがわかります。つまり、なぜ事故が起こるのかをしっかりと理解できれば、具体的にどうしたらよいかも自ずとわかってきます。
例えば、脚立を使う際には「天板に乗ってはいけない」「登って良いのは上から2段目の踏さんまで」「ヘルメットを被る」「傾斜や凸凹がある場所には脚立を置かない」等といったルールがあります。これらを字面だけで暗記しようとすると、どれか一つくらいは忘れてしまいそうです。そこで、そもそもの理由を考えてみます。脚立での作業に伴う危険は転落です。転落する理由を考えると「脚立から大きく身を乗り出してバランスを崩す」「身体を支える所がない天板に乗る」「脚立がぐらつく」等が思い浮かぶと思います。
次に、転落しないための方策を考えます。「大きく身を乗り出さず、こまめに脚立の位置を移動する」「天板に乗ると身体を支えるものがないため、天板には乗らない」「膝下の部分を最上段の踏さんと天板で支えればバランスを保てる」「脚立がぐらつかないように、傾斜や凹凸のある所には設置しない」といった対応方法が浮かんできます。また、脚立での事故事例を知ることができれば、脚立くらいの高さでも転落して頭を打つと重傷を負い、場合によっては死んでしまうことも理解できます。そうすると「ヘルメットを被る」ことも大事であることに気付けるはずです。
このように、そもそもの理由が理解できれば、具体的な項目が思い浮かびやすいため、単に字面を暗記するよりも覚えやすいのではないでしょうか。このことを活用して、作業に携わるメンバー全員で対象となる作業毎に「事故に遭わないためにはどうしたらよいか」について議論し、出てきた意見をまとめれば、手順書やマニュアル作りに役立つのではないでしょうか?当事者同士で議論することで全員の意識に残りますし、ルールに対する認識も「担当者が決めたルールを守らされる」から「自分たちで決めたルールだから守る」に変わるのではないでしょうか?