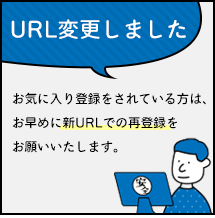世界の労働安全衛生の「前向き」な動き
R5年1月 冨田 宗樹
あけましておめでとうございます。昨年は新型コロナ感染に加え、国際情勢にも大きく揺さぶられた一年でした。今年はこれらが解決され、将来への足掛かりとできるような年となることを願っています。
昨年(2022年)5月に「ビジョンゼロ・サミット・ジャパン2022」が開催され、労働安全衛生に関わる世界中の国際機関、公的機関及び民間企業から参加がありました。また、今回のサミットでは、初めて「農業」に関する分科会が設置されました。
私がこの会議に関わる中で、大きく2つの気付きがありました。
1点目は、農業での労働安全衛生について、欧州各国も日本と同じような問題 -事故情報が十分に収集されておらず、組織的な支援体制も不十分- を抱えていることです。これは、労働安全衛生の基本的な枠組みが、雇用されて働く人の保護であることに対し、農業は個人経営が中心であるために、これが当てはまらないことに起因します。そのため、欧州でも、他産業と比較した農業部門の労働災害の多さが問題となっているとのことでした。
2点目は、他産業を含む世界的な労働安全衛生の動きとして、「労働安全=労働災害防止」を超えて、それぞれの働く人にとっての仕事や職場の「価値」をいかに高めるかという点に視点が移りつつあることです。そこでは、「災害がないこと」は前提であり、それも含めた「あるべき姿」「実現したい価値」といったその職場の目指す「目的地」を明らかにすることが求められます。目指す未来のために、今やれること、やるべきことを行っていくという、時間軸の上でもメンタルな面でも「前向き」な取組が進められているのです。
農業分科会においても、鹿児島のある生産者様より、そのような実践のご紹介がありました。働きやすい職場を作ることで、付加価値の高い生産物を効率的にお届けし、その収益によってさらに職場をよくするという「あるべき姿」を明確に持っておられ、そのために、今できる改善を、日常的に行う作業・確認といったレベルからほ場内の機械作業経路の改修に至るまで、地道に着実に積み上げていく取組を紹介されていました。海外からの参加者にも強い感銘を与えたものと思います。
農作業安全は、義務として負う「重荷」ではなく、思い描いた営農をいつか実現するために、なくてはならない土台です。世界的にも課題は多く、簡単に答えの出ない分野ではありますが、世界に先駆けた取組を我が国から生み出せるよう、皆様とともに進んで参りたいという思いを新たにしています。