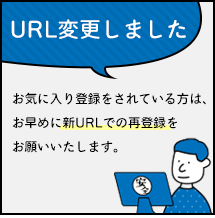「5S」と農業
R7年6月 小林 慶彦
以前、フランスでトラクタ生産の工場を見学したことがありました。大型のトラクタが素早く組み立てられていく様子に驚きましたが、もう一つ印象に残ったのは工場が整然としていることでした。工場内は片付いていて、スムーズに作業が行われていました。
日本でも職場環境改善の取り組みが盛んで、自動車メーカーなど製造業では「5S」が広く取り組まれています。5Sとは、整理、整頓、清掃、清潔、躾の頭文字Sを取ったもので、改善活動の第一歩と位置づけられています。5Sは作業の効率化だけでなく、事故の防止にも役立つことから、製造業、医療などで実践がさかんですが、農業分野でも事業者を中心に取り組みが行われています。
最初の2Sである「整理・整頓」と聞くと、モノをきれいに並べることを想像しますが、ここでの意味は異なります。整理とは「必要なものと不要なものを区別し、不要なものを直ちに処分すること」、整頓とは「必要なものが必要なときにすぐ使えるように置き場を決め、表示すること」です。(※1)
まずはいらないモノを減らし(=整理)、その後に使いやすく置き場を決めていく作業(=整頓)を行います。まずはモノを減らす「整理」が、現場を改善することに繋がります。
農業においては、倉庫に放置されている農機具、使用していない資材などが発生しがちです。これらを廃棄し、使用頻度の高い資材を使いやすく配置することは、作業をスムーズに進めることに繋がります。これによって、作業に余裕が生まれ、事故の遠因となる慌ただしい作業が減少します。また、歩行時につまずくことによる転倒や、機械やモノにぶつかったり、挟まれたりするリスクも減少します。点検が容易になるので農機具の不具合にも気づきやすくなるほか、必要な道具がすぐ使えるので、機械の 整備も必要時に適切に行えます。
そうはいっても、今後使えるかもしれない、捨てるにはもったいないモノは、つい取っておきたくなります。判断に迷ったときには、1年以上使用していないモノは廃棄する、とりあえず一時置き場に移動して保管期間を過ぎたら捨てるなどの方法が、よく使われます。全員参加で、不要なモノに理由や保管期限などを書いた赤い紙を貼りつけていく「赤札作戦」も、なにが不要品か一目で分かるため効果的とされています。
まずは、長年使っていないモノをひとつ捨ててみませんか。
https://orsj-ml.org/orwiki/wiki/index.php?title=5S_(生産システムにおける) (2025年4月4日)