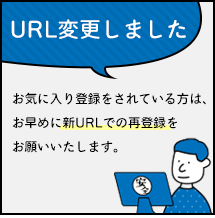高齢者と安全
H16年4月 中野 丹
先日、NHKで「家庭内事故を防げ」という番組があった。それによると、厚生労働省の調査では、1992年から10年間で不慮の死亡者数(かっこ内は65才以上の高齢者)は、交通事故で15,828人から11,743人(4,746人)に減少しているが、家庭内事故は6,560人から11,109人(8,368人)に増加しており、高齢者に限ると家庭内事故は交通事故のおよそ1.7倍にも上っているとの事である。
家庭内事故で多いものは、転倒、風呂で溺れる等で、転倒の原因としては、ちょっとした段差(じゅうたんのめくれ、畳の上の新聞紙やビニール袋等)との事で、一番安全と思われる家の中でこれだけの事故が発生している事には驚きである。安全対策として段差をなくすバリアフリー化を進めているが、それだけでは防ぎきれていないのが現状だそうである。
じゅうたんのめくれ等のちょっとしたものが重大事故につながるとは、今後、どのような対策をたてればよいのかと考え込んでしまう。関係機関でも家庭内事故を防ぎ高齢者の生活を支える機器を開発中ということであり期待したい。
農林水産省の農作業事故調査では、農作業事故に占める高齢者の割合は平成13年で72%を越えて増加の傾向にある。日本農作業学会でも最近の学会誌(通巻第117号、118号)で農村の高齢化に伴う農作業問題の特集を組んでいる。その中で、農村は都市に比べ20年程度高齢化が先行しているとの報告もある。
これからの農作業安全対策を考えるためには、一般の高齢者対策を越えた対策の取り組みが必要ではないかと考えさせられた。