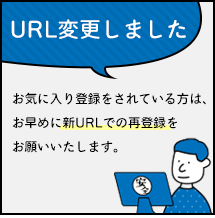理論の現場への適用
H27年1月 穴井 達也
新年あけましておめでとうございます。
年末年始に自動車で帰省したり、旅行に出かけられたりした方も多いと思います。自動車の旅でいやなものといえば渋滞です。ちょっとでも隙があれば、詰めたり、車線を変えたりしたくなるものです。
ところが、渋滞学の権威である東京大学の西成教授によると、車間を40mとれば理論的には渋滞は発生せず、従って、1kmくらいの渋滞のうちに、車間を40mとる車が現れると渋滞が次第にとれていくのだそうです。蛇足ですが、高速道路での渋滞では、隙を見つけ頻繁に車線変更をするより、ひたすら一番左の走行車線を走る方が早く抜けられるとのことです。
目から鱗の理論ですが、40mも車間があるとつい詰めたくなる人は多いでしょうね。そこで、渋滞対策として車間を40mとる車を数台渋滞吸収隊として走らせることを提案しているそうです。また、理論の普及の面では、講演の多くを小中学校で行っているそうです。子供は素直に親に話すし、10年後は本人が当事者になるということを考えてです。
農作業事故についても、われわれ生研センター(現:革新工学センター)の調査・分析などにより、防止するための注意すべきポイントがわかってきており、農作業事故防止運動などで現場に啓発普及されていますが、残念ながら農作業事故を目に見えて減らせるような提案までは出せていません。対象の性格が違うのですぐには渋滞学のようにはいきませんが、異分野での取組や研究成果の伝え方なども研究し、効果的な提案ができるようにならなくてはいけないと年頭に当たり考えさせられました。