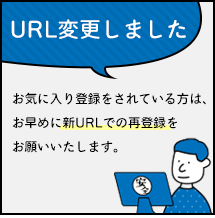安全への意識と安全な環境を
H31年4月 下元耕太
4月になり、暖かくなってまいりました。これから、ほ場に出て作業することも多くなると思います。しかし、農作業が本格的に始まるということは、事故に遭う可能性も多くなるということです。月別の農作業中の死亡事故数を過去5年間の合計でみますと、4月から10月にかけて高く推移しています(梅雨の6月以外は年間の上位1~6位を占める「平成 29 年に発生した農作業死亡事故の概要」, 農林水産省)。是非、気を引き締めてこれからの作業をお願い致します。
造船関係で働いていた友人から、作業場で人とすれ違う際の挨拶は「ご安全に」と言うのだと聞いたことがあります。常にお互いの安全に気を配り、自分たちは危険と隣り合わせの作業をしているといった意識を忘れないようにするためだと思います。農水省が発表している「10万人あたり死亡事故発生件数」等をみますと、農業は年間約16件/10万人(建設業は約6件/10万人、交通事故は約3件/10万人)と、死亡事故の割合が高い産業になってしまっていることをご存知でしょうか。
農業は人間の力を凌駕する「自然」と「機械」を同時に相手にする危険と隣り合わせの作業という意識を持っていきましょう。
また、安全に対する意識(気持ち)はもちろん大事ですが、気を付けるだけでは防げません。安全のために、機械や環境などの対策も一度考えていただければと思います。危険になりやすい環境の一つに、ほ場への進入路があげられます。農林水産省農村振興局による土地改良事業計画設計基準 計画「ほ場整備(水田)」 (平成25年)では、進入路についてそれぞれ下記のような記述があります。
①進入路の勾配については、「12°以下とすることが望ましい」
②進入路の幅員については、「4m以上の幅員を有することが望ましい」
③傾斜地における進入路については、「スリップ防止のための舗装を行う等の十分な安全対策を講じた進入路としなければならない」
今まで問題なかったからといって、今日も問題ないと安心してはいけません。安心と安全は違います。「安心」を疑いましょう(H30年12月コラム) 。物事を客観的に判断するには、数字にすることが大切です。今はスマホで角度や距離を計測できる時代です。もちろん、メジャーや角度計を使用しても構いません。まずは、ほ場の進入路を測ってみるところから始めてみてはいかがでしょうか。