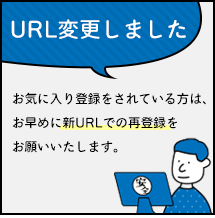安全に関する技術の協調
R1年9月 山﨑裕文
農業機械や自動車においては、現在ロボット農機や自動運転車の研究開発が盛んに行われています。普及には、安全性の確保が必須であることは言うまでもありません。このような安全に関する研究開発は、多くの公費を投入して産官学協調で行えないのだろうか、と考えることがあります。既に多くの分野で公費が投入されていますが、当然特許等の関係もあり各研究成果を誰もが自由に使用できるようにはなっていません。
自動車業界の一例ですが、今年の4月に、ある大手自動車メーカーが、ハイブリッド車(HV)開発で培ったモーター・PCU(Power Control Unit)・システム制御等車両電動化技術の特許実施権を無償で提供するとプレスリリースされました。この対応に関して、様々な考察が行われていましたが、HVの製造コストを下げるために特許を公開したのでは、との意見が掲載されていました。この自動車メーカーのプレスリリースでは、副社長の言葉として、車両システムの電動化が進むと考えられるこの先の10年について、「今こそ協調して取り組む時だ」と記載があります。
農業機械の安全技術に関する研究においても、このように協調して取り組めないものでしょうか。農業従事者が大幅に減少し、一人当たりの耕作面積が増加している現在、ロボット農機の普及は日本の農業における生命線になります。開発にかけるコストを皆で減らし、安全に使えるロボット農機を、少しでも安い価格で少しでも多くの人に普及させるべく、組織の垣根を越えた枠組みが形成されることを妄想しています。簡単なことではありませんが、開発に困っている人が容易に情報交換できるグループの発足ができれば、足掛かりにはなるかもしれませんので、学会等も活用しながら、何かできることがないか模索したいと思います。
現在、自動化農機をご使用の方々におかれましては、ヒヤリやハットした際の情報を、ぜひ各メーカーに積極的にお寄せいただき、現場の意見を開発に反映していただけますと幸いです。