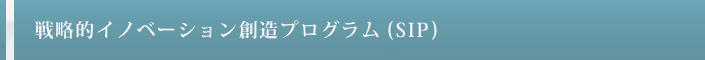第2期 スマートバイオ産業・農業基盤技術
第1回
農業はデータサイエンスのフロンティア
境界領域だからこそ国のプロジェクトでやる意味がある


「Creative Researchers」では、「SIPスマートバイオ産業・農業基盤技術」の研究者に焦点をあて、インタビューを通じて研究の意義とその魅力を伝えていきます。第1回は、「持続可能な循環型社会を実現する『農業環境エンジニアリングシステム』の開発」研究責任者を務める市橋泰範さん(理化学研究所 バイオリソース研究センター 植物-微生物共生研究開発チーム チームリーダー)にお話をうかがいました。
――「農業環境エンジニアリングシステム」の概要について教えて下さい。何を目指す研究なのでしょうか。
市橋:キャッチフレーズ的に言えば、「豊かな土を作り、人々を健康にする」という取り組みです。豊かな土は植物を育み、植物は最終的には食につながって、人々を健康に、笑顔にするというつながりを意識して研究を進めています。その豊かな土作りのために、微生物と有機成分に着目しました。
SIPバイオ農業が目指す「スマートフードシステム」は、生産現場から加工、流通、販売、消費、そして資源循環によって生産現場に戻る円環を実現します。その中で我々の「農業環境エンジニアリングシステム」コンソーシアムは、生産現場と資源循環を結びつけるために、作物生産現場で利用できる土作りを中心とした農業技術の開発、その開発のためのバイオデジタル化技術の開発と、開発した技術の評価に取り組んでいます。
――土というのは、植物が育つ環境ということですよね。その中にいる微生物が、植物の生育に大きな影響を与えているということですか?
市橋:現在の農業は、土壌の無機成分を測定し、調整するために化成肥料を施肥することで収量を増やしています。植物は土中の無機成分を吸収して成長するという、1840年にリービッヒが提唱した無機栄養説に立脚しており、ハーバー・ボッシュ法という、高圧なエネルギーによって空気中の窒素を化成肥料にする技術が発明されたことで世界の人口増加に伴う食料の安定供給を支えています。
ところが、化成肥料を使いすぎたことで、環境問題や地球温暖化といった弊害が生じています。環境に負荷を与えず、収量を増やしていくためには、化成肥料に頼った農業を見直す必要があるというのが現在の課題です。
そこで我々が注目しているのが日本の伝統的な農業です。日本の伝統農業は土作りを非常に大切にしているのですが、やり方は現代農業とは違って、微生物や複雑な化合物が代謝されて植物に利用されていくというプロセスをうまく利用することで持続可能性を担保しています。例えば、落ち葉の堆肥化による土作りで次の植物を育てるといったことです。このシステムを上手く利用した農業を、科学の枠組みに入れ込みたいのですが、非常に複雑でこれまでアンタッチャブルな領域でした。ここをデジタル化によってうまく理解することで、新しい農業技術を確立したいと考えています。
 微生物を利用した農業資材として、土中のリン酸を植物に供給する「アーバスキュラー菌根菌」に着目。イネ、クローバー、ネギを使って、作用を研究している。
微生物を利用した農業資材として、土中のリン酸を植物に供給する「アーバスキュラー菌根菌」に着目。イネ、クローバー、ネギを使って、作用を研究している。
――農学分野だけではなく、化学、生物学、情報科学などさまざまな分野の専門家が必要になりそうです。
市橋:そうですね。さらに生物学の中でも、植物、土壌、微生物などが複雑に絡まっているので、個々の分野は発展していてもその境界領域はなかなか難しい。そこをSIPのような国家プロジェクトでやる意味があると思っています。
研究者としては、若手・中堅で集めたメンバーに、アドバイザーとして各分野の大御所の先生に入っていただいています。また、バイオデジタル化というキーワードに関連したシーズ技術を持つ17の民間企業・研究機関に参画いただき、農学分野を超えた異例の産学連携が実現しています。この分野は、通常であれば競争相手を意識した研究成果の囲い込みが起こりがちなのですが、このコンソーシアムでは参画機関がデータをシェアして、そのデータから新しいものを作っていく、オープンイノベーションを目指しています。

――バイオデジタル化技術についてもう少し詳しく教えて下さい。
市橋:一言で表すとすれば、「実験室内の理化学装置を使って、あらゆるものを測定する技術」と言えます。従来の農学の研究だと、土壌化学性、物理性、生物性、あと作物もあわせて30データ項目程度でやっていたのを、最新技術を使えば数万データ項目を測定可能になります。これまでと比較にならない解像度でさまざまな物事を見ることができるようになります。世界中を見ても他にアプローチはされておらず、独自性の高い手法です。
 次世代シーケンサーの前処理に使用している分注器。試料を一度に大量に作成するために欠かせない。
次世代シーケンサーの前処理に使用している分注器。試料を一度に大量に作成するために欠かせない。
今、国内の農業の現場で行われている土壌診断では、だいたい物理化学性だけを見ています。一方で、世界に目を向けると、アメリカを中心に、土壌の生物性がとても注目を浴びていて、そこでもう一大ビジネスが始まっている。日本はその点で出遅れています。ですが、我々の研究は生物性も全部取り入れた多角的な取り組みで、世界的にも一歩先をいく強みがあるので、新しい展開を目指しています。
――測定した結果をどのように新しい農法開発へとつなげていくのですか。
市橋:短期的には今ある技術の評価、長期的には集まったデータから新しいものを作り出す、ということですね。我々のコンソーシアムでは福島県郡山市の農業総合センターの圃場で、参画企業の皆さんに新しい農法や資材をどんどん投入してもらって、コンペのような形で我々の技術で多角的に評価しています。こうして一括して集めたデータから、農地に何を加えるとどうなる、という作用機序を見いだせる。すると、この原理に基づく予測が可能になり、新しい知見を応用に活用できます。
現状は、作物、微生物、土壌それぞれのデータベースは存在するのですが、その間が全くつながっておらず、最終的な生産現場や農家やビジネスになかなかつながらない。ここをうまく横断検索できるのりしろになるようなデータを我々のコンソーシアムから出していきたいです。つながってWAGRIのように連携したデータベースで管理することで、アクセスした企業が上手く利用して新しいビジネスを始めるといった、新しい農業の世界観ができてくると思っていますし、我々はそこにコミットしたいと考えています。

――先生ご自身が土壌に興味を持たれたのは何がきっかけだったのでしょうか。
市橋:もともとは植物の発生学で学位を取得して、植物の多様性に関わる遺伝子制御ネットワークの研究をしていました。フィールドに目を向けた研究をやろうということで、2016年に「植物-マイクロバイオータ超個体の生命活動ネットワーク解明」というテーマでJSTのさきがけ研究者に採択していただきました。
この時に、生態系の中で植物はさまざまな微生物と相互作用して1つの個体として振舞っているのではないか、という概念を提唱したんです。人間も、人間の細胞だけではなく、腸内フローラなども含めた一括のシステムとして、超個体として生きているという話を聞いて、それはそのまま植物に当てはまると思ったんですね。植物と周辺の微生物をまとめてアメリカの研究室で開発していた次世代シーケンサーなどの大規模解析技術で解析することで、さまざまな複雑な関係性が見えてくるのではないかというのが、研究の大元になったコンセプトです。今までになかった手法ですが、アプローチはこれまで私が取り組んできた遺伝子制御ネットワークの研究と同じです。
――植物細胞の遺伝子の解析と微生物の解析が同じ手法でできるんですね。
市橋:マイクロバイオームという、さまざまな微生物がどこにいるかを数値データで解析しているのを見せてもらった時に、今まで自分が細胞内での遺伝子発現データでやっていた解析とほとんど同じことをやっていることに気づきました。マルチオミクス解析という手法で、医療領域ではセントラルドグマを階層構造で分析するために、DNA、RNA、プロテイン、代謝物それぞれをオミクス解析する手法が既に導入されています。新しい手法をいち早く農学分野に取り入れることができたということは、我々はラッキーだったと思っています。

――とはいえ、発生学と農学では、全く扱うテーマが違いますよね。同じ手法が適用できるとはいえ、躊躇はなかったのでしょうか。
市橋:発生学って、やはり基礎研究で、教科書レベルの話なんですよ。そこにまだまだ自分よりも研究レベルが上の先輩方がいらっしゃる。私自身がこれから研究者としてやっていくために、もう少し社会に必要とされる分野を模索しないといけないと思っていたところで、 農業は今までデータサイエンスが十分に活用されていなかった。非常に大きなフロンティアを感じて飛び込んだんです。
もともと理学出身なので、誰も知らなかったことが分かるとワクワクするということはもちろんあります。でも、研究のやりがいってなんだろう、と突き詰めて考えると、ワクワクすることはもちろん大事なんですけど、科学の力で社会貢献ができるというところにあるのかなと思います。社会の一構成員として自分が貢献している実感を持てる仕事をしたいと私自身も思っていますし、チームメンバーにヒアリングしても、若い人はだいたいそういうことを考えています。
楽しいことをやってお金がもらえるということだけでは、短期的にはよくても、人生を考えると物足りないと思うんですよね。SIPのような国家プロジェクトでサイエンスをやって、論文を書いてプレスリリースをすることで、少しでも社会の役に立てたと思える瞬間はとても嬉しいし、チームとして関わったことで自分自身の仕事に誇りがもてる。そういうことって重要なんだと思います。
 今より少し未来の2300年には、ギフトとしてさまざまな機能を持つ土が贈られる時代が来るかもしれない。(バイオリソース研究センター一般公開2019の展示より)
今より少し未来の2300年には、ギフトとしてさまざまな機能を持つ土が贈られる時代が来るかもしれない。(バイオリソース研究センター一般公開2019の展示より)
――これから研究者を目指す人にメッセージをお願いします。
市橋:まず一つめが、先程も言った通り、今はチャンスだということ。テクノロジーが進歩してきて、我々が使っている最新のデジタル化技術のようなものが、手軽に、気軽に、予算もわりと格安で試せる。また、テクノロジーの進歩で、分野の垣根もだんだん飛び越えやすくなっています。本当に深いところまでは無理でも、ある程度の情報はネット上で補って、異分野とのコミュニケーションができるようになっています。
今はコロナの影響で仕事の本質が見直されている状況です。言い換えると、想像力をたくましくして夢を実現できる時代が来たという気がするんです。農学はまだまだそういうところが、ほかの分野に対しては遅れている部分なので、ここは若い世代にとってチャンスだと思っています。
食という分野は医療に比べると単価が安いので、なかなかビジネスにつながりづらい部分はあります。でも、「衣食住」という人間が生きるために必須の要素なので、絶対に無くなることはない。なので、ここでいろいろなことを考えて試すということが多くのチャンスに繋がる分野だと思っています。
そしてもう一つが、共創しましょう、ということ。アメリカやヨーロッパでのビッグサイエンス化の流れは止められないと思うんです。これと戦い勝つためには、オールジャパンで、研究者だけではなくSIPのような産学官が上手く連携すること、そして流行り物のテーマに乗っかるのではなく、日本のユニークさを打ち出していくことが求められています。調和や共生を大事にする日本の文化で育った研究者による協力体制が必要だと思っているので、若い研究者の方にはぜひこのフロンティアに来ていただきたいですね。
――ありがとうございました。


市橋 泰範(いちはし・やすのり)
理化学研究所 バイオリソース研究センター 植物−微生物共生研究開発チーム チームリーダー。
2010年 東京大学大学院理学系研究科博士課程修了 理学博士。2010年 University of California Davis Postdoctoral fellow。2014年 国立研究開発法人 理化学研究所 基礎科学特別研究員。2016年 国立研究開発法人 科学技術振興機構 さきがけ研究者。2018年 国立研究開発法人 理化学研究所 バイオリソース研究センター チームリーダー、内閣府戦略的イノベーション創造プログラム「スマートバイオ産業・農業基盤技術」(SIP第2期) 農業環境エンジニアリング研究コンソーシアム 研究代表。専門は、植物生理、植物微生物相互作用。