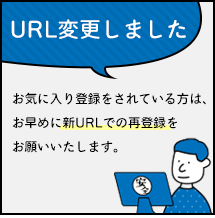点検・整備・清掃に関するコラムの一覧です
点検・整備・清掃に関するコラムの一覧です
 マンガで描かれた農作業事故
マンガで描かれた農作業事故
今回は農家のエピソードや農業の蘊蓄(うんちく)がコミカルに描かれているマンガ「百姓貴族」について農作業事故に関する部分を紹介します。作者は少年マンガ「鋼の錬金術・・・
 繁忙期。でも、お願いします
繁忙期。でも、お願いします
4月です。だんだんと暖かくなり、新入生や新社会人の方たちが期待と不安を抱いて新たな生5月になりました。新緑が美しく、風も心地よくて過ごしやすいのか、私も・・・
 「ゆっくりなら危なくない」?
「ゆっくりなら危なくない」?
農作業事故の現地調査を行っていると、「同じような事故が日本中で繰り返し起きている」ということを実感します。そのなかで今回は、農機の回転部に手が巻き込まれ・・・
 使用している刈刃に異常はありませんか?
使用している刈刃に異常はありませんか?
草刈りのシーズンがやってきました。刈払機で切っても切ってもまた生えてくる雑草の生命力にゲンナリすると同時に、そのたくましさを尊敬してしまうこともありますが・・・
 機械は小さくても安全装備は重機と同等である
機械は小さくても安全装備は重機と同等である
最近、あるテレビ番組で麺は小麦から、スープは素材を採取するところからラーメンを作るという企画が始まりました。この番組を見るようになったきっかけは、別の・・・
 取扱説明書に書かれていないこと
取扱説明書に書かれていないこと
以前にこのコラムでは、取扱説明書の重要性や読みやすいものをつくる難しさにふれましたが、筆者が安全鑑定を担当するコンバインでは特に強くそれを感じます。コンバインは・・・
 手軽に使えるカセットガス農機
手軽に使えるカセットガス農機
最近、刈払機や歩行型トラクタでは、ガソリンではなく、カセットガスを燃料としてエンジンを動かすものが市販されており、耕うん機の場合、カタログによれば、1本の・・・
 収穫作業も安全にお願いします
収穫作業も安全にお願いします
いよいよ9月となり、本格的な農作物の収穫シーズンを迎えることになりました。農林水産省の「2011年秋の農作業安全確認運動」(9月1日~10月31日)も始まります・・・
 被災地域での農作業について
被災地域での農作業について
東日本大震災から一カ月以上経ち、復旧、復興までの道が見えない状況の中でも、営農に向けた準備に取り組んでおられる方も多いかと存じます。農水省から技術指導者に・・・
 刈払機の飛散物防護カバーの基準改正
刈払機の飛散物防護カバーの基準改正
年が明けて早1ヶ月が経ちました。寒い日が続いており、草刈りシーズンはまだまだ先ですが、シーズンオフの今、あらためて刈払機の安全装備である飛散物防護カバーに・・・
 シーズンオフこそ安全対策を
シーズンオフこそ安全対策を
皆さんの中には、多忙な秋作業シーズンも終わり、来年に向けた準備に余念のない方も多いかと思います。皆さんは、今シーズン、農作業中にヒヤリとしたことがなかった・・・
 農作業安全講習のすすめ
農作業安全講習のすすめ
先日、フォークリフト運転技能講習会、玉掛け技能講習を受講しました。少し難しい話になりますが、最大荷重が1トン以上のフォークリフトを運転する場合、また、つり上げ・・・
 「農機安全eラーニング」完成版を・・・
「農機安全eラーニング」完成版を・・・
農作業による死亡事故の原因別では、農業機械作業に伴うものが7割を占めており、機械の安全な使用方法について正しい知識を身につけることは非常に重要となっています。・・・
 農作業安全月間の前に
農作業安全月間の前に
少し前のことですが、昨年9月にアメリカのオバマ大統領より農作業安全週間に関する声明が発表されました。この週間は、1944年から行われているもので長い歴史を持つ、・・・
 取扱説明書、読んでいますか?-その2
取扱説明書、読んでいますか?-その2
6月コラムで、農業機械における取扱説明書の重要性と、一方で内容が増えて複雑化する傾向にあり、読みやすいものを作るのは簡単でないことを書きました。これは農業・・・
 取扱説明書、読んでいますか?-その1
取扱説明書、読んでいますか?-その1
今年度から安全コラムを担当することになりました。どうぞよろしくお願いいたします。3月までは主に乗用トラクターの検査鑑定業務を担当しておりました。このうち安全・・・
 安全衛生管理委員になって
安全衛生管理委員になって
私ごとですが、先月から職場の安全衛生管理委員をおおせつかり、さっそく、安全衛生管理研修と安全衛生パトロールの機会がありました。研修は1日がかりのもので、労働・・・
 情報の共有による危険回避
情報の共有による危険回避
宮沢賢治の詩「雨ニモマケズ」をもじって「雨ニモアテズ」という詩が、最近の子供たちの雰囲気をよく表し、話題になっているそうです(掲載ホームページ1)。この詩・・・
 悪いことは重なる!
悪いことは重なる!
インターネット上のフリー百科事典『ウィキペディア』に、航空機に乗って死亡事故に遭遇する確率は0.0009%であるという記述があります。航空機事故はめったに起きない・・・
 そろそろ春作業の準備を -バッテリ・・・
そろそろ春作業の準備を -バッテリ・・・
立春を迎えたとはいえ、「春は名のみの~」と歌われているように、日射しが強くなってくる半面、寒さはまだ続きそうです。木々の芽が少しずつ膨らんで新しい季節への・・・