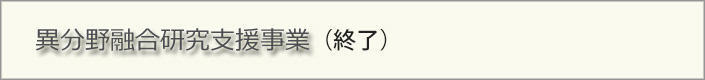技術コーディネーター
堤 裕昭(熊本県立大学)
コンソーシアム参加機関
熊本県立大学、東京大学海洋研究所、株式会社多自然テクノワークス、株式会社恵天
研究内容
海水の交換量の少ない内湾の生け簀を用いた魚類養殖漁業が、好適な養殖環境を維持し、持続可能な養殖システムの確立をめざして、
- 生け簀直下の海底に堆積した有機汚泥を、有機物の分解能力に優れたイトゴカイ(多毛類)およびその共生菌の培養コロニーを用いて浄化する生物浄化技術を開発する。
- 魚類養殖場専用のマイクロバブル発生装置を開発し、生け簀の水質およびその直下の海底の水質改善を行い、養殖魚の溶存酸素濃度低下からの保護と、生け簀直下の海底に堆積した有機汚泥に散布したイトゴカイおよびその共生菌の働きを助ける。
中間評価結果概要
課題に対して現場海域における実証的な調査・研究を遂行するだけでなく、研究室レベルでの新しい方法論も生み出しながら前進しており、成果の産業的応用が切に望まれると評価できる。また、困難が故に研究者が避けてきた難しい細菌の機能研究を含めており、学術的にも高度な成果を挙げている。
一方、水質改善に効いているのが、マイクロバブルなのか、イトゴカイなのか、または双方の相乗効果なのかをはっきりさせるような実験配置及び例数の改善をフィールドで工夫されたい。このためには、現場と大学が一層連携を強化されることを期待したい。加えて、今後、微生物活性とイトゴカイの活動、有機物分解の事実についての現場効果の観測を含めた更なる調査が望まれる。
研究成果も積極的に公表されているが、高レベルの研究成果から考えると、なお一層の努力が必要と考えられる。インパクト・ファクターの高い国際誌への投稿が切に望まれる。
なお、本技術が現場で展開されることを考慮し、物質名や基準値の表し方について、水産用水基準にある底質の環境基準に準拠することが望ましい。