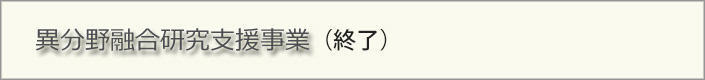技術コーディネーター
川田 元滋((独)農研機構中央農業総合研究センター)
参画機関
(独)農研機構中央農業総合研究センター、(独)農研機構作物研究所、新潟薬科大学、クミアイ化学工業(株)、ケイ・アイ化成(株)
【研究内容】
アブラナ科作物由来の抗菌蛋白質ディフェンシンは幅広い抗菌活性を示すことが知られ、これを新規天然抗菌剤として実用化することをねらいにしている。ディフェンシン蛋白質の機能が増強された複数の改変遺伝子について、各種抗菌活性試験により産業用、農業用および家庭用抗菌剤としての用途を明らかにして、商品化に向けた大規模製剤化試験を行い、実用的生産レベルでの生産・精製システムを確立する。さらに抗菌活性に関わる遺伝子構造および作用機作に関わる新知見を蓄積し、天然抗菌剤製品の付加価値向上に役立てる。最終的には、消費者から根強く求められている、環境にやさしく安全性が高い天然抗菌剤の製品化を目指している。
【中間評価結果概要】
総体的には当初の中間目標に近いレベルの研究が実施されている。今後は知的財産権と論文受理に全力を傾けるべきである。
これまでの研究では、塩基置換による9種の機能増強型抗菌蛋白が得られており、どれを最終候補化合物とするかを速やかに決定すべきである。
カラシナ由来の抗菌蛋白は、標的分子が従来のディフェンシンと異なり、殺藻効果が認められ、殺菌効果の及ぶスペクトルが広い、という特徴が明らかになった。ディフェンシン蛋白を抗菌剤として、早期に商品化を図る応用的研究にシフトすべきである。そのためには、大量調製、安全性評価、実用性評価に傾注し、実行予算も見直すべきと考える。
最終的に農薬として水稲等の病原菌や殺藻剤として商品化を進める場合には、水質汚濁、水生生物への影響に対する安全性試験を十分に配慮して計画、実施する必要がある。とくに、殺菌剤の殺スペクトラムが広いことはそれだけ安全性をチェックすべき生物種の範囲が広いことを意味するので、そのための対策を十分に講じるべきである。
本ディフェンシンが水稲等の抗菌剤、殺藻剤、真菌性皮膚病への外用薬としての可能性を持つことは良いが、最終的なターゲットを絞ることが重要である。