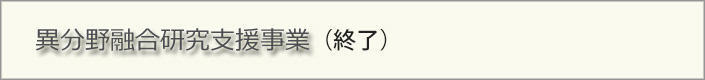技術コーディネーター
天野 良彦(信州大学)
参画機関
信州大学、(株)東芝、(独)農研機構食品総合研究所、日研化成(株)
【研究内容】
地域未利用バイオマス資源のキノコ培地残渣を産業素材として変換利用するため、効率良く可溶化し酵素変換するための要素技術を開発しリアクターシステム化するとともに、溶出したβ-オリゴ糖を機能性食品素材として、あるいは不溶残渣リグノセルロースを電機産業用絶縁構造材料として利用する応用技術を開発する。これらの開発素材を利活用する新事業の創出が期待されるとともに、わが国の環境保全と資源開発問題の解決に資することが期待される。
【中間評価結果概要】
研究全体の進捗は概ね順調であり、地域特色を活かし産業廃棄物を有効利用するバイオマス変換技術開発研究として期待される。廃棄物からキシロオリゴ糖等有用成分を大量に回収できるのであれば、マテリアルバランスに基づく実用化の検討は価値が十分にある。
概して「産」がリードし「独」と「学」は遅れている。後者の研究が「技術の開発」に追いついておらず、技術連携・融合にまで到達していない機関があり、全体としてバランスのとれた研究進展になるよう、チーム間の十分な対話と相互連携が必要である。
可溶化・固液分離用の高圧水熱反応リアクターと後段の素材変換用酵素リアクターとを分離機を介して連結する「ハイブリッドリアクター」を提案しているが、各単位操作の処理速度を合わせる連続操作は難しいと思われる。従って、高圧水熱処理工程と酵素処理工程とを厳密に分離し、連続操作を考えないシステムの検討も選択枝に入れるべきである。また、バイオマス成分を可溶化する技術として導入した、本事業の鍵となる高圧水熱反応について、他の類似の可溶化反応と比較検討し、この高圧水熱反応過程にそれらを上回るメリットについて充分説明する必要がある。
本研究の出口のオリゴ糖と絶縁材料では、各生産必要規模が数桁のオーダーで異なるものと思われ、物質収支を念頭に置いたデータ解析と説明が必要である。実機製造にあたっては、イニシャルコストのみでなく、市場見通し、ランニングコスト、廃菌床の発生量とのバランスなどへの注意が必要である。
キノコ培地残渣以外の未利用バイオマスをも考慮するなら、バイオマス素材のオリジンによる組成差異の把握や、各ステップでの生成物組成が元のキノコ培地残渣の組成と質・量的にどう違うかを把握する必要がある。