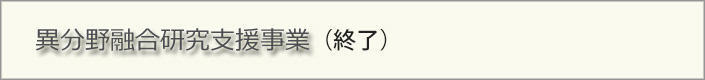技術コーディネーター
近藤 昭彦(神戸大学)
参画機関
神戸大学、月桂冠(株)、京都大学、関西化学機械製作(株)、三栄源エフ・エフ・アイ(株)
【研究内容】
醸造微生物である麹菌や酵母のゲノム情報を活用して、希少価値の高い機能性糖質(イソフラボンアグリコン、γ-サイクロデキストリン)、機能性ペプチド(アンセリン、フェリクシン、酒粕分解ペプチド)、機能性脂質(酵素フレーバー)などの食品素材を自在に生産できるバイオコンバージョンシステムを開発する。具体的には酵母と麹菌のゲノム情報から有望な酵素遺伝子を抽出し、酵母あるいは麹菌への細胞表層提示技術とハイスループットスクリーニング技術を利用して酵素機能を飛躍的に向上させたスーパー醸造微生物株を創出し、さらにそれらを用いた機能性食品素材の生産・回収・精製プロセスを開発する。またそれら素材の特性解明と食品への応用を検討する。
【中間評価結果概要】
技術コーディネーターは全体をうまくまとめて研究を実施しており、全体としておおむね順調に進行している。今後も現在の研究計画に沿って進めて良いところが大部分であるが、プロセス化の分担課題については以下のようなテコ入れが必要と思われる。
すなわち、新規遺伝子の単離、機能解析は十分な努力が感じられ、細胞表層提示技術の確立は、酵母細胞では順調であると思われるが、麹菌では未知なことが多く、一層の努力が望まれる。ハイスループットスクリーニングはこれまでの蓄積も有り、順調である。
一方、バイオプロセスのプラント設計とプロセスの最適化では、本事業が生産を目的としている観点からみると、表層提示細胞を固定化してフレーバー改良に使うことには無理があるように感じられる。組換え微生物を使わないシステムの方が実用性が高いと思われるので、ぜひ検討頂きたい。
また、開発題目にある「安全な」を達成目標に入れるならば、具体的ターゲットを明示して評価しなければいけない。確かに清酒酵母と麹菌はGRASであるが、それの細胞表層提示体となれば遺伝子組換え微生物となり、GMOの大量工業培養の規制をクリアする必要があろう。 成果の公表は十分なされているが、特許等の出願が少ない。これはプロジェクト進行上のフェーズからいえば理解できる点もあるが、後半増やす努力が望まれる。