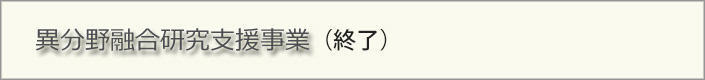技術コーディネーター
大竹 久夫(大阪大学)
参画機関
大阪大学、東和科学(株)、(株)神鋼環境ソリューション、小野田化学工業(株)、(財)日本土壌協会、神戸大学、下関三井化学(株)、広島大学
【研究内容】
下水処理で排出される余剰汚泥の加熱によって遊離するリンは、凝集沈殿させて人工リン鉱石として回収できる。人工リン鉱石は多くの不純物を含むため、その除去、改質技術を開発する。人工リン鉱石の工業原料としての有用性を天然リン鉱石と比較して評価する。人工リン鉱石を原料として、加工リン酸肥料等のリン酸質肥料および工業用リン酸を製造する技術を開発し、製品の有用性を圃場試験等により評価する。高エネルギー化合物であるポリリン酸の特性を利用し、その合成酵素を物質生産に応用する新たなバイオ技術を開発する。これらのリン回収、再利用システムのライフサイクルアセスメントを行い、リン資源リサイクルの事業性を評価する。
【中間評価結果概要】
人工リン鉱石の改質法、人工リン鉱石からの加工リン酸肥料及び工業用リン酸の製造法の開発等、研究成果を個々にみた場合には、過半の研究チームがほぼ目標を達成している。しかし、問題点の認識並びに研究の方向性について研究チーム間の相互理解、連携が不十分であり、コンソーシアムが全体として有効に機能していない。現状のままでは当初目標の達成が困難と懸念される。この点を改善するような研究計画の見直しが必要である。特に、リン肥料の製造時に問題となる人工リン鉱石中の有機質の扱いやその評価について、コンソーシアム全体の考え方を十分整理し、連携して研究を推進できるようにする必要がある。また、微生物のポリリン酸蓄積機能の解明や、ポリリン酸を活用するバイオ技術の開発では、学術的に貴重な成果を上げているものの、これらの成果を本事業の中でどう生かすかが必ずしも明確になっていない。このことについてもコンソーシアムとしての考え方を整理すべきである。
人工リン鉱石は天然リン鉱石に比べてはるかにコストが高いので、リン資源の回収、再利用のリサイクル事業化は困難と思われる。したがって、補助金等の政策面のアセスメントに加え、下水汚泥肥料、化成肥料等を含めた幅広い人工リン鉱石利用法も検討すべきであろう。
以上の通り研究期間の後半においては、技術コーディネーターの強い指導のもとに、コンソーシアムとしての共通目標を十分意識した研究計画の見直しと、それに基づいて各研究チームの相互理解と連携を強化した研究が実施されることを期待したい。
成果の発表、知的財産権の取得について、研究チームによってかなりの差がみられるので、技術コーディネーターの指導による改善を望みたい。