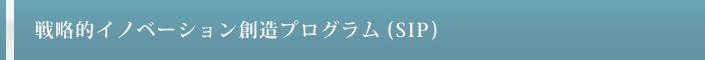第2期 スマートバイオ産業・農業基盤技術
第1回
長岡を微生物によるバイオコミュニティの総本山に

多くの微生物の活躍で、我々の日常生活は成り立っている。例えば、食卓に、納豆、チーズ、ヨーグルトにパンといった、発酵食品が並ぶ。酒も微生物によってアルコールを造り出す醸造というプロセスの産物だ。さらに、食品以外の分野でも微生物は活用されている。廃棄物の分解、医薬品製造を含む有用物質の産生が代表例だ。
こうした私たちの社会にとって有用なものとして利用されている微生物は、全ての微生物のほんの一部にすぎないと、SIP「スマートバイオ産業・農業基盤技術(以下SIPバイオ農業)」バイオ資源循環コンソーシアムの「微生物探索スクリーニング」チームの小笠原渉代表(長岡技術科学大学教授)は言う。
「人類が培養することができている微生物は全体の0.02%です。微生物の培養なんて簡単にできると思っている人が多いのですが」(小笠原代表)
つまり、私たちが知る微生物は極一部に過ぎず、知らない微生物のなかにはまだまだ有効なものが存在しているはず。しかし、膨大な微生物のなかから、ピンポイントで目的のものを探し出すのは非常に困難だ。「微生物探索スクリーニング」チームと小笠原代表は、効率よく目当ての微生物を探し出す技術の開発に取り組んでいる。
(参考:エマルションを用いた微生物探索 )
 長岡技術科学大学大学院工学研究科技術科学イノベーション専攻の小笠原渉教授
長岡技術科学大学大学院工学研究科技術科学イノベーション専攻の小笠原渉教授
同チームは、代表機関となる長岡技術科学大学の所在地である新潟県長岡市を拠点に、研究成果の社会実装に取り組んでいる。その社会実装のイメージを端的に示すと、同チームがこれまでに開発した「微生物探索スクリーニング」を組み合わせた「微生物探索プラットフォーム」を核にして、長岡市をバイオエコノミーの拠点化する試みだ。
小笠原代表は、長岡市の地元企業、大学、自治体を巻き込んで、資源循環によるバイオエコノミーを創出するための実証の場として「N.CYCLEプロジェクト」を立ち上げ、米に関わる資源循環を微生物によって実現しようとしている。長岡の「米どころ」「発酵・醸造の街」といった特色のひとつとして、「微生物の研究拠点」を加えようという野心的な試みだ。
そのN.CYCLEプロジェクトに対して、地元長岡は何を期待しているのか、そこから何が生まれようとしているのか、そのためにどんな取り組みを行っているのか、社会実装の現場でたずさわる人々に話を伺った。
 コシヒカリを生んだ新潟県長岡市は、日本有数の米どころ。イネが青々と育つN.CYCLEプロジェクトの試験田では5月の田植えから約1カ月が経ち、順調に生育している
コシヒカリを生んだ新潟県長岡市は、日本有数の米どころ。イネが青々と育つN.CYCLEプロジェクトの試験田では5月の田植えから約1カ月が経ち、順調に生育している
岩塚製菓と言えば、スーパーやコンビニに行けば製品をすぐに見つけられる、せんべいやおかきなどの米菓製造における大手企業だ。1947年(昭和22年)に新潟県の旧 越路町(2005年に長岡市に編入)で創業し、今でも同地に本社や主力工場を構えている。
その岩塚製菓が、なぜ資源循環N.CYCLEプロジェクトに参加しているのか。同社の常務取締役・マーケティング本部長の阿部雅栄さんは、それについて「従業員のため、地域のために、というのはうちの昔からのキーワード」だと話す。
長岡ではかつて、農閑期になると多くの働き手が都市部に出稼ぎに出ていた。家族と離れて暮らさなければならない、そんな地元の人々の姿を憂いて平石金次郎と槇計作が、地元に雇用の場を創出するために立ち上げた食品製造事業が岩塚製菓のルーツだ。したがって、地域への貢献を非常に重視する。
 2020年に竣工した「BEIKA Lab」は最新工場と同時に新製品開発の拠点(画像提供:岩塚製菓)
2020年に竣工した「BEIKA Lab」は最新工場と同時に新製品開発の拠点(画像提供:岩塚製菓)
地域を重視する岩塚製菓が、同じくらい重視しているのがフードロスの削減だ。岩塚製菓では米菓の原料にすべて国産米を使っている。製造過程で洗米水、いわば「米のとぎ汁」が生じるが、家庭でのそれとは異なり、量と濃度が莫大だ。
「洗米水は牛乳みたいな白色になるんです。米が水を吸いやすくするために、米同士がぶつかって表面に傷が付くように洗うのと、水をできるだけ使わないようにするので、どうしても高濃度になる」(阿部さん)
この洗米水は多くの米のカケラ、すなわち有機物を豊富に含んでいる。また、食品の製造工程で生じるもののため、味はともかく衛生面では人が飲むことができるほど。しかし、これまでは産業廃棄物として、お金をかけて処分するしかないという課題があった。
「やっぱり心が痛いんですよね。昔の人間なので、米粒ひとつ捨てたら目が潰れる、と言われて育った。だから、できることなら解決したい」(阿部さん)
そうした課題を抱えていた岩塚製菓は、地元企業のつながりから長岡技科大の小笠原代表と出会い、お互いの取り組みや課題を共有した。そのなかから生まれたのが、「ノンケミカル工場」というビジョンだ。洗米水からさまざまな成分を抽出し、それを元に肥料を作ったり、洗浄剤を作ったりする。肥料は田んぼに撒き米の栽培に活用し、洗浄剤は工場設備の清掃に使う。その洗米水の処理に、SIPによる微生物探索プラットフォームによって選別、育種された微生物が活用されることが期待される。
「洗米水に含まれる不純物を取り分けるとき通常は凝集剤という化学薬品を入れる。でも、それを入れた洗米水から作った堆肥は有機JASに認定されない。だから、不純物を凝集する微生物を探してきて、それで洗米水を処理する。そこから油脂を抽出すれば、洗浄剤も作れる」(小笠原代表)
収穫した米は米菓の材料となるし、洗米水由来の洗浄剤を使い化学合成由来の洗剤を止めれば、工場で使うもの、工場から出ていくもの、すべて合成化学物質を使わない「ノンケミカル工場」とすることができる。小笠原代表が示したこのビジョンに岩塚製菓も共鳴し、N.CYCLEプロジェクトへの参画を決めることとなった。
「最新鋭の工場では水の使用量を抑えるため洗米水が高濃度になってしまい、処理に悩んでいた。そこに、夢がある話をいただくことができた」(阿部さん)
「ノンケミカル工場こそ、うちが目指す方向だと思った」(阿部さん)
岩塚製菓が目指すノンケミカル工場の実現の成否は、微生物を利用した洗米水由来の肥料や洗浄剤に依るところが大きいが、現時点ではいずれもまだ取り組み始めたばかり。「私たちは、やると決めたらどんどん行きたい」と阿部さんも、N.CYCLEプロジェクトの進展に強く期待を寄せる。
 岩塚製菓 常務取締役・マーケティング本部長の阿部雅栄さん
岩塚製菓 常務取締役・マーケティング本部長の阿部雅栄さん
ホーネンアグリは、水稲向けや園芸用の培土を製造販売している農業資材メーカーだ。特に、稲の苗を育てるための苗床の土では、新潟県の水田面積のうち40%以上のシェアを持っている。日本有数の米どころにあっての縁の下の力持ちだ。また、リサイクル事業として、公園などの植栽の剪定枝葉や刈草、米を脱穀した後の籾殻、食品工場からでる廃棄物などを培養土の原料としている。
同社取締役社長の小林ひかりさんは「農家では苗半作と言う言葉があり、作物の出来のうちの苗の出来が半分、栽培が半分と言う意味です。そのくらい、苗作りは大切です」と教えてくれた。その苗作りに欠かせない苗床の土の作り手として、ホーネンアグリの農家への影響力は小さくない。
N.CYCLEプロジェクトの実現、そして岩塚製菓が目指すノンケミカルのポイントは、廃棄するはずだったものを資源として循環させ、リサイクルすること。その循環プロセスにおいて、廃棄物を堆肥にする重要な役割をホーネンアグリが担っている。具体的には、洗米水の処理で生じる有機物を微生物で発酵させ、堆肥とし、その堆肥を固形化したペレットにすることで、田んぼに撒きやすくする。
「弊社は岩塚製菓様をはじめ、長岡市内の事業者が排出したものを受け取って、リサイクルして堆肥を作っている。それをちゃんと地域の田んぼや畑に循環して、そこからおいしい作物ができ、食品の加工にも回せる、そんなサイクルができたらすごくいい。そこの裏方として、有機物を受け取って土に戻す、という役割を担わせていただいています」(小林さん)
通常、堆肥はバラバラの土のような状態であるため、田んぼに撒きづらいそうだ。そこで、ある程度の固形物のペレット状にすることで、取り扱いが容易になるという。また、昔は堆肥施用が行われていたが、手間がかかるため省略されるようになった。そうした理由もあり、近年、長岡市内で「田んぼの地力が落ちているのではないか」という声が聞かれるようになった。具体的には、単位面積当たりの収量が減少したり、夏場の高温障害を受けやすくなったりということがあるそうだ。そこで、堆肥による田の土の改善は、地元長岡の農家からも大きな期待が寄せられている。
 廃棄物を原料とした堆肥(左)と、それをペレット状に加工したもの(右)
廃棄物を原料とした堆肥(左)と、それをペレット状に加工したもの(右)
同社の敷地内にある試験田のほか、長岡市内の3つの生産者の協力を得て、35反(およそ3.5ヘクタール)の試験田にて、堆肥の効果を検証している。試験田は、この春(2022年5月)に初めての田植えをしたばかりで、取材した6月の時点ではまだ青々としていた。今後、新たな微生物の導入や、製造工程の最適化、また堆肥を撒く量や時期などの調整と検証を進める。
そして、検証をより正確に、科学的なプロセスで進めるために、本社内にラボ「培養土・微生物研究室」を設置し、培養土の成分分析や苗の生育の検証などに取り組んでいる。このラボの設備には、長岡市のバイオエコノミー推進事業補助金が活用されており、地元から大きな期待が寄せられていることがわかる。そして、ホーネンアグリ自身も、N.CYCLEプロジェクトへの参加の契機として地域への貢献を強く語る。
「N.CYCLEプロジェクトは、参加する皆さんが、地元のためにやっていきたいという思いが強い。私たちも、土作り環境作り健康作りでの社会貢献が会社の理念なので、共感してやらせてもらっています」
「農業はいま、肥料を始めとするあらゆる資材が値上がりしているのに、農産物の価格は上げられないので、すごく厳しい状況です。一方で、農業は食料供給だけでなく、地球環境にも貢献できる可能性がある。そうした状況だからこそ、本当に必要になる資材を研究開発して、農家に使っていただけるものを提案したい」(小林さん)
 ホーネンアグリ取締役社長の小林ひかりさん
ホーネンアグリ取締役社長の小林ひかりさん
今後、微生物探索プラットフォームによって選別された「より良い微生物」が加われば、ホーネンアグリの堆肥は「資源循環」に加えて、更なる付加価値がもたらされる。ただし、稲作は1年に1回のサイクルであり、その検証も1年単位で行わなければならないため、まだまだ先は長い。そうした長期の取組を継続し支えるためには、ステークホルダーを取りまとめていく役割が重要だ。N.CYCLEプロジェクトにおいてそれを担っているのが、ネオスという会社だ。
ネオスは、主に長岡の地元企業のWebサイトや広告などの企画・制作を行うデザイン会社。N.CYCLEプロジェクトにおいては、運営コーディネートの役割を担っており、同社の常務取締役・営業企画本部長の村上敦子さんは、その主な役回りを「進行コーディネートやスケジュール管理」というが、実質的にはそれ以上のまとめ役を担っている。
中心となる小笠原代表を始めとして、N.CYCLEプロジェクトに参画する企業は、本来それぞれ異なる仕事に取り組んでいる。岩塚製菓は米菓の製造販売、ホーネンアグリは堆肥の製造販売、長岡技術科学大学は教育と研究と、それぞれ本業は異なり、そのビジネスモデルや商流も大きく異なる。
 ネオスが制作した「N.CYCLEプロジェクト」のポスター。お米を軸にした長岡における資源循環を表現している(画像提供:ネオス)
ネオスが制作した「N.CYCLEプロジェクト」のポスター。お米を軸にした長岡における資源循環を表現している(画像提供:ネオス)
そうしたコメ産業に関わる組織が集まり、N.CYCLEプロジェクトは始動した。もちろん、資源循環というエコシステムの構築による地元への貢献という意識は共有しているが、本来的には強い利害関係があるわけではない。だからこそ、コーディネートが重要であり、デザイン会社であるネオスの強みが生かされているのだと村上さんは話す。
「今回のような取組を1枚の絵で見せなければいけないという時に、役割分担のイメージ図をデザインして、 プレゼンの中で理解しやすい形にすることが、私たちにできること」(村上さん)
ビジネスや営みの分野が異なれば、話す言葉も違ってくるのはよくある話。そうしたギャップを乗り越えるためにも、「共通理解」として一つの絵を共有することには大きな効果がある。そうした役割をデザイン会社が担うのは、適任と言える。
また、ネオスはWebサイトや広告の制作を通じて、多くの長岡の企業や組織とつながりがある。実際に岩塚製菓やJA越後ながおか、長岡市役所の商品デザインやWebデザインなどを行っており、その立場からコーディネートという役割を担うのは納得できる話だ。
「参加する企業はそれぞれ単独でバイオへの取り組みを思案していて、お互いの連携ができていなかった。そこで、以前から知り合いだった小笠原先生と一緒に地元企業にお話しをするなかで、資源循環の可能性を見出すことができた」(村上さん)
N.CYCLEプロジェクトへの参加企業は、それぞれ地元への貢献を意識し、またできるだけ環境負荷を下げるための施策を考えていた。だが、資源循環のサイクルは、新たなエコシステムの創出であり、ひとつの組織だけでは困難であることは、すぐにわかる。だからこそ、村上さんと小笠原代表の出会いから、プロジェクトがスピーディーにかつ密接な形で立ち上がったのだ。
 ネオス 常務取締役・営業企画本部長の村上敦子さん
ネオス 常務取締役・営業企画本部長の村上敦子さん
それと同時に、現時点で利害関係が薄い参加企業に対し、継続的にプロジェクト参加へのインセンティブを示し、実際にコミュニケーションとコミットメントを持続させるためには、コーディネーターの役回りが欠かせない。村上さん自身、以前は大手広告代理店に勤務しており、そうした複数のステークホルダーのなかで動き回りながら、プロジェクトを動かして行く経験に長けている。
「普段から地元企業とお仕事させていただいていて、そこで課題をうかがっているから、皆さんにとって、どういう形で進めればいいのかがなんとなく見えている」(村上さん)
だからこそ、その役回りは「スケジュール管理や進行」を超えたものになる。そして、プロジェクトへの参加企業とネオスに共通しているのは、やはり地元への貢献だ。そのなかでも「バイオ」がキーワードとなったのは、もちろんSIPバイオ農業に参画する長岡技術科学大学と小笠原代表の存在もあるが、もう一つ大きいのは、長岡市が内閣府による「バイオコミュニティ」の認定を受けている「バイオの街」である点だ。
では、なぜ長岡は「バイオの街」となったのだろうか。
2021年6月に、長岡市は内閣府から「バイオコミュニティ」に認定された。バイオコミュニティとは、政府が定めた「バイオ戦略」に基づくバイオ関連市場の拡大に向けた方策の一つとして、特色のあるバイオ分野の取り組みを展開する地域が認定されるもの。長岡のほかには、北海道、鶴岡、福岡が選ばれている。
その認定に先立つ2020年1月に、長岡では「長岡バイオエコノミー・シンポジウム」を開催した。シンポジウムには、予想以上の参加者が集まり、「驚いた」と同市商工部次長兼産業イノベーション課長の斉藤真紀さんは語る。
「自治体がこういう堅いイベントをやると普通はあまり人が集まらないんですけど、この時は会場に入りきれずにお断りするような状況でした。その後の酒蔵を会場とした懇親会も非常に盛り上がって、そこから市役所の雰囲気が変わりました」(斉藤さん)
 2020年1月17日に開催された長岡バイオエコノミー・シンポジウムの懇親会の様子(写真提供:長岡市)
2020年1月17日に開催された長岡バイオエコノミー・シンポジウムの懇親会の様子(写真提供:長岡市)
長岡市は国内有数の米の生産量を誇る米どころである。一方で古くから栄えた機械加工や鋳物業など基盤的技術に加え、電気・電子機械や液晶、半導体などの多様な業種がバランスよく集積するモノづくりの街でもある。長岡のモノづくりの特徴は、多品種少ロットのニーズにも対応できる高い技術力を持ち、ほとんどがB2Bであり、消費者が直接手に取るような最終製品を取り扱う企業はほとんどない。そうしたなかで、モノづくりの技術を活かしながら新たな産業の創出として、「バイオ×モノづくり」に取り組んでいくこととなった。長岡市役所が、研究開発の社会実装である「N.CYCLEプロジェクト」に関わるのも、そうした自治体としての産業振興という意味合いが強い。
だが、なぜそれが「バイオ」だったのだろうか。実は、長岡市内には新潟県内では最多、国内でも2番目となる17の酒蔵があるほか、醤油や味噌の醸造所も多く、特にそうした蔵が集まっている摂田屋地区を以前から「醸造のまち」と名づけ、10年以上前から観光名所の一つとしてアピールしてきた。
また、近年は食の分化や歴史とのなかからも「発酵」というキーワードが注目されていることもあり、「醸造のまち」と絡めて2019年に「HAKKO Trip」というイベントを開催したところ、非常に多くの参加者を集めた。当然ながら、醸造のもととなる発酵は微生物による現象であり、バイオ研究の出発点の一つでもある。
 長岡市ではバイオコミュニティの認定以前から醸造や発酵、そしてバイオについて取り組んでいた
長岡市ではバイオコミュニティの認定以前から醸造や発酵、そしてバイオについて取り組んでいた
そして、もう一つ大きな要因だったのが、長岡技術科学大学の存在だ。同大学と小笠原代表は、SIPバイオ農業「微生物探索スクリーニング」サブコンソチームの代表機関であり、研究機関や企業とバイオ研究に取り組んでいる。
「私たちが知らない間に、バイオに関連する研究者とか企業の方がたくさん来られていた」(斉藤さん)
長岡市に存在するプレイヤーと状況、そして歴史的な背景とが組み合わさったことで、バイオが重要なキーワードとなっていき、先のバイオエコノミー・シンポジウムの開催を契機に、明確な形になっていった。
「バイオエコノミーを取り込むことによって産業を活性化させ、長岡の自然の豊かさだとか、食のおいしさみたいなところが、長岡の魅力につながり市民をはじめ長岡を好きな人が増えるといいなと、バイオコミュニティについては思っています」(斉藤さん)
自然や農業が大きなポジションを占める長岡において、資源循環は重要なタームであり、その点について長岡には成功体験があった。それが、バイオガス発電だ。家庭からのゴミ収集時に、可燃ゴミと生ゴミとを分けて収集し、生ゴミを発酵させて生じるメタンガスを発電に利用するもの。2013年から開始したこの事業、市民にとってはゴミの分別の手間が増えるものの、市側が説明会を繰り返し実施するなど丁寧に進めた結果、2021年には225万kWhの発電量に達し、余剰分を電力会社に売却するなど、財政にも貢献している。
こうしたさまざまな積み重ねの結果が、長岡市の"バイオ推し"のバックグラウンドとなり、N.CYCLEプロジェクトへの支援へとつながっているのだ。では、N.CYCLEプロジェクトは、その社会実装としての役割をどのように具体化していくのか、小笠原代表にうかがった。
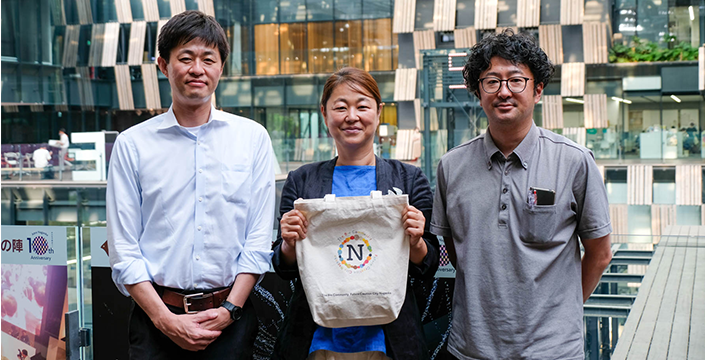 長岡市市商工部次長兼産業イノベーション課長の斉藤真紀さん(中央)と、同課バイオエコノミー担当係長の川上徹さん(右)、同課主査の佐藤春雄さん(左)
長岡市市商工部次長兼産業イノベーション課長の斉藤真紀さん(中央)と、同課バイオエコノミー担当係長の川上徹さん(右)、同課主査の佐藤春雄さん(左)
ここまで見てきた様に、SIPバイオ農業の「微生物探索スクリーニング」チームの社会実装は、新潟県長岡市における資源循環のエコサイクルを生み出すための「N.CYCLEプロジェクト」という形をとって進んでいる。
「長岡はコシヒカリが生まれた街。そこで未利用資源を活用するとなると、お米に関するものが最初に出てくる。そこで、岩塚製菓さんの洗米水を、ホーネンアグリさんが堆肥にして、それを使って農家がまたお米を作る」(小笠原代表)
そのN.CYCLEプロジェクトの鍵となる微生物の探索に、いま小笠原代表と長岡技科大は挑んでいる。
「微生物はいろんな種類がいます。油を作るもの、酵素を作るもの、有機物を凝集させるもの。そういうものを探してきて、今度は培養できるようにしないといけない。それをできるのが僕らのチーム」(小笠原代表)
微生物の探索とひとことに言っても、最初に述べたとおり、現在、人間が培養し利用できているのは、全体の0.02%とごくわずか。新たな取り組みにおいて、効果を発揮する微生物を探し出すためには、さまざまな環境からさまざまなサンプルを取り、そこから微生物を探し、培養し、検証するという、地道な作業が必要だ。微生物探索プラットフォームとは、そのプロセスを効率的に行う技術と試薬と装置、そしてノウハウの総体だ。
「まだ培養できていない新たな微生物を探すために、函館や沼津から深海魚を送ってもらっています。そうやって、探索するためのサンプルを手に入れるネットワークも大事です」(小笠原さん)
また、見つけた微生物をさらに有用なものとするための「育種」も行う必要がある。育種とは、分離し培養した微生物の変異株を見つけたり、より機能を高めるための操作を行ったりする営みだ。そうしたプロセスを経て、本当に産業において有効な微生物を得ることができるのだという。
「残念ながら日本企業は、そうした微生物の探索と育種にコストをかけられなくなってきている。なので、僕らはいろんな研究機関と一緒に、長岡にそういう拠点を作ろうと動いている。N.CYCLEプロジェクトはその先行事例でもある」(小笠原さん)
微生物の活用とは、長期的な取り組みの果てにたどり着くもので、腰を据えて取り組むべきもの。だからこそ、自治体や地元に根付いた企業と共に取り組んでいく必要がある。N.CYCLEプロジェクトへの取組はそのことも示している。
 「微生物探索はバイオにも農業にもすべての研究に貢献できる立ち位置、その意義は長岡にとっても大きい」、と話す小笠原先生
「微生物探索はバイオにも農業にもすべての研究に貢献できる立ち位置、その意義は長岡にとっても大きい」、と話す小笠原先生
一方で、そうして作り出した事例を、どうやって横に展開していくのか。それを成し遂げてこその社会実装となるはずだ。
「SIPに取り組んだことによって、いろんな参画機関とつながった。このネットワークこそが、次につながる体制になる。こうした拠点を作ることも成果になるはず」(小笠原代表)
「現在は、微生物の探索にいろんな企業と協力して取り組んでいるけど、これ以上増えてくると大変。かといって、単にマニュアル化しても、それだけでできることではない。だから、長岡に微生物について取り組む研究者や企業が集まれるようなところを作りたい」(小笠原代表)
「長岡を微生物の総本山にする」と小笠原代表は力強く言う。
研究だけをしていても拠点は作れない。SIPバイオ農業で生み出した微生物探索スクリーニングの研究成果を、長岡においてさまざまなメンバーと共に微生物探索のプラットフォームとして実際に活用し、地域に根ざした資源循環サイクルを作り出す。
さらに、そうやって生み出した事例を長岡に訪れる企業や研究者、学生と共有していくことで、日本や世界にも広げて行く。そのための「総本山」が、いま長岡に生まれようとしている。