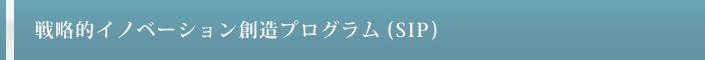第2期 スマートバイオ産業・農業基盤技術
第4回
合成生物学等を駆使した食素材・品種育成技術の開発
品種改良と生産性の向上で、世界の食料問題解決への貢献を

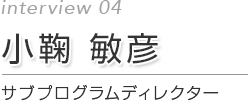
インタビューの第4回は、小鞠敏彦サブプログラムディレクターに、「合成生物学等を駆使した革新的な食素材・品種育成技術の開発」が取り組む課題について聞いた。
――「スマートフードシステム」の中で、小鞠サブプログラムディレクターがご担当の「合成生物学等を駆使した革新的な食素材・品種育成技術の開発」は、「開発」として位置付けられています。どのような役割を担うのでしょうか。
小鞠:スマートフードシステムの入り口として、食品のもとになる農業生産物を効率よく生産するための、いわゆる生産性向上が一番大きな役割になります。肥料、農薬、その他の農業資材といった、我々がインプットと呼んでいるものを減らしたり、より良いものにしたり、アウトプット、すなわち作物の収量を増やしたり品質を良くするということですね。例えば肥料をたくさん入れすぎても、作物は使い切れずに無駄になってしまいます。必要最低限の量を入れ、作物が使いこなす効率性を高めるという、2つの側面から、生産性の向上をはかっています。
――具体的にはどのような課題に取り組まれているのですか。
小鞠:課題のうち2つは、品種改良に関わることです。まず1つめは、「データ駆動型育種」。「育種」という、昔から人類が手掛けてきた技術を、データによってより効率化することです。これまでの育種でもデータにもとづく選抜も行われていますが、それよりは人の目で見て、良いものを選んでいくという要素が強かった。さらにデータの項目を増やし、よりデータに基づく選抜を行わなくては、これ以上の生産性の向上は見込めません。例えば、植物の遺伝子情報、育成時の土壌や気象条件などの環境要因、収穫物の品質や収量をデータ化して蓄積することで、どのようなインプットを入れれば、どういうアウトプットが出るかがわかるような世界を目指します。
従来の代表的な育種の手法としては、2つの品種を掛け合わせて、それぞれの良い特性を持つ品種を作り出すというものがあります。今回も果樹に関する課題がいくつか入っていますが、こうした多年生作物は「桃栗三年、柿八年」ということわざもあるように、種をまいてから何年もかけ、収穫しなくては成果が見えません。しかも、植えた木は実がなるまでに大きくなりますから、あるスペースに植えられる木の数にも限りがあります。何十万という組み合わせから選びたくても、現実に、1つの育種場で育てられるのは200本程度です。
そこで、データを活用して、苗のうちに遺伝子を調べることにより、「この遺伝子を持つならこういう性質があるはず」ということが、実がなるようになる前の段階でわかります。収穫を待たずとも、良い性質がありそうな苗を遺伝子で選別して、エリートだけを200本育てて調べれば、良いものを選びやすくなる。結果、全体として効率が上がることが期待できます。まだまだ入り口ですから、一足飛びには実現できませんが、データに基づく品種改良に少しでも近づいていくことが課題です。
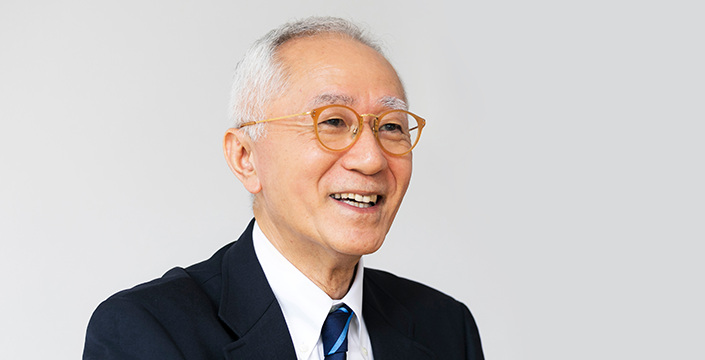
小鞠:もう一つは、ゲノム編集です。こちらは、どちらかといえば技術開発の側面が強い取り組みになります。遺伝子はDNAからできていますが、DNAというのはわずか4種類の塩基と呼ばれる物質の配列(並び方)で情報を表現しています。この塩基の並びが植物の性質にどのようなかかわりを持つかを理解して、塩基、すなわち情報ごとの単位のレベルで遺伝子を切ったり貼ったり、挿入したりという操作を行う、精密ゲノム編集技術の開発を目指しています。
ゲノム編集という言葉を5~6年前からよく聞くようになった背景には、CRISPR-Cas9という、DNAの塩基配列の特定の部分を見つけて切断する技術の登場があります。これは極めて優れた技術なのですが、これまでは切った箇所に偶然起きる変化を利用していました。つまり、CRISPR-Cas9で切った部分が、もとに戻る時に発生するランダムなエラーの中から、目的に都合のよいものを選ぶことで「編集できた」と言っていたのです。SIP「スマートバイオ産業・農業基盤技術」では、DNAをこれまでのCRISPR-Cas9が切断できなかった場所でも切断できるようにすること、そして切った場所を狙った通りの配列に改変できるようにすることで、精密ゲノム編集を可能にします。
5年間の成果として、メロン、トマト、花きなどのいくつかの品種で、より甘くなる、日持ちしやすくなる、より身体によい成分が増えるなど、2つ以上の性質を改良することを目指します。それぞれの性質に対応する遺伝子の塩基配列については既にデータがあるのですが、それらを遺伝子に組み込み、農作物に複数の特徴を新たに持たせるには、精密ゲノム編集技術がないと難しいのです。
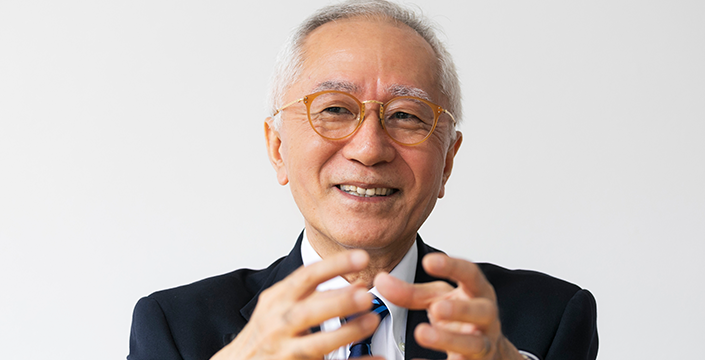
――データ駆動型育種とゲノム編集という2つの方法で、品種改良に取り組まれているということでした。品種改良以外にはどのような取り組みをされているのでしょうか。
小鞠:3番目の課題は、「農業環境エンジニアリング」と呼んでいます。何を行っているのかというと、土壌など作物を取り巻く環境を精密に測定することで、肥料、堆肥、土壌改良資材などのインプットと、アウトプットである作物の関係を明らかにしていきます。
農業は、その土地によって土の状況、環境、気象など、さまざまな条件が違いますから、同じように肥料や堆肥を入れても、ある時は効果があっても別の時には何の効果もないということがあります。そこで、入れた後、土の中でどうなっているか、特に、土の中にいる微生物や、その他の成分をきちんと測定することにより、作物の品質や収量との相関を明らかにしたいと考えているのです。
アウトプットの方も、もちろん調べます。今回は小松菜や大豆など、なじみの深い作物を使います。土に何をどのくらい入れたら、微生物や土がどうなったか、そしてどのくらい穫れたか、栄養はどうか、といったことを全部調べることで、何をどのような条件で入れればいいかがわかってきます。最終的には、肥料などを最小限にして、効率良くいいものがたくさん収穫できるようになる条件を見つけることができればいい、ということです。
――土の状態を調べるというのは、これまであまりされていなかったのでしょうか。
小鞠:肥料成分と土の関係、水分や有機物がどのくらいあるのかといったことはこれまでにも調べてはいますが、広い圃場の中で調べられるのはせいぜい1か所です。でも、圃場全体が一様なわけではない。農家の人はよく分かっていて、田んぼでも畑でも「この辺はよく獲れる場所」「この辺はちょっと良くない場所」といったことを知っていますが、それをデータでは押さえていないのです。
今回も無限に測定することはできませんが、測定技術や、測定データを処理する技術が向上しているので、今までよりも地点数を増やすことができます。しかも、今まで測らなかったものも測ります。担当者は、微生物叢、作物の遺伝子がどう働いているかというところまで徹底的に調べたいと言っています。
ある特定の微生物をある程度増やして入れると、微生物叢が変わって土壌が良くなるという、微生物資材もあります。ただ、生物がいる場所に生物を入れるというのはやはり水もので、効果がある時もない時もあるというので農家もあまり信用していなかった。今回徹底的に調べることで、信頼のおけるような使い方ができるのではないかと期待しています。
――豆類の根に菌が住んでいて、肥料を作っている、という話は聞いたことがあります。
小鞠:豆類は本当に極端なケースで、根粒菌という根にコブを作る菌がいるのですが、それが空気中の窒素を化学反応しやすい形に変えることで、肥料を作るんですね。これほど劇的ではなくても、さまざまな有用な微生物がいます。そうしたものを土に入れていくことで、作物が育ちやすくなったり、病気にかかりにくくなったり、といったことが期待できます。
土壌の改良には、これまで捨てられてしまっていたようなものも利用します。例えば、日本酒を醸造する時にできる酒粕は、今は一部産業廃棄物として捨てられてしまっています。これも、上手く農業の現場に持ち込むことで、土の状態がよくなり微生物も活躍しやすくなるのだそうです。使われずに捨てられてしまっていたようなものをリサイクルすることで、資源循環にも貢献していくテーマにもなっています。

――土の中の微生物を調べるのはやはり土を取って培養して、という手順になるのでしょうか。とても大変そうです。
小鞠:土の中にいる微生物の中で、実験室で培養できるものはほんの一握りで、大半は培養できない。ということは従来の手法では調べようがないんですね。ではどうするかというと、微生物だって生物なんだからDNAを持っているはずだということで、採取した土からとにかくDNAを全部抽出して、その配列を次世代シーケンサーで徹底的に調べることで、そこに何の生物がいるのか読み取る、メタゲノム解析という手法で調べようとしています。
ここ20年から30年で、DNAを調べる技術は大きく進化しました。DNAの配列を素早く調べられるようになったし、それがコンピューターの発展とすごく相性がいいので、バイオインフォマティクスという研究分野もできて、発展してきています。
一方で、実際の作物のデータを取るのは、いまでも大変なんです。圃場で果樹を育てるにも、何年もかけて1つの圃場で200本しか育てられない。さらに、膨大な過去の研究知見は全部紙の印刷物で保存されているので、それらは利用できるデータになっていないんです。
また、過去のデータをデジタル化することも必要ですが、少なくともこれからとるデータはデジタルにしようと。すると、次に来る問題が、今、作物のデータの測り方には、方言みたいなものがあることです。たとえば、「イネの穂がいつ出たか」についても、その地方の試験場によって異なる基準がある。その上、記録の取り方も、人によって流儀がありますから、それを全部統一しないとデータとして集積できない。データ駆動型育種のために、そうした方言の「統一」をはかることも、今回の研究の重要なテーマです。
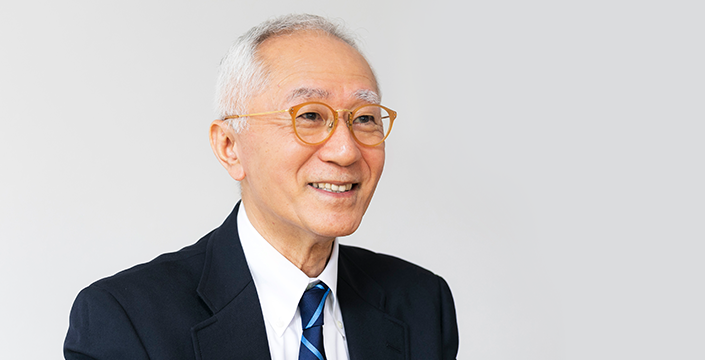
――多岐にわたるテーマに取り組まれていますが、SIP第2期終了後の出口戦略はどのようにお考えでしょうか。
小鞠:データ駆動型育種にしてもゲノム編集にしても、新しい方法を確立できたとして、それが実際の品種改良につながるのは、今の時点では何年後と言えないぐらい先の話になります。実際に種をまいて育てるまでの時間はどうしたって短縮できないので、これはどうしようもない。なので、どの課題も、入り口を工夫する課題と、出口に近い課題をセットにしています。
出口に近い課題というのは、既にこれまでの実績である程度先が見通せているものを新品種として世に出していくことです。データ駆動型育種では、リンゴの褐変(リンゴを切って放置すると短時間で茶色く変わる現象)をおさえた品種改良、ゲノム編集では、甘いメロン、栄養成分の多いトマト、花きは日持ちするとか、色が新しいとか、そういった新しい特徴を持つ品種を新品種として出していきます。
農業環境エンジニアリングは、もっと短時間で成果を出すことができる分野ですので、新しい農業資材やその使い方など、早期の事業化を期待しています。
入口の方というのは、技術として立派なものを作り、将来の技術開発につなげていく。あとは特許を取得して、知財をきちんと確保していくことです。
――基礎的な技術は、どの段階をもって完成とするのか、何か基準のようなものがあるのでしょうか。
小鞠:難しいですね。特許を取れたか、という問われ方が一番わかりやすいですが、あとは実用的なプロジェクトに組み込むことができたかどうか、ということですね。CRISPR-Cas9は医薬分野の利用が先行していますが、ありとあらゆる分野で期待されるようなすごい技術になりました。我々の考えている精密ゲノム編集が完成すれば、農業分野で世界をリードする技術になると期待しています。
――最後に、小鞠先生ご自身のSIP「スマートバイオ産業・農業基盤技術」への期待や、抱負をお聞かせください。
小鞠:データ駆動型育種、精密ゲノム編集、農業環境エンジニアリング、それぞれ目指しているものができたら本当にいいなと思います。私自身は日本たばこという会社に入社して最初に担当したのがタバコの品種改良、その後イネ、トウモロコシと、ずっと品種改良に携わってきましたので、特に育種には思い入れがあります。
今は、データ駆動型育種と精密ゲノム編集という2つのプロジェクトに分かれていますが、究極の目的は同じで、塩基配列レベルで育種したいということなんです。なので、この2つが対となって、理想の品種改良ができるように進むよう、期待しています。
農業環境エンジニアリングは、しかるべきところにしかるべき量の生産資材をインプットして効果を発揮させることで生産効率を高めるという、まさに農業としてあるべき姿ですよね。今、日本の米の生産量って、ピーク時の半分ぐらいしかないんですが、それは農業に関わる者として悲しいことです。その大きな理由は、日本で作ると生産コストが高いからなんです。農業生産性向上の技術が本当にうまく機能すれば、日本でも諸外国と対抗できるぐらいの効率で生産できるのではないでしょうか。
実際、マクロで見ると、食料は不足すると言われているのですから、日本だって少しでも農業生産性を向上して、国内消費できない米は輸出すればいい。日本の農業の発展が、世界の食料問題の解決につながることを願っています。


小鞠敏彦(こまり・としひこ)
日本たばこ産業株式会社経営企画部・サイエンスアドバイザー。
同社・植物イノベーションセンター所長、経営企画部部長、フェローを経て、現職。バイオテクノロジーによる品種改良の技術開発と事業化に長く携わる。アグロバクテリウムによる穀類への遺伝子導入法の研究は、日本育種学会賞、農林水産大臣賞などを受賞。現在、(公社)農林水産・食品産業技術振興協会副会長、日本植物細胞分子生物学会の産学官連携担当理事を務める。