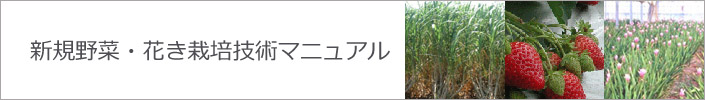沖縄県、鹿児島県にまたがる南西諸島でもっとも重要な作物はサトウキビである。サトウキビ生産拡大のため、圃場の集積、機械化、法人化などを通して大規模・低コスト生産システムの確立が急務とされている。しかし、サトウキビの大規模化を進めるには、一方で、さとうきびに圃場を提供しながら、サトウキビ生産に見合う収益をあげる農家群がなければこのシステムは成り立たない。このようなシステムを妨げる問題点の一つは気象的制約で、野菜などを作るのに適しているのは冬期を中心とした僅かな期間である。もう一つの問題は土地の利用についての慣行が他県とはかなり異なっており、容易には貸借関係が成立しないことである。
このような中で新たなシステムへの接近を図るには南西諸島で可能な高収益作目の生産技術を確立することが第一に必要である。我々は本プロジェクトを基本技術の開発から着手せざるを得なかった。それも5カ年という短期間に農家が自ら実施し、収益をあげることができる営農技術として確立することを目標とした。
対象とした主な作目は野菜と花きである。畜産や果樹は短期間での成果は難しく、さらに、成果が農家に普及するには相当の長期間を必要とする。もっとも注目したのはイチゴである。イチゴは現在、他県産が沖縄の店頭に並ぶ。鮮度は落ちているし価格は高い。従って、イチゴが島内で生産できれば相当のインパクトがある。加えて温度管理などは他の作目生産にも適用可能な技術となりうる。種なしスイカは他で試みたことのない新技術として、国内初の産地形成を目指した。施設利用作目ばかりでなく、サトウキビとの輪作を考慮してバレイショの新作付け体系の開発も目標とした。
花ではカーネーションに挑戦した。母の日需要はかつてほどではないが、春先の生花として根強い人気がある。これも温度管理の難しいことが予想された。他に、市場性などを考慮してユーチャリス、シンテッポウユリを加えた。高収益を目標に厳密な生産管理をしようとすると、植物としての特性が次々、問題となって立ち現れ、基礎的な生理学・生態学的研究がいかに重要かということを思い知らされた。
いずれもの作目も沖縄に適した土壌管理、病害虫防除等の共通的な基盤技術を必要としており、また、背景にある農地貸借など沖縄独特の慣行も調査する必要があった。これらは我々にとってははじめての経験であったが、多くの場面で沖縄県農試との協力が功を奏した。また県農試は鹿児島県農試と別の作目を対象に「地域基幹研究」を実施しており、このウェブサイトにはその成果も取り入れさせていただいた。
最終年度に当たり、現在までに得られた成果を「マニュアル」という形でとりまとめた。
年度途中の取りまとめであるため、最終報告ではないが、お世話になった皆様へのお礼の気持ちを込め、試してみようとする農家への最低限の情報を盛り込んだつもりである。このこのウェブサイトをご覧いただき、亜熱帯での新しい高収益農業に挑戦しようとする生産者が一人でも多く現れることを願っている。
九州沖縄農業研究センター作物機能開発部長