沖村誠
ア. 研究目的
亜熱帯に位置する沖縄県では、冬季温暖な気候を有効利用した野菜、花き類等による高収益集約作物の栽培技術の導入・定着が強く求められている。本課題では、沖縄の冬季に導入可能なイチゴの短期栽培技術を開発するため、雨除けハウス等の簡易施設を利用した冬季収穫による県内自給向け短期作型を目標に、これに適する品種を選定し、その苗生産技術を確立する。
イ. 研究方法
1.生態的特性の異なる品種の特性解明と適品種の選定
沖縄におけるイチゴの冬季短期栽培に適する品種特性を明らかにするため、生態特性の異なる品種及び久留米育成系統の1~3月どり作型適応性を検討した。
1998~1999年の2カ年は、促成用品種(とよのか、さちのか、女峰、とちおとめ、章姫、久留米58号)、半促成用品種(越後姫、きたえくぼ)、中間型品種(Pajaro,北の輝)、四季成り性品種(サマーベリー)及び外国品種(Florida belle)の12品種を、8月下旬に10.5cmポリポットに採苗し、11月上旬に沖縄農試園芸支場の雨よけハウスに畦幅120cm,株間25cmの2条植えで定植した。定植前の花芽分化促進のための暗黒低温処理(摂氏12度・15日間)効果及び深休眠性品種の冷蔵処理(定植前摂氏5度・25日間)による休眠打破効果についても検討した。
2000~2002年の3カ年は、久留米育成の促成用系統(2000年8系統、2001年9系統、2002年11系統)を用いて、9月上旬採苗、10月下旬~11月上旬定植の12~3月どり栽培により優良系統の選抜を行った。
基肥は5カ年ともN,P2O5,K2Oを各1.0kg/aとし、追肥は適宜行った。調査は生育、開花、収量及び果実品質について行った。
なお、イチゴ苗を沖縄に導入する際はミカンキイロアザミウマ防除のため臭化メチル薫蒸処理を行った。
2.生態的特性の異なる品種のランナー発生解明
沖縄の自然環境条件下における多様な生態特性を有する品種のランナー発生生態を明らかにするため、図2に示す11品種を供試し、1月末まで九州沖縄農業研究センター野菜花き研究部(久留米)の無加温ガラス室で育苗した苗(低温遭遇区)と沖縄農試園芸支場の雨よけハウスで育苗した苗(低温非遭遇区)を、2月1日に長さ60cm,容積10Lのプランターに3株ずつ計9株定植し、沖縄農試園芸支場の雨よけハウスで栽培し、ランナー発生数と採苗可能な子苗数を6月下旬まで調査した。
3.‘さちのか’の効率的苗生産技術の確立
1998~1999年の2カ年にわたる試験結果より、沖縄に適する品種として選定された‘さちのか’の効率的な苗生産技術を確立するため、一次ランナー苗を二次親株として用いる二段階採苗法の有効性を検討した。
8月中旬に沖縄農試園芸支場における栽培試験供試株から採苗し、翌年2月に定植した親株から発生した一次ランナー苗(子苗)を二次親株として用いた。処理区として子苗を5月15日、6月1日及び6月15日に定植した区及び慣行の親株定植区を設けた。子苗は定植2週間前に10.5cmポットに採苗し、プランターに定植し、雨よけハウスで栽培した。一次ランナーの発生数と子苗数を8月中旬まで調査した。
ウ. 結果
1.生態的特性の異なる品種の特性解明と適品種の選定
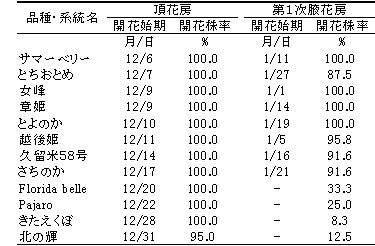
表1 沖縄の自然条件下における自然開花期
沖縄の自然条件下での頂花房の開花は、四季成り性品種‘サマーベリー’が最も早く、以下促成用品種の‘とちおとめ’、‘女峰’、‘章姫’、‘とよのか’、‘さちのか’等で、深休眠性の中間型品種‘Pajaro’、‘北の輝’や寒冷地型品種‘きたえくぼ’は‘とよのか’に比べて12~20日程度遅かった。また第1次腋花房の開花は、四季成り性品種や促成用品種では頂花房の開花後35日前後に安定してみられたが、中間型品種や寒冷地型品種では60日後の2月末でも半数以上の株でみられなかった(表1)。
収穫初期の1月下旬の生育は、促成用品種と四季成り性品種は無処理区と暗黒低温処理区とも順調であったが、中間型品種と寒冷地型品種はいずれの区でも葉面積や葉柄の伸張が小さく矮化様相を示した(表2)。収穫開始は、いずれの品種も無処理区が暗黒低温処理区より5日前後早く、無処理区では‘サマーベリー’の1月4日が最も早く、以下‘章姫’1月6日、‘とよのか’1月9日、‘さちのか’1月14日で、他の品種は1月20日~28日と遅かった。
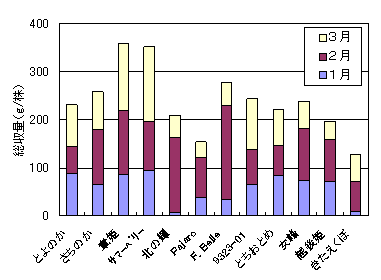
図1 月別収量(無処理区)
3月末までの総収量は、いずれの品種も無処理区が暗黒低温処理区より高く、無処理区では‘章姫’、‘サマーベリー’、‘Florida belle’、‘さちのか’が高かった。1月の収量は‘サマーベリー’、‘とよのか’、‘章姫’、2月の収量は‘Florida belle’、‘北の輝’が高かった(図1)。果実品質の優れる品種として、硬くて高糖度の‘さちのか’、‘北の輝’、大果で硬い‘Pajaro’、高糖度の‘章姫’、‘とよのか’が挙げられた(表2)。優良系統の選抜試験では、極早生で多収の‘9601-05’、‘9819-05’、早生で高硬度の‘0067-11’等が沖縄冬季の短期どり作型での適性 が認められたが、いずれの系統も‘さちのか’に比べて、果実品質はやや劣った(表3)。‘さつまおとめ’は大果で硬度が高く日持ち性に優れていたが、晩生 でランナー発生数が少なく増殖が問題であった。
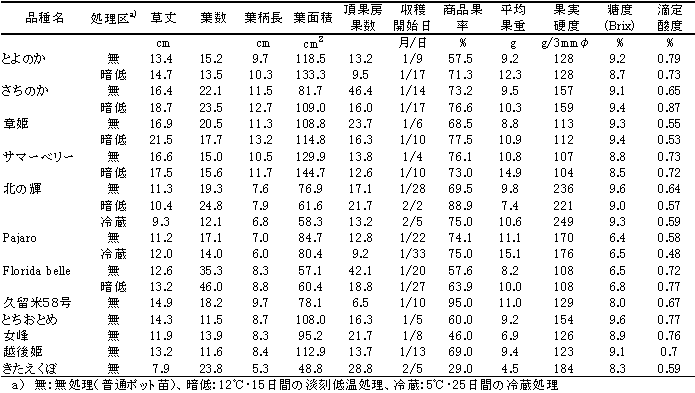
表2 沖縄での1~3月どり栽培における生育及び果実品質
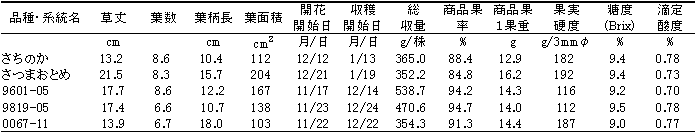
表3 久留米育成系統の生育・開花・収量・果実品質
2.生態的特性の異なる品種のランナー発生解明
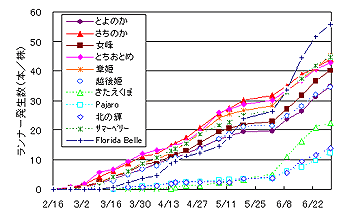
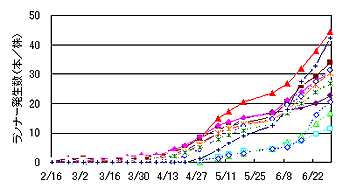
図2 ランナー発生数の推移
(上:低温遭遇区、下:低温非遭遇区)
ランナー発生は低温遭遇区では促成用5品種は2月中旬、また‘サマーベリー’、‘越後姫’は3月初旬からみられ、5月下旬には20~30本/株の1次ランナーが確認された。‘Florida belle’はランナー発生開始が3月中旬と遅かったが、5月下旬には20本/株以上に達した。‘Pajaro’、‘北の輝’、‘きたえくぼ’ではランナー発生開始が3月中旬~4月中旬と遅く、5月下旬のランナー数は3本/株程度と少なかったが、6月下旬には10~20本/株に達した(図2上)。なお‘きたえくぼ’、‘北の輝’では、3月下旬から1ヶ月の追加的な冷蔵処理(摂氏5度)によりランナー発生が促進された。低温非遭遇区では、促成用5品種及び‘サマーベリー’、‘越後姫’は2月上旬にランナー発生が始まったが、初期発生数が極めて少なく、株間差が大きかった。しかし4月中旬頃から発生数が増加し、5月下旬には15~20本/株となった。‘Florida belle’では4月下旬からランナー発生がみられ、5月下旬には10本/株程度に達した。‘北の輝’、‘きたえくぼ’、‘Pajaro’では発生開始が4月中旬~5月上旬と遅れ、5月下旬のランナー数は株当り2~4本と少なかったが、6月下旬には10~20本/株に達した(図2下)。
採苗可能な子苗数は低温遭遇区では‘Florida belle’、‘とよのか’、‘さちのか’、‘女峰’、‘越後姫’、‘きたえくぼ’で7月中旬までに100本/5株程度以上採苗できたが、その他の品種の採苗数はやや少なかった。低温非遭遇区でもほとんどの品種で同様の傾向がみられたが、‘北の輝’は7月中旬までの採苗数が30本/株程度と特に少なかった。(データ省略)
3.‘さちのか’の効率的苗生産技術の確立
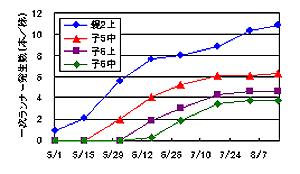
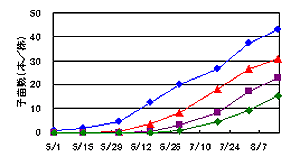
図3 さちのかのランナー
発生数(上)と子苗数(下)の推移
親株定植区におけるランナー発生は、5月初旬以降は急増し、7月中旬には株当り10本程度となった。子苗を二次親株として定植した区では、いずれも定植直後からランナーが発生し、7月中旬の株当り発生数は5月15日定植区で6本、6月1日定植区で4本、6月15日定植区で3本程度であった。7月中旬以降はいずれの区でも一次ランナーの発生はほとんどみられなかった(図3
上)。親株定植区における子苗数は、5月中旬以降は多くなり、5月中旬で株当り5本、6月上旬で10本、6月中旬で15本程度であった。また、子苗定植区における8月中旬の株当り子苗数は、5月15日定植区が30本、6月1日定植区が23本、6月15日定植区が15本であった(図3下)。
エ. 考察
1.生態的特性の異なる品種の特性解明と適品種の選定

写真1 さちのかの着果状況
沖縄の冬季において、促成用品種や四季成り性品種は順調な生育・開花を示したが、深休眠性の中間型品種や寒冷地型品種は生育が緩慢で開花が遅れ、株が矮化した。収量性では連続的的に果房が出蕾する四季成り性品種‘サマーベリー’と促成用品種‘章姫’が優れていたが、両品種は果実硬度は低く日持ち性が劣ることから沖縄冬季の栽培には不適と判断された。中間型品種や寒冷地型品種は、深休眠性のため夏期短日条件の沖縄では早い時期から休眠に導入し、花芽分化後の発育が緩やかとなり開花が遅れ、株が矮化して低収となった。また冷蔵処理による休眠打破効果が小さかったことから、亜熱帯沖縄の冬季の作型には実用性が低いと判断された。沖縄における冬季短期栽培で収量を上げるためには、腋果房を連続的に分化するタイプ、及び頂果房(+第1次腋果房)で多収を上げるタイプが想定される。収量性からみると、前者では‘女峰’、‘章姫’、‘サマーベリー’等、後者では‘Pajaro’、‘Florida belle’等が有望と考えられるが、果実品質面を考慮すると‘さちのか’が最も適するものと判断された(写真1)。
亜熱帯沖縄におけるイチゴの冬季短期どり作型には、生態的特性として早生性、浅休眠性、強草勢、果実特性として良食味性、良日持ち性、大果性を有する品種が適しており、供試した12品種の中では促成用品種の‘さちのか’が最も適すると判断したが、‘さちのか’では早生性と収量性がやや問題であることから、2000~2002年の3カ年にわたり、‘さちのか’に代わる有望品種・系統の選抜試験を行った。その結果、沖縄冬季の高温条件下での栽培では、果実の硬度や糖度等の果実品質が優れる‘さつまおとめ’と極早生で多収の‘9601-05’及び‘9819-05’の適応性が認められたが、収量面と果実品質面から総合的に判断して、いずれの系統も沖縄冬季の栽培では‘さちのか’より劣ると考えられた。今後は亜熱帯沖縄に適した優良品種の育成が必要である。
2.生態的特性の異なる品種のランナー発生生態解明
沖縄の自然条件下では、浅休眠性の促成用品種等でもランナー発生開始が遅れて発生本数が少なかったが、これは沖縄の冬季の自然条件下では休眠打破に必要な低温量が必ずしも十分でないためと考えられる。このため、寒冷地型の深休眠性品種では、早期に苗を確保するためには低温処理による休眠打破処理が必要である。
3.‘さちのか’の効率的苗生産技術の確立
‘さちのか’は沖縄の自然条件下では低温処理により休眠打破しなくてもランナー発生数が多く、かつ苗の仕上がりが早く育苗期間が短くてよい1)ことから、本品種の効率的な苗生産方法として子苗を二次親株に用いる二段階採苗法が有効であった。‘さちのか’の冬季短期栽培において、採苗適期の8月中旬1)までに本圃定植に必要な子苗10,000株/10aを確保するには、親株40株を2月にプランターに定植し、5月下旬から6月中旬に発生する子苗400株(40株×10)を採苗・定植すればよいことが明らかとなった。この二段階採苗法は、冬期間は少ない親株数で管理できるため省力的であり、健全な苗を効率的に生産するのに極めて有用である。
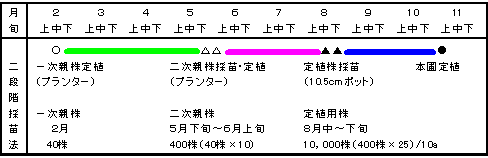
図4 沖縄における‘さちのか’の育苗体系
オ. 今後の課題
‘さちのか’は食味と日持ち性に優れるものの、早生性と収量性がやや劣ることから、‘さちのか’に代わる早生、大果で多収品種の育成が必要である。
また、沖縄県におけるイチゴ栽培技術は、品種‘さちのか’を用いて、苗生産から花芽分化処理、定植時期、病害虫防除を含めた栽培管理までほぼ確立したが、本技術の定着・普及に当たっては、熟練した指導者による綿密な技術指導と指導者の養成が不可欠である。今後、技術指導者の先進地域での研修など、指導者養成のための支援が必要である。
カ. 要約
沖縄の冬季に導入可能なイチゴの短期栽培技術を開発するため、生態的特性の異なる品種・系統の1~3月どり作型適応性を明らかにし、適品種を選定するとともに効率的な苗生産技術を確立した。
- 沖縄の冬季において、促成用品種や四季成り性品種は順調な生育・開花を示すが、深休眠性の中間型品種や寒冷地型品種は生育が緩慢で開花が遅れ、株が矮化し、また冷蔵処理による休眠打破効果も小さかった。
- 沖縄の自然条件下では、浅休眠性の促成用品種等でもランナー発生開始が遅れて発生本数が少なかった。寒冷地型の深休眠性品種では、早期に苗を確保するためには低温処理による休眠打破処理が必要である。
- 冬季短期栽培で収量を上げるためには、腋花房を連続的に分化するタイプ(章姫、サマーベリー等)、及び頂果房(+第1腋果房)で多収を上げるタイプ(Florida belle等)が有望と考えられるが、早生性と浅休眠性を有し、果実が硬く日持ち性に優れ、食味が良い促成用品種‘さちのか’が最も適すると判断された。
- 沖縄における‘さちのか’苗の効率的な生産方法として、一次ランナー苗を二次親株に用いて冬期間は少ない親株数で管理できる二段階採苗法が有効であった。親株を2月に定植(40株)し、5月下旬から6月上旬に発生する子苗(40株×10=400株)を採苗・定植することで、採苗適期の8月中旬には本圃定植用の子苗数(400株×25=10,000株/10a)を確保できた。
キ. 文献
- 中島規子・宮城信一・高市益行・久場峯子・荒木陽一:沖縄における採苗時期の違いと株冷処理の有無がイチゴの花芽分化・生育および収量に及ぼす影響。園学雑69(別2)、341,2000
