須藤憲一・今村仁
ア. 研究目的
花き生産による高収益化を目指して、カーネーション、シンテッポウユリ、ユーチャリスの沖縄県の気候に対する生育開花反応を解析し、新たな生産技術を開発する。カーネーションでは、集中開花技術(今村ら1997)を援用して、需要の高まる3月から「母の日」までに採花する技術の開発を目標とする。種苗コストが低いシンテッポウユリの実生苗の利用による生産体系は初夏から秋期が主であり、近年年末に向けた抑制生産技術の開発が行われ初められているにすぎない(鷹見ら2002)。この試験は沖縄県の冬期の温暖さを利用した春期採花作型を開発する。沖縄県で多量に栽培されているものの、結婚式に向けた需要期の安定採花が困難であるユーチャリスについては初夏および秋期に採花する技術の開発を行う。
イ. 研究方法
1. カーネション
沖縄県農試園芸支場において、つぼみの出現日や開花日に及ぼす温度の影響、定植時期や栽植密度ならびに電照が収量・品質に及ぼす影響を品種比較を含めて検討した。沖縄県宜野座村の現地実証試験では、秋に定植する作型で栽培を行った。また、久留米においては、温度が開花の早さに及ぼす影響、ごく早期の整枝の影響、節間伸長と品種の早晩性の関係、品種の夏越し後の生存状況、整枝を判断するための生育指標等を調査するとともに、沖縄の温度環境を模した温暖な条件で苗に対する低温処理の効果を検討した。
2. シンテッポウユリ
極早生種の‘さきがけ雷山’、早生種の‘雷山1号’、中性種の‘雷山2号’、晩生種の‘雷山3号’、同F1品種の‘オーガスタ’を主に供試した。福岡県久留米市において人工気象室、温室内で好適播種環境、苗の低温処理効果、花芽分化や開花に及ぼす温度、日長、苗齢、品種の早晩性の影響等について検討を行うとともに、沖縄県宜野座村で、ビニルハウス内と露地で栽培試験を行い、定植時期や電照が生育開花に及ぼす影響を調査した。
3. ユーチャリス
主に沖縄県宜野座村の現地試験地において、1mm黒防風ネットハウスの中にピアレス遮熱フィルム(透過率35%)と複層フィルムサニーコートで被覆した高さ2mの簡易施設を作成し、4m2に1台設置したエアコン(消費電力800w)による冷暖房で促成、あるいは抑制試験を行った。21cm鉢に3球、あるい60cmプランターに10球球根を植え付け、各球根当たり2~3枚の展開葉を持つ株を入室して処理を行った。高温処理時には遮熱フィルムは外した。別に遮光ハウス内地床で5年程度栽培していた株の上からサニーコート2枚を被せて高さ60cmのトンネルを作り、5m2の面積を窓用エアコン(消費電力790w)で低温処理を行った。
ウ. 結果
1. カーネション
a. 定植法
沖縄での定植適期は10月であった(表1)。7月定植では枯死株が多発する場合があり、11月定植では収量が少なくなった。株間×条間は10cm×20cmまたは20cm×20cmで優れた。最終摘心時期は11月下旬が適していた。
b. 生育開花反応
沖縄では発らいから約30~36日で開花し、発らいから開花までの日数の季節的変化は小さかった(図1)。発らいから開花までの期間は、昼温摂氏24~26度、夜温摂氏10~12度を境界域として、それより高温で促進され、低温では抑制されていた(図2、図3)。
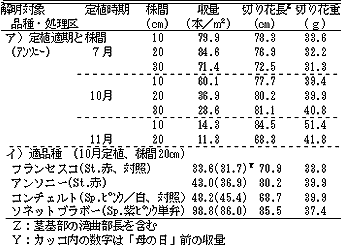
表1 定植時期と採植密度が切り花品質
および収量に及ぼす影響(沖縄抜粋)
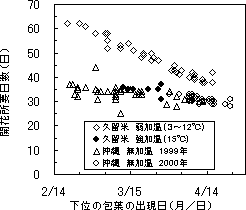
図1 発蕾日と開花所要日数の関係
(’フランセスコ’)

図2 夜間の温度域別遭遇時間
と開花所用日数(久留米における栽培)
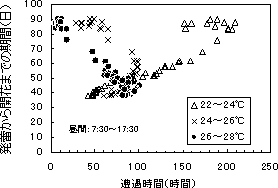
図3 昼間の温度域別遭遇時間と
開花所用日数(久留米における栽培)
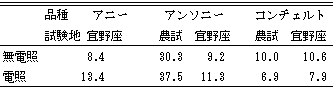
表2 電照が収量に及ぼす影響(本/株)
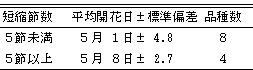
表3 品種の短縮節数と早晩性の関係
c. 品種生態
電照により、‘アニー’、‘アンソニー’では伸長する茎数が増加し開花時期も前進化したため収量が多くなった(表2)。しかし、‘コンチェルト’では収量が低下した。開花時期や収量には大きな品種間差があり、沖縄に適する品種が複数見いだされた(表1)。スタンダード系では‘アンソニー’、‘モータルデ’、‘アルテア’、スプレー系では‘ソネットブラボー’、‘エチュード’が優れた。久留米で従来の整枝開始より3ヶ月以上早い12月からの整枝を行うと、収量や品質はむしろ低下した。苗を暗黒条件で低温処理しても開花は促進されなかった。越年株を夏に極度の高温条件(昼:摂氏35~40度、夜:摂氏28度)で3ヶ月間処理した後も、95%(21/22株)の個体が生存した。秋に発生した枝の、節間の短い節の数(短縮節数)が少ない品種は開花が早い傾向がみられた(表3)。
d. 現地実証試験
初年度は収量が低く開花期も遅れ、「母の日」までの収量は14.9本/m2だったが、品種を変更したところ改善し、「母の日」までの収量は54.1本/m2となった。しかし、母の日前2週間の採花は全体の16%と少なかった。
2. シンテッポウユリ
a. 発芽環境
好適発芽環境を調査した結果、摂氏20/15度(昼/夜温)で高い発芽率を示した。久留米では3~4月の播種で問題が無かったが、沖縄では3月播種が70%,4月播種では20%台に低下した。
b. 花芽分化要因
8葉前後に育苗した苗を摂氏5度で1~2ヶ月間暗黒下で低温処理を行ったが、定植後の抽台は促進されたものの摂氏15度加温、無電照栽培では花芽分化は促進されず、6月以降に草丈3m,葉数250枚程度で開花した。開花に及ぼす温度と日長の影響を検討した結果、摂氏20度加温で早く、少葉数で開花し、高温が花芽分化を促進した。また長日処理によりそれぞれの温度条件で少葉数で開花した。早生品種ほど低温環境下での開花が早かった(図4)。
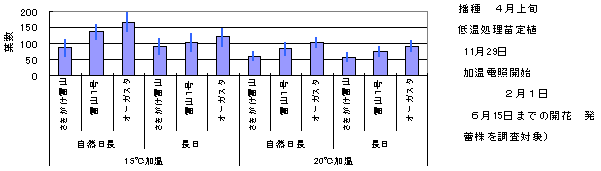
図4 加温温度・長日処理が花芽分化までの葉数に及ぼす影響
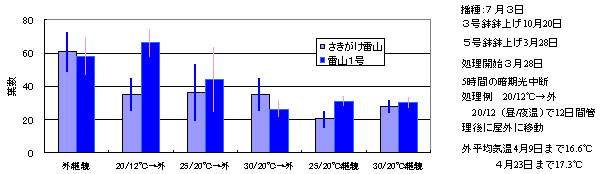
図5 長日下での12日間の遭遇温度が花芽分化までの葉数に及ぼす影響
c. 花芽分化に要する高温の程度の影響
長日下で、極早生種の‘さきがけ雷山’は摂氏20/12度(昼/夜温)に12日間遭遇すると花芽分化を開始したが、早生種の‘雷山1号’は、同条件では起こらなかった。摂氏25/20度の高温条件では12日間の遭遇で花芽を分化し、摂氏30/25度条件ではより早くなった(図5)。
d. 高温付与と長日処理による開花期の前進
長日条件で1月6日から3週間最低気温摂氏20度で栽培した結果、4月上旬から晩生品種を含めて開花した(図6)。なお、個体が小さいと花芽分化が遅れ、葉数20枚程度の節間伸長を開始した時期からの処理が適切と判断された。2002年度の試験では12月上旬より高温処理を行った結果、早生種の‘雷山1号’や‘オーガスタ’は3月彼岸時の開花が可能になったが、高温処理開始時期を前進したほどの効果は得られなかった。
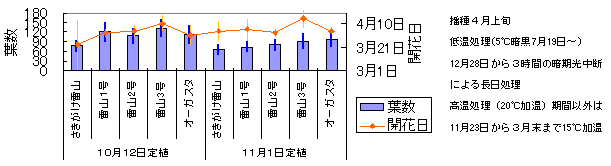
図6 1月6日~2月1日間の高温処理が生育開花に及ぼす影響
e. 沖縄県における現地試験結果
2000年の試験では10月18日に定植した場合、早生性が強い株は1月ごろから草丈40~50cm,1輪程度の極小茎で開花した。4月上旬までに2%の株が開花し、1/3が発蕾した。早期に開花した個体からは2次枝が株元から数本萌芽し、5月以降に1mを越える草丈で開花した。2001年度は早期開花を避けるために11月13日に定植時期を遅らせたが、多くの株が極大化し、5月以降に開花した。電照区では、2月から開花が始まり、その中で、晩生種の‘オーガスタ’は4~5輪の花数で草丈1.5m程度の良品が彼岸前に採花できた(図7)。早期に開花する早生品種ほど、短茎、少輪あるいはブラインドになった。
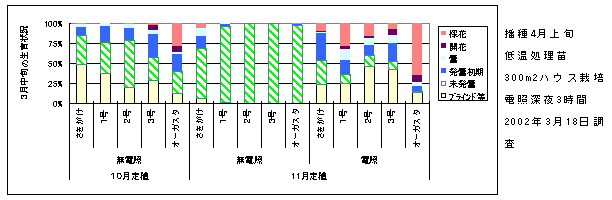
図7 定植時期と電照効果現地試験(沖縄県宜野座村2001年度)
3. ユーチャリス
a.寒冷紗ハウス内での需要期の秋季の自然開花は年によって不安定であった。
2000年9月下旬から11月上旬に自然開花が多かったことから、約2ヶ月前の温度環境を調べたところ、この年は7月下旬から8月上旬に摂氏25度以下の低温期間が1週間程度あった(図8)。
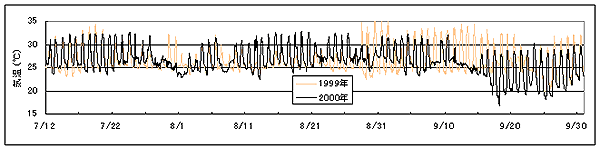
図8 秋季開花増加年(2000年)の温度環境(宜野座寒冷紗ハウス内)
b. 低温処理による秋期採花
7月上旬低温処理開始で9月中旬、7月中旬で10月上旬、7月下旬で10月中旬に開花した。摂氏20度の終日冷房で約3ヶ月弱で開花した。摂氏23度冷房では2.5ヶ月で開花したが、採花率は低下した。8月末あるいは9月中旬からの冷房開始では採花数は激減した。早期に冷房を停止するより、花茎が確認できるまでの処理で採花率は高くなった。地床で栽培中の株に対して7月23日~9月1日冷房温度摂氏20度でまで処理したところ、供試40株から9月下旬の週に一斉に120本が短期間で採花できた。(表4)
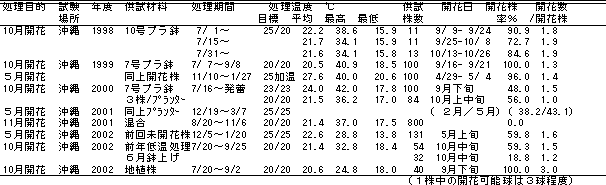
表4 開花調節処理効果
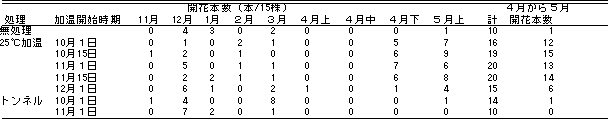
表5 高温抑制栽培における高温処理開始時期の影響
c. 高温管理による初夏採花
初夏の需要期への対応として、冬期花芽が形成されない摂氏25度以上に10月上旬から1月下旬まで暖房管理して株を充実させ、その後の自然低温で花芽を分化させることを試みた結果、4月下旬から5月上旬に採花できた。暖房開始時期が遅れると秋季の低温で花芽分化が進む球根があり、12月からの加温では冬期の不時開花球が増加した。無加温のトンネル被覆環境では効果が無かった。(表4 表5)
エ. 考察
1. カーネション
沖縄において品種間の収量や茎伸長の差が大きかった原因として、温暖な気候条件のため、低温要求の充足が不十分であることが推測された(米村、1990)。摘心時期の調整や苗の低温処理等ではこれに対応できなかったことから、品種の選択がきわめて重要である。沖縄に適した品種は概して早生系であったが、早生品種の中にも沖縄に不向きなものが多数存在し、試作の重要性が確認された。沖縄で開花期が分散しやすく早期化する原因としては、気温がほぼ常に開花を促進する領域にあるためと判明した。夏の高温は、株の枯死の直接的な原因ではなかったことから、将来的には苗の県内生産も不可能ではないと推察された。
2. シンテッポウユリ
種苗コストが安い実生苗を使い、冬期温暖な沖縄県における露地あるいはハウス保温栽培による需要期の彼岸採花作型開発の可能性が期待された。10月中旬のセル成型苗定植では早生品種では弱少開花、晩生種や11月上旬定植では、極早生種の一部を除き、抽台はするものの、花芽分化が遅れ、3~4mに巨大化して4月後半から6月に開花する性質が強かった。摂氏20度程度の高温環境が花芽分化を促進する等の試験結果から、ハウス内平均気温が摂氏20度以下になる12月中旬までに花芽分化をした個体は早く開花し、できなかった個体は摂氏20度程度に気温が上昇する3月前後から花芽を分化したと判断された。長日処理は、花芽分化を早めるために、11月定植でも全品種で花成反応を促進した。揃いと初期生育が良い、比較的晩生種の‘オーガスタ’は理想的な草姿で彼岸前に開花し、この品種を用いた彼岸出荷が可能と判断できた。しかし、他の品種を利用する場合には、商品価値が低い短茎、少花数で開花する傾向が強く、株の充実期間を確保する育苗、定植時期、電照開始時期の検討が必要と考えられた。また花芽分化後の花の発育も高温が必要であった。
3. ユーチャリス
日本中部では8月初旬までの高温によって充実した球根がその後低温に遭遇することによって花芽分化するため、開花は早くとも10月下旬以降になる。早くから高温になる沖縄では、7月からの冷房処理で9月中旬から開花させることが可能であった。光透過率10%程度の弱光環境下での低温処理が可能であるので、採花球率の向上と、冷房コストの低減によって営利生産に結びつけられる技術と考えれた。また冬期に摂氏25度で管理すると、処理以前に花芽を形成していた球根の極一部が早期に開花するものの、11月上旬ごろから暖房を行えば多くの球根は花芽分化が抑制され、暖房停止後の低温に再遭遇後に花芽を分化し、5月前後の結婚式シーズンに開花させることができる。沖縄の冬期の日平均気温は最低でも摂氏15度程度であり、内地における温度付加を考慮すると営利的な周年生産が可能と判断された。年毎の秋期の自然採花数の変動は、偶発する摂氏20~25度の気温低下の時期と、その軽度の低温でも刺激を感じる球根の充実程度に影響されており、球根の充実機作の解明でより有利な生産体系の確立が期待できる。
オ. 今後の課題
1. カーネーション
需要が多い3月と5月上旬の収穫本数の比率を上げることが経営的には有利であり、整枝法の検討が必要である。また将来的には、低コスト生産と害虫の侵入防止のために、沖縄オリジナル品種を育成し、苗を県内生産することが望ましい。
2. シンテッポウユリ
より採花時期を安定化するために、品種生態の解明と育苗法、定植時期、電照開始時期等の検討が必要である。品種、定植時期等の検討により多様な作型の発展が可能である。
3. ユーチャリス
球根の充実機作の解明による低コスト化によって、安定周年供給技術の確立が必要である。
カ. 要 約
1. カーネーション
沖縄に適した品種を用いて、10月に10cm×20cm(株間×条間)で定植し、11月下旬に最終摘心を行うことにより、3月から5月上旬の切り花生産が可能である。
2. シンテッポウユリ
‘オーガスタ’等の初期生育が優れ、やや晩生品種の低温処理苗を11月上旬にハウスに定植し、電照を行うことによって、彼岸時の良品採花が可能である。
3. ユーチャリス
7月上旬~8月上旬からの摂氏20度の低温処理による9月中旬~11月上旬採花、11月から2月までの摂氏25度加温による抑制栽培で4月下旬から5月中の採花が可能であり、需要期に安定供給できる。
キ. 文献
- 今村仁・須藤憲一:カーネーションの開花期予測と母の日を目標とした栽培技術.園学雑,66(別2),568-569(1997)
- 米村浩次:切り花栽培の新技術.カーネーション.上巻.誠文堂新光社.東京.92-94(1990)
- 鷹見敏彦・齊藤哲:実生苗を利用したシンテッポウユリの抑制栽培について.園学雑,71(別2),437(2002)
