荒木陽一・山口博隆
ア. 研究目的
低温性の野菜であるイチゴは、これまで亜熱帯の沖縄で本格的に栽培されることはなかった。しかし、近年、果実が硬く、しかも糖度が高い品種が育成されてきている中で、沖縄でも高品質のイチゴが栽培される可能性が出てきた。一方、沖縄で市販されているイチゴは一部外国産も含まれているが、九州を初めとする県外産が主体である。それゆえ、収穫から店頭に並ぶまでに最低でも3日を要し、鮮度ならびに食味の低下が問題になっている。美味で鮮度の高いイチゴの供給が強く望まれている。
沖縄での基幹作物は現在でもサトウキビであるが、取引価格の低迷で農家経営が苦しくなってきている。農地の流動性が低い沖縄(井上ら2001)では、規模拡大による所得の向上は望めず、いきおい高収益な品目に頼らざるを得ない状況にある。
そこで、高収益品目の一つであるイチゴを沖縄へ適用することを目的に、これまでに沖縄に適する品種の選定(野口ら1999)、沖縄での定植時期の決定(高市ら1999)、沖縄での生態特性の把握(中島ら2000a,中島ら2000b,沖村ら2001)等の検討がなされた。
本課題では、これらの結果を基に沖縄の農家圃場において栽培試験を行い、生育や収量、品質等の生産性の検討を行った。
本研究を行うにあたり、イチゴ実証試験のための圃場をご提供いただき、日々の栽培管理ならびに収穫調査を引き受けて下さった沖縄県宜野座村松田地区の山川吉美様には大変なご協力をいただいた。ここに記して感謝する。
イ. 研究方法
処理区として短日夜冷処理苗区(以後夜冷区)と普通ポット苗区(以後普通区)を設けた。'さちのか'を供試し、雨よけ状態の耐台風性ハウス内で二段階採苗(豆田ら2000)を行い、プランター定植の第2次親株から発生した定植用の子苗を2001年8月14日に親株から切り離してセルトレイに挿苗した。ミスト条件下で発根させた後、9月3日から5日の間に10.5cmのポリポットに鉢上げして定植用苗とした。育苗期間中は45%の遮光資材をハウス外に展張した。
育苗中の苗の半分を夜冷区用とし、9月25日から10月15日までの20日間、短日夜冷処理を行った。短日夜冷処理は定植苗を沖縄県農業試験場園芸支場(沖縄市具志川市)に設置した短日夜冷処理装置に入庫し、昼間は天井部の遮光フィルムを巻き上げて自然光下で成り行き制御とし、夜間(17時~9時)はフィルムを巻き降ろして冷房装置で15°Cになるよう管理した。
短日夜冷処理終了翌日の10月16日に10株を選定して、花芽分化程度を検鏡した。定植は、当初10月16日に行う予定であったが、沖縄近海に1週間近く停滞した台風21号のために、10月22日に行った。普通区は11月1日に花芽分化程度を検鏡した後に定植した。
試験圃場は宜野座村松田地区の県営開拓圃場に設置した。土壌は国頭マージ土壌で、間口6m×奥行き20mの2連棟パイプハウスで試験を行った。
定植2週間前に牛糞主体の堆肥を2t/10aと粒状炭酸苦土石灰を100kg/10a施用した。また、定植1週間前にLPコート140日タイプ入りBB肥料(N:P2O5:K2O=15%:15%:15%)を10a当たり66.7kg(N:P2O5:K2O=10kg:10kg:10kg/10a)施用した後、畦立てを行った。
栽植様式は畦幅120cm,条間23cm,株間25cmの2条外成り方式とし、定植前にシルバーマルチを敷設した。定植時からしばらくの間、活着促進のため45%遮光資材を展張した。ビニルフィルムの展張は11月14日に行った。
環境条件として、ハウス内気温、地温、土壌水分を測定した。気温はハウス中央部で高さ1.5mの位置に、また、地温は深さ10cmの位置にセンサーを設置して測定した。土壌水分はハウス中央部で深さ10cmの位置にテンシオメータを設置して測定した。
株の栄養状態として、葉柄の硝酸イオン濃度並びにカリイオン濃度をコンパクトイオンメータやRQフレックスにより測定した。測定はイチゴの下葉から採取した葉柄を細かく刻み、約1gを乳鉢にとり、蒸留水4mlを加えて摩砕した後、測定に供した。イオン濃度が測定器の測定範囲より高い場合は、適度に希釈した。
生育や果実品質調査はハウス内のうねの一部に長さ約2.5m(20株)の調査箇所を設け、出蕾ならびに果実品質などを調査した。
1果房当たりの果数を12果程度とし、それ以上の花や果実は摘花あるいは摘果した。収量は各処理区全体の規格別出荷パック数で調査した。出荷基準は1パック重を320-330gとし、個数の目安は3Lが12個、2Lが約15個、Lが約20個、Mが約25個、Sが約33個とした。
沖縄産イチゴの優位性を明らかにする目的で、県内のスーパーで販売されていた県外産のイチゴを1パックずつ購入して品質調査を行い、同時に販売されていた宜野座産のイチゴと比較した。調査項目として、1パック内の全ての果実について一果重、果色、果実硬度、糖度ならびに酸度を測定した。
ウ. 結果
定植時(夜冷区は短日夜冷終了時)の花芽分化程度は、夜冷区では頂花房のみ分化が見られ、分化程度としてはガク片形成期から雄ずい形成期まで進んでいた。一方、普通区では頂花房だけでなく第1次腋花房でも花芽分化が見られ、分化程度は頂花房がガク片形成期から雄ずい形成期、第1次腋花房が未分化から肥厚中期であった(第1図)。
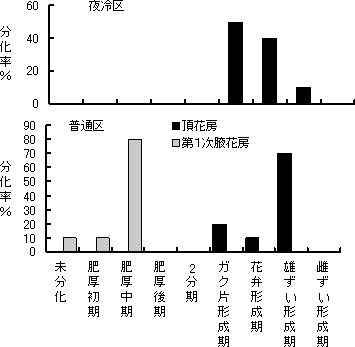 第1図 夜冷区と普通区の花芽分化状況
第1図 夜冷区と普通区の花芽分化状況
注)分化率は調査10株のうちの各分化段階の苗数の割合。
短日夜冷苗は2001年10月16日検鏡。
普通ポット苗は11月1日検鏡。
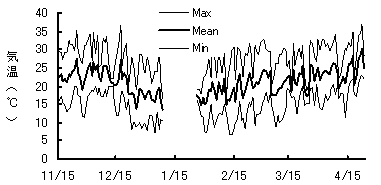
第2図 栽培期間中のハウス内気温の推移
栽培期間中のハウス内の気温変化をみると、日平均気温は12月20日頃までは摂氏20度以上であったが、22日夜半から23日早朝にかけて最低気温が摂氏10度以下になったのに伴って、日平均気温も摂氏20度を下回るようになった。日最高気温は冬季といえども晴天の日は摂氏30度を上回る日が多かった。日最低気温は摂氏10度を下回る日があったが、摂氏5度以下になることはなかった(第2図)。

第3図 栽培期間中のハウス内地温の推移
ハウス内の地温変化をみると、日最高地温はやはり12月20日頃までは摂氏20度以上であったが、それ以降急激に低下し、摂氏17度近くにまで達した。しかし、1月10日あたりから急激に上昇を始め、1月20日頃には摂氏22度まで達した。その後再度低下を始め、2月1日に期間中で最も低い摂氏17度を記録した後、徐々に上昇を続け、収穫終了時には摂氏26度までになった。日最低地温は一番低下した時点で摂氏16度であり、摂氏15度以下になることはなかった(第3図)。
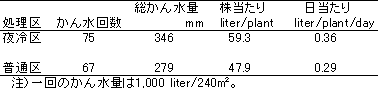
第1表 栽培期間中のかん水量
栽培期間中のかん水量は、定植後しばらくの間は毎日1t/240m2かん水し、ビニール展張後は2日に1回、12月に入って3、4日に1回、2月中旬以降は2、3日に1回の割合でかん水を行った。栽培期間中の総かん水回数は75回(普通区は67回、以下同様)、1株当たり59 liter(48 liter)で、平均すると360 ml/株/日(290 ml/株/日)であった(第1表)。
このかん水に伴う土壌水分吸引圧の変化をみると、年内はpF1.0からpF2.0の範囲内で推移したが、1月以降は若干高く、pF1.5からpF2.5の間で推移した(第4図)。
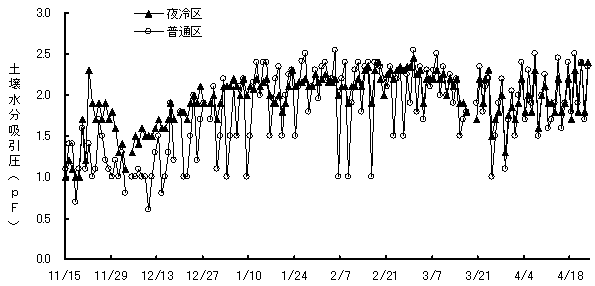
第4図 栽培期間中の土壌水分吸引圧の変化(深さ10cm)
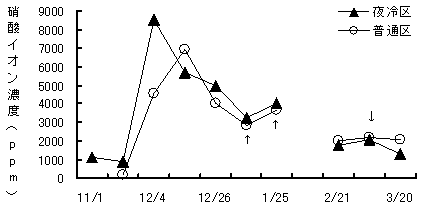
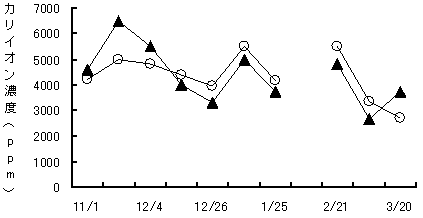
第5図 栽培期間中葉柄搾汁液の濃度変化
注)↓↑は追肥施用時期を示す。
栽培期間中の葉柄の硝酸イオン濃度並びにカリイオン濃度の変化をみると、硝酸イオン濃度は定植が早かった夜冷区が高く推移したが、夜冷区は12月上旬をピークに、普通区は12月中旬をピークに低下を始め、以降は両処理区ともほぼ同じ様な傾向で徐々に濃度を下げながら推移した。カリイオン濃度も初期は夜冷区が高い値で経過したが、12月に入ってからは両処理区とほぼ同程度の値で推移した(第5図)。
育苗期間中を含め栽培期間中は病気や害虫の発生がほとんどなく、定植直後わずかにダニが発生しただけで、それも直ちに防除したので、生育は順調に行われた。
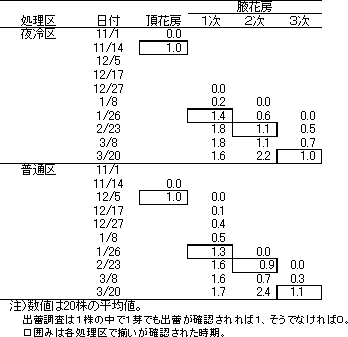
第2表 花芽分化処理が花芽の出蕾に及ぼす影響
頂花房出蕾は短日夜冷処理の有無で異なり、夜冷区が11月14日、普通区が12月5日であった。しかし、第1次ならびに第2次腋花房には夜冷処理の影響はみられず、両処理区ともそれぞれ1月下旬ならびに2月下旬であった(第2表)。
夜冷区は収穫開始が12月16日で、年内は1日おきに15パック程度収穫できたが、年明けから収量が低下し始め、2月下旬の第1次腋果房の収穫開始直前は収穫物がほとんどなくなった。第1次腋果房の収穫に続き、3月中旬から第2次腋果房の収穫が始まった。これに対して、普通区は収穫開始が1月4日で、1月20日頃に頂果房の収穫が最大になった後、2月下旬の第1次腋果房の収穫開始までコンスタントに収穫が続いた。第1次腋果房に続き、3月中旬からは第2次腋果房の収穫が始まり、4月下旬まで収穫が続いた(第6図)。
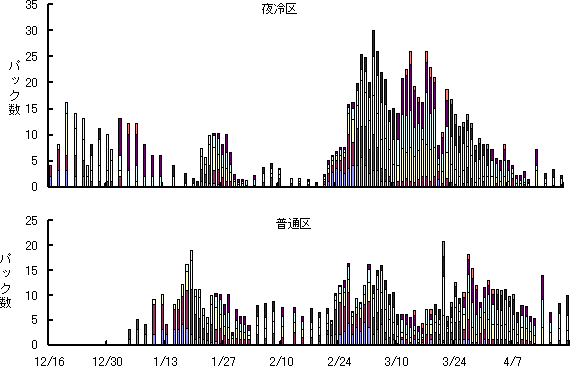
第6図 栽培期間中の日別収量の推移(120m2当たり)
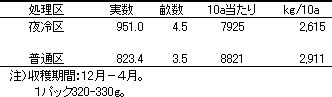
第3表 各処理区の総収量(収穫パック数)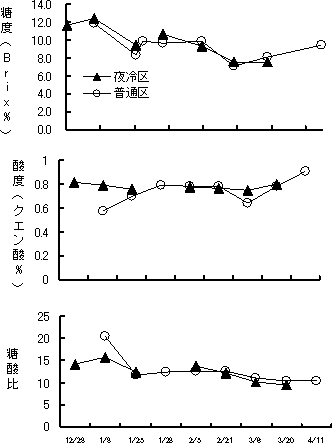
第7図 栽培期間中の果実の糖度、
酸度並びに糖酸比の推移
各処理区の収量は10a換算で夜冷区が2,615kg,普通区が2,911kgであった(第3表)。
果実糖度(Brix%)は年末年始は10%以上であったが、1月下旬から急激に低下し、その後一時的に10%を超す時期もあったが、概して10%以下で推移した。一方、果実酸度は夜冷区では終始0.8%前後で推移したが、普通区では収穫初期は0.6%,収穫中期は0.8%,収穫終期が0.9%と、収穫が進むにつれて徐々に上昇した。この結果、糖酸比は普通区の収穫初期が20と高かったが、それ以外はほぼ15から10の間を徐々に低下しながら推移した(第7図)。
果実品質を市販イチゴと比較した結果、果実硬度は県外産よりも高かったが、糖度は低く、酸度は逆に高く、糖酸比で県外産の1/2程度の値であった(第4表)。
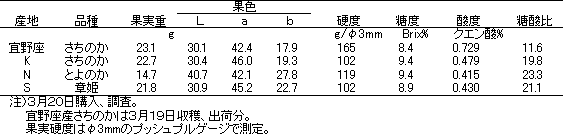
第4表 沖縄県のスーパーで売られていたイチゴの品質調査
エ. 考察
事実、本試験での夜冷区の定植予定日には、台風21号が1週間近く沖縄近海に停滞したため、当初予定していた定植が10月16日から10月22日に延期になった。この影響は定かではないが、木村(1984)は花芽分化後の低窒素条件では開花が遅れ、着果数が減少すると報告している。
夏の高温長日条件下で生育したイチゴ苗は、9月の低温短日条件で花成誘導を受けて花芽が分化する(木村1984)。九州では'さちのか'の花芽の自然条件下における分化時期は9月下旬から10月上旬であるが、沖縄では10月下旬(中島ら2000)から11月上旬(高市ら2001)である。本試験での普通ポット苗の花芽分化もほぼ同時期に行われ、11月1日の検鏡では頂花房の花芽分化はガク片形成期から雄ずい形成期まで進んでいた。また、第1次腋花房も未分化から肥厚中期まで進んでおり、これが頂果房の収穫に引き続いて第1次腋果房の収穫が行われた理由と考えられる。これに対して、短日夜冷処理苗は処理終了時の10月16日の検鏡では、頂花房がガク片形成期から雄ずい形成期まで進んでおり、短日夜冷処理の効果があったと考えられた。しかし、この時点では第1次腋花房の花芽分化は確認できず、これが頂果房と第1次腋果房の収穫の中休み(伏原ら1984)になったと考えられた。
分化した花芽は、その後出蕾、開花という経過を辿るが、本試験では頂花房の出蕾揃いが夜冷区では11月14日、普通区では12月5日で、両処理区とも分化確認からほぼ1ヶ月後であった。収穫開始は夜冷区が12月16日、普通区が1月4日であったので、20日間程度の差があるが、ほぼ花芽分化時期の違いが収穫開始時期の違いにもなって現れたことになる。
しかし、第1次腋花房の出蕾揃いは両処理区とも1月26日で、短日夜冷処理の影響は見られなかった。すなわち短日夜冷処理は頂花房の分化・出蕾を促進したが、第1次腋花房の分化・出雷には影響を及ぼさなかったものと考えられる。
近年、イチゴ栽培においても効率的な肥培管理を行って、生育促進並びに収量増加を図り、施肥量の削減と環境保全の観点から、植物体の栄養診断を行う事例が増えている(六本木1992)。通常葉柄の硝酸イオン濃度とカリイオン濃度が測定されるが、カリイオン濃度は栽培期間中ほぼ一定の値で推移したのに対して、硝酸イオン濃度には大きな変化がみられた。イチゴの場合、通常、花芽分化を促進するために8月中旬以降窒素の供給を中断するが、そのために定植時には硝酸イオンがほとんど検出されない程度にまで低下している。しかし、本圃に定植したイチゴが活着すると、急激に硝酸イオン濃度が上昇し、頂花房の開花期頃にピークに達する。その後、果実の肥大に伴って低下を続けるパターンを描く(六本木1992)。本試験でも同様の経過を辿り、収穫開始後、液肥の供給により一時的に上昇することもあったが、低下の流れを大きく変えるほどではなかった。本試験ではわずかに3回の追肥であったが、硝酸イオン濃度の低下が始まった開花期以降、定期的に追肥を行っていれば、さらなる増収を図ることができた可能性も否定できない。今後はこの点に重点を置いて検討する必要がある。
本試験でのイチゴの収量は、夜冷区が2.6t/10a,普通区が2.9t/10aで、夜冷区の方が少なかった。これは短日夜冷苗が普通ポット苗に比べて早い段階から着果負担に遭遇したためと考えられた(川上ら1990)。一方、前年度の普通ポット苗の収量である1.8t/10a(高市ら未発表)と比較すると、本試験では1.1t/10aほど増加した。この理由として、本試験では第1表に示すように適正な量のかん水(荒木2003)が行われるとともに病害虫の発生が少なかったために、イチゴが順調に生育したこと、農家がイチゴ栽培2回目でいろんな面で栽培技術が向上したことと共に、栄養診断に基づき液肥の追肥を行ったことも増収の一因と考えられる。本試験では3回で合計2kg/10aの窒素を追肥し、元肥と合わせると12kg/10aの窒素を供給したことになる。品種が異なるが、伏原ら(1989)は宝交早生でわずか1回の追肥(3.5~4 kg/10a)でも総収量の増加を確認している。本試験では伏原らの試験の1/2程度の窒素量であったが、収穫期間が1月から4月までの4ヶ月間と伏原らの収穫期間より2ヶ月ほど短かったので、わずか2kg/10aの窒素量でも効果があったものと考えられる。
本試験での収穫期間は夜冷区で4ヶ月、普通区では3.5ヶ月間であった。試験開始当初、沖縄でのイチゴの収穫期間は1月から3月までの3ヶ月間と予想していたが、実際は予想よりも半月から1月ほど延長することが出来た。この理由として、'さちのか'の品種としての優秀性で、年内あるいは3月以降の気温の高い時期でも、高い果実硬度を保ち、また、生食用として許される範囲の糖度を維持(森下ら1997)していたためと考えられた。
イチゴの促成作型において、頂花房の花芽分化を促進すると、第1次腋果房の収穫開始が遅れることが報告されている(伏原ら1984)。本試験でも頂果房の収穫開始が夜冷区で普通区よりも20日ほど早かったのに対し、第1次腋果房の収穫開始が両処理区でほぼ同時期であった。そのために夜冷区の収量が年明け頃から少なくなり、第1次腋果房の収穫開始直前には収穫物がほとんどない状態になった。これに対して、普通区の収穫は年明けから始まり、2月下旬の第1次腋果房の収穫開始まで、収穫が途絶えることなく、ほぼ一定の収穫物が得られた。この夜冷区と普通区の日別収量を各5aで換算して図示すると第8図のようになる。
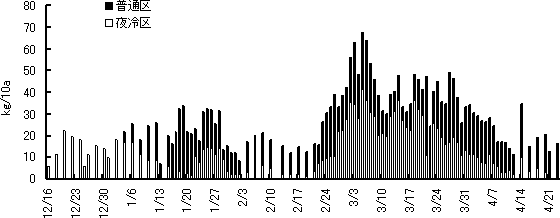
第8図 短日夜冷苗と普通ポット苗の組合せによる日別収量の変化
注)各処理区5a換算。
すなわち、12月中旬から収穫が始まった夜冷区の収量は1月に入ると減少してきたが、その頃から普通区の収穫が始まり、夜冷区の収量減少を補う形で、普通区の収量が増大した。花芽分化処理の有無にかかわらず、第1次腋果房の収穫開始はほぼ同時期の2月下旬から始まり、大きな収穫の山となった。引き続いて第2次腋果房の収穫が始まったので、収穫の山は4月中旬まで続いた。この結果、収穫期間は12月中旬から4月中旬までの4ヶ月間であった。亜熱帯の沖縄では、高温のためにどうしても収穫期間が短くならざるを得ない。一つの作型だけで栽培した場合、例えば短日夜冷を行う作型では、収穫開始は早いが収穫の中休みが生ずるとともに、全体収量が低いという欠点がある。また、普通ポット苗を用いる作型では、総収量は多いが、単価の高い12月の収穫が期待できないという欠点がある。それゆえ、台風ならびに高温のために、短期栽培を目指さざるを得ない沖縄では、短日夜冷苗と普通ポット苗を組み合わせた栽培を行うのが合理的と考えられる。
果実糖度は1月上旬までは10%以上であったが、それ以降は10%以下で推移した。これは第3図で明らかなように、1月中旬に高温の日が続いたために、急激に糖度が低下し、その後気温が徐々に上昇(特に最低気温)したために、結局10%以上になることはなかった。沖縄の春は天気の変化が目まぐるしく、晴天の日にはハウス内が35°C以上になることもある。しかし、沖縄のハウスは電気の通じていないところが多く、換気扇を用いて気温を下げることは期待できない。せいぜい天井部への寒冷紗の被覆あるいは天窓・側窓の開放程度であり、大きな気温上昇抑制効果は望めない。
トマトではかん水を控えることにより糖度を高めることは可能である(荒木ら1994)。しかし、チップバーンの発生しやすいイチゴではかん水を控えることによる糖度上昇は期待できないし、また、その効果も小さいと考えられる。事実、本試験でも第4図に示すように、夜冷区の土壌水分吸引圧が普通区より高く推移したが、糖度は両処理区ともほぼ同程度の値で推移し(第7図)、果実糖度に及ぼす土壌水分の影響は小さいと考えられた。
野口ら(1999)は、現在国内で栽培されている主要品種を沖縄で栽培し、総合評価として'さちのか'が最も適していると報告している。したがって、将来的には沖縄において沖縄の気候に適した品種を育成する必要がある。その時の育種目標としては、(1)果実硬度が高い、(2)果実の糖度が高く、糖酸比が高い、(3)大果性である、(4)花芽分化が容易である、などがあげられる。
このような沖縄産イチゴであるが、沖縄県内で販売されている県外産イチゴと比較すると、糖度で0.5~1.0度ほど低く、酸度で2倍ほど高く、糖酸比で1/2程度で、食味としては県外産には及ばないことが明らかになった。しかし、果実硬度は県外産の1.5倍ほど高く、鮮度が高いことが明らかになった。県外産が沖縄の店頭に並ぶのは早くて収穫から3日後であるため、収穫からかなりの時間が経過している。また、沖縄へ航空機で運ばれたとしても複数回の積み卸しを行うために、荷傷みが生じている。それゆえ、現状で沖縄産イチゴが県外産イチゴに勝る点は、果実が硬いということと、果皮色が鮮明で光沢があるという点であり、これらの点をセールスポイントとして売り込んで行くことが可能と考えられる。
オ. 今後の課題
沖縄でのイチゴ栽培は、育苗期間に比して収穫期間が短い。それゆえ、省力的な育苗方法を開発する必要がある。また、育苗に耐台風性ハウスが必要となるため、個別農家毎の育苗は難しく、JA等による苗の育苗、花芽分化処理、ならびに配布体制を整備する必要がある。さらに、収穫期間を延長するには複数の作型を組み合わせる必要があり、花芽分化処理方法や遮光等の施設内環境調節技術を開発する必要がある。加えて、果実品質の低下を防止する環境調節技術や、流通技術の開発を行う必要がある。
カ. 要約
亜熱帯の沖縄において、イチゴの年内収穫を可能にするとともに、収穫の波を小さくし、1シーズンの総収量を3t/10aとする技術開発を行った。
- 短日夜冷装置を用いて、'さちのか'の花芽を確実に分化させると、12月中旬から収穫が始まった。
- 頂果房の収穫を早めることにより収穫の中休み現象が見られたが、普通ポット苗を組み合わせることにより、日々一定量の収量を確保できた。
- 花芽分化処理の有無にかかわらず、第1次腋果房の収穫はほぼ同時期に始まり、引き続いて第2次腋果房の収穫が始まったため、大きな収穫の山となった。
- 栄養診断に基づき液肥の追肥を行ったところ、目標とする3t/10aに近い収量が得られた
キ. 文献
- 荒木陽一(2003)土壌水分制御.「五訂施設園芸ハンドブック」(日本施設園芸協会)p.196-205. 園芸情報センター、東京.
- 荒木陽一(1994)体内水分を指標とした温室トマトの水管理に関する研究、野菜茶試研報 A.8;63-103.
- 伏原肇・室園正敏・吉武貞敏(1984)促成イチゴの中休み現象に関する研究第1報 'はるのか'産地における実態について、福岡農総試研報 B-4;25-30.
- 伏原肇・室園正敏(1989) 促成イチゴの中休み現象に関する研究第4報定植時期及び定植後の追肥が生育・収量に及ぼす影響, 福岡農総試研報 B-9;13-16.
- 井上裕之・田口喜勝(2001)沖縄における農地貸借のメカニズムと今日的特徴、日本農業経営学会『農業経営研究』 39(2).
- 川上敬志・青木宏史・土岐知久(1990)イチゴの夜冷育苗による熟期促進法、千葉農試研報 31;55-72.
- 木村雅行(1984)II花芽の分化と発育「農業技術大系野菜編3イチゴ」p.基33 -基53. 農文協、東京.
- 豆田和浩・浦田丈一・田中龍臣(2000)イチゴの二段階採苗法における採苗時期と生育、収量、九農研機構 62;178.
- 森下昌三・望月龍也・野口裕司・曽根一純・山川理(1997)促成栽培用イチゴ新品種'さちのか'の育成経過とその特性、野菜茶誌研報 12;91-115.
- 中島規子・宮城信一・高市益行・久場峯子・荒木陽一(2000a)沖縄における採苗時期の違いと株冷処理の有無がイチゴの花芽分化・生育および収量に及ぼす影響、園学誌 69(別2);341.
- 中島規子・宮城信一・高市益行・久場峯子・荒木陽一(2000b)沖縄におけるイチゴ花芽の自然分化時期と温度の関係、園学九支研究集録8;71.
- 野口裕司・宮城信一・望月龍也・曽根一純・久場峯子(1999)生態特性の異なるイチゴ品種の沖縄における生育、収量及び果実特性、園学誌 68(別2);255.
- 沖村誠・曽根一純・宮城信一・中島規子・望月龍也(2001)生態特性の異なるイチゴ品種の沖縄における自然開花期および生育・収量・果実特性、九農研機構 63:181.
- 沖縄気象台(2002)台風の発生数と沖縄県への接近数(1955年~2001年)、沖縄気象台予報課防災係作成.
- 六本木和夫(1992)果菜類の栄養診断に関する研究(第2報)葉柄汁液の硝酸態窒素濃度に基づくイチゴの栄養診断、埼玉園試研報 19;19-29.
- 高市益行・田中和夫・中島規子・野口裕司・宮城信一・久場峯子・山崎篤・荒木陽一(1999)亜熱帯(沖縄)における促成イチゴ品種'とよのか'および'さちのか'の開花・生育特性、園学誌 68(別2);254.
- 高市益行・登野盛博一・中島規子・荒木陽一・小橋川共志・久場峯子(2001)亜熱帯の沖縄におけるイチゴ品種'とよのか'および'さちのか'の花芽分化特性および収量性、園学誌 70(別2);296.
