虫害;柏尾具俊、病害;西村範夫・小板橋基夫
ア. 研究目的
沖縄県のサトウキビ産地への導入を試みるイチゴ、カーネーション、シンテッポウユリ、ユーチャリスを対象に、生産地における重要病虫害の把握及び原因が明らかでない重要病害虫の生態解明や防除試験を実施し、防除法を確立する。これらの安定生産技術の確立に資する。
イ. 研究方法
- イチゴ苗に寄生するミカンキイロアザミウマの臭化メチルくん蒸による殺虫法を確立した。また、温湯浸漬による殺虫法を開発した。
- 沖縄県農業試験場園芸支場内のイチゴの試験圃場においてイチゴの病害診断を行った。採取または園芸支場から送付された罹病株から病斑部を切り取り、表面殺菌した後、素寒天培地に置床して糸状菌を分離した。イチゴから分離したF. oxysporumと疫病菌について接種試験を行い病原性を確認した。
- 沖縄県において既存の登録農薬で防除が可能であるか否かを明らかにするため、平成13、14年度に、ガラスハウスにおいてプランタで育苗し、ドリップ灌水を行い、ほぼ2週間間隔で既登録農薬を散布した。また、萎黄病対策として夏季に太陽熱消毒とクロルピクリンによる土壌消毒を実施した。
- 沖縄県のイチゴの実証試験ほ場において主要害虫の種類と発生時期量を調査した。また、実証ほ場で採集したナミハダニの各種殺ダニ剤の感受性検定を行った。これらの結果に基づき、沖縄県におけるイチゴ害虫の防除体系を策定した。
- 沖縄県北部の東村で栽培されているユーチャリスにおいて病害診断を実施した。ユーチャリスから分離したBotrytisの病原性は接種試験で確認した。ウイルス病については九州農試病害遺伝子制御研究室が診断した。
- ユーチャリス、カーネーション、シンテッポウユリで発生する重要害虫の種類を調査した。また、ユーチャリスで被害の大きいオモトアザミウマの加害様相、有効薬剤の探索、防除試験を行った。
ウ. 結果
- 臭化メチルの20g~40g/m3の2時間のくん蒸処理は、ミカンキイロアザミウマの卵、幼虫、蛹、成虫を100%の殺虫することができた。また、同様の処理条件でイチゴ苗に寄生したミカンキイロアザミウマは完全に殺虫された(表1)。本処理による‘さちのか’と‘とよのか’の苗に対して薬害並びに生育に影響は認められず、臭化メチルによるイチゴ苗に寄生した殺虫法が確立された。
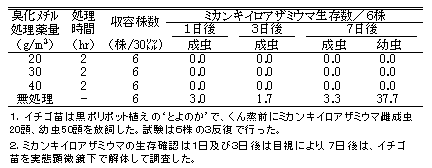
表1 イチゴ苗に寄生したミカンキイロアザミウマの臭化メチルくん蒸による殺虫効果 - ミカンキイロアザミウマのイチゴの葉の組織内に産下された卵、イチゴ葉上の幼虫および成虫は摂氏45度の温湯に5分以上浸漬処理することで完全に殺虫された。処理温度が摂氏47度の場合は3分以上、摂氏50度の場合は2分以上で同様の効果が得られた(表2)。また、アザミウマの寄生したイチゴ苗をポットごと摂氏45度または摂氏47度の場合は5分間、摂氏50度の場合は3分間の温湯浸漬処理により完全殺虫ができた。花芽分化後の‘さちのか’と‘とよのか’の苗は、摂氏47度と摂氏50度の5分間の温湯処理により、処理直後に未展開葉にわずかな褐変が見られるが、処理後の生育や出蕾時期への影響は見られなかった。また、イチゴ苗に利用できる温湯処理装置は、市販のポリ水槽(350リットル)、投げ込みヒーター、温水の攪拌用ポンプ等を組み合わせることで簡単に作成でき、コンテナに20株前後のポットを並べて一度に処理することが可能であった(図1)。
また、イチゴ苗に利用できる温湯処理装置は、市販のポリ水槽(350リットル)、投げ込みヒーター、温水の攪拌用ポンプ等を組み合わせることで簡単に作成でき、コンテナに20株前後のポットを並べて一度に処理することが可能であった(図1)。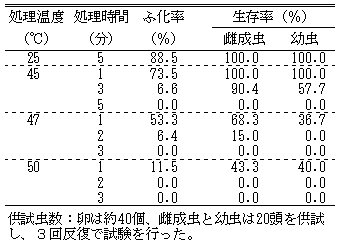
表2 ミカンキイロアザミウマに対する温湯処理の影響
図1 試作した温湯浸漬処理装置 - 沖縄県におけるイチゴの重要病害は炭疽病、うどんこ病、疫病、萎黄病であり、この他に菌核病と灰色かび病の発生が認められた。これらは九州地域と同じであるが、炭疽病及び萎黄病により1、2月にも枯死株が発生するという点に特徴があった。
平成13年に夏期に発生するうどんこ病が認められたが、分離同定はできなかった。平成13年度と14年度の散布実績を表2に示した。13年度には、うどんこ病は前作終期の4月に発生したが、5月以降の育苗期には発生しなかった。炭疽病または疫病は6,000株中10~20株の発病にとどまった。平成14年度もほぼ同様であり、雨よけ、ドリップ灌水、農薬散布により、病害の発生は抑制された。 - 沖縄県のイチゴの実証ほ場で見られる主要害虫は、ハダニ類、ワタアブラムシ、ハスモンヨトウであり、本土のイチゴ栽培で見られる主要害虫と同様であった。ハダニ類は、育苗期、本圃ともに発生が多い傾向にあり、実証ほ場では試験開始1年目と2年目においては、基本防除体系に沿った防除が行われたにもかかわらず多発し、かなりの被害が問題となった。
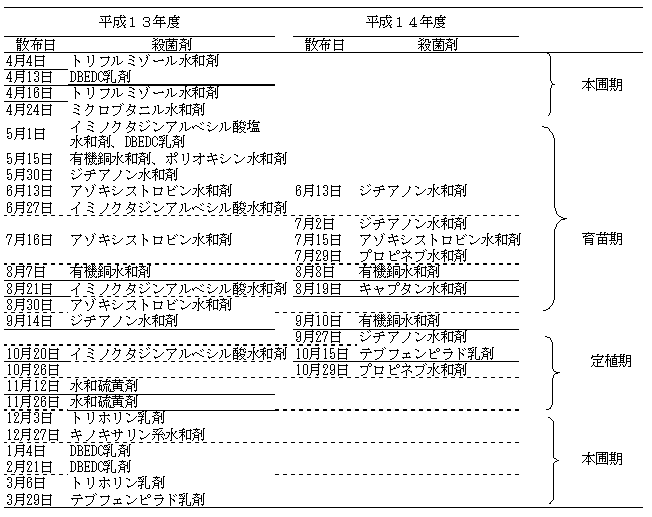
表3 平成13年度、平成14年度の薬剤散布暦(沖縄県園芸支場)
しかし、ハダニの防除を行う上での注意点について農家への指導を徹底した結果、3年目には高い防除効果が得られた。また、現地のハダニを対象に薬剤抵抗性の有無を検討した結果、ビフェナゼート水和剤、ミルベメクチン乳剤、エトキサゾールフロアブル等の主要殺ダニ剤は感受性の低下は見られなかった。アザミウマ類としては、育苗期にはミナミキイロアザミウマの被害が多く、本圃では、3月~4月にかけてヒラズハナアザミウマの発生が見られたが、1~2回の薬剤散布で防除は可能であった。このほか、イチゴの実証ほ場では3年目にタイワンキドクガやシャクトリガ類による加害が見られたが、ハスモンヨトウに有効な薬剤での同時防除で高い効果が得られた。なお、ミカンキイロアザミウマについては、試験用のイチゴを沖縄県に持ち込む際、臭化メチルによるくん蒸を実施した結果、現地試験ほ場での発生は試験期間を通じて見られなかった。
図2 ユーチャリスのウイルス病と灰色かび病
大型病斑は灰色がび病、葉の凹凸とモザイク症状はウイルス病 - ユーチャリスの重要病害はウイルス病、灰色かび病、白絹病であった(図2)。ウイルス病は蔓延しており、激しいモザイク症状株でアマゾンユリウイルス、やや症状の軽い株でPotyvirusまたはCarlavirusグループのウイルスが確認された。密植で湿度が高いハウスでは灰色かび病と白絹病の発生が認められ、坪状に欠株を生じたハウスがあった。
- ユーチャリスを加害する害虫はアザミウマ類、ナメクジ類、アフリカマイマイ、ハスモンヨトウであった。このうちアザミウマ類による花の被害は著しく、生産安定の阻害要因となっていることが明らかにされた。アザミウマの種について同定を行った結果、オモトアザミウマTaeniothrips eucharii (Whetzel)と特定された(図3)。
本種による被害は花、蕾、苞、茎、葉に見られる。花と蕾は加害部が褐変し、著しい場合には奇形花となることや苞開花前に黄変し、開花時までに枯死する(図4、5)。そのため、本種の加害を受けると商品価値が著しく低下することが明らかになった。また、本種は10月から5月までの間いずれの時期においてもユーチャリスの花や蕾に見られ、沖縄県では未調査の盛夏期を除いてほぼ周年発生していることや本種は出蕾直後から花蕾に寄生し産卵する等の生態的知見が得られた。
図4 ユーチャリスの健全花(上)と被害花(下)
図3 オモトアザミウマの成虫(左)と幼虫(右)
図5 ユーチャリスの健全蕾(左)と被害蕾(中、右)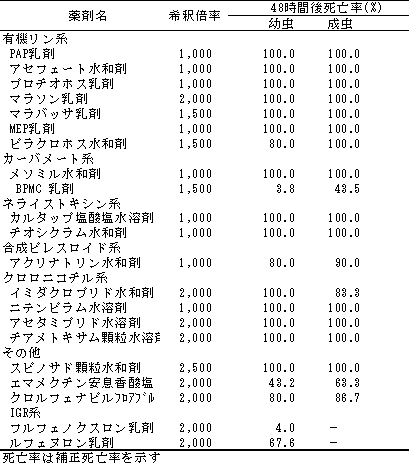
表4 オモトアザミウマに対する各種薬剤の殺虫効果 - オモトアザミウマの幼虫と成虫に対して高い殺虫活性を有する薬剤は、有機リン剤のPAP乳剤、MEP乳剤、マラソン乳剤など6薬剤、クロロニコチル系のアドマイヤー水和剤、ニテンピラム水溶剤等4薬剤、スピノサド顆粒水和剤、チオシクラム水和剤、カルタップ塩酸塩水溶剤、メソミル水和剤であることを明らかにした。これらの有効薬剤を利用した防除試験を実施した結果、本種に対する防除は出蕾直後から開花時までほぼ1週間間隔で実施することにより高い防除効果が得られることが実証された。
- カーネーションでは、ハダニ類のよる加害が見られた以外には特に問題になる害虫は見られなかった。また、シンテッポウユリでは問題となる害虫は見られなかった。
エ. 考察
- 本プロジェクトの第一の目的は沖縄県においてイチゴの栽培法を確立することであり、本土からイチゴの苗を持ち込む必要があった。しかし、本土では侵入害虫のミカンキイロアザミウマが発生しており、イチゴは本害虫の好適な寄主植物であることから、イチゴ苗とともに本害虫を未発生地の沖縄県へ持ち込む危険性が指摘された。しかし、臭化メチルによるイチゴ苗寄生のミカンキイロアザミウマの完全殺虫法を開発するとともに、沖縄県で試験に供するイチゴ苗はすべて本法によってくん蒸処理を行った。こうした対策を講じることにより本害虫の沖縄県への持ち込みを完全に防止した。また、温湯浸漬による本害虫の殺虫法は、簡便であることや環境への影響が少ない方法であることから、沖縄県内でのイチゴ苗の配布の際のミカンキイロアザミウマの分布拡大の防止対策として有効な方法と考えられる。
- 沖縄県では本土復帰以前から少数の農家によりイチゴの試作栽培が行われてきた。その際に問題になった病害虫は炭疽病、うどんこ病、スリップス、ハダニであり、これらの防除が大変重要であると報告されている(濱井ら、1991)。園芸支場内の試験では、これら以外に疫病と萎黄病が発生し、炭疽病と萎黄病により冬季にも枯死株が発生することが明らかになった。露地育苗での炭疽病の防除は難しいが、雨よけ栽培(石川ら、1989)及び雨よけとミスト灌水の組み合わせ(山口ら、1999)の防除効果は非常に高いことが報告されている。本試験では、雨よけ栽培とドリップ灌水を行い、既存の登録農薬で育苗期間中の二次感染を防ぎ、炭疽病、萎黄病、疫病による発病株を廃棄することにより、発病株をごく少数に抑えることができることを実証した。本プロジェクトで考案された二段階育苗方式では、第一段階の株数が少ないため、下葉かきを十分に行うことが可能である。薬剤散布の効果が向上して二次感染を防ぎ、同時に発病株を除去することにより、発病が抑制されたと推察される。炭疽病菌の不活化は罹病残さの嫌気的発酵で可能(石川ら、1990)であり、発病株や除去した下葉をビニール袋に入れて、空気を排出して密封し、施設内に置いておく方法が良いと考えられる。うどんこ病は雨よけ栽培で発生しやすくなるが、下葉かきを十分行うことができれば薬剤防除で抑えることは可能である。また、萎黄病が本圃で発生したら、燻蒸剤または太陽熱により土壌消毒をする必要がある。
- 沖縄県の試験ほ場で問題となるイチゴの害虫は、ハダニ類、ハスモンヨトウ、ワタアブラムシなどであり、本土のイチゴ栽培で問題となる害虫と同様であった。しかし、ハダニ類の発生は多い傾向が見られたことから、育苗期に防除を徹底し、苗からハダニを本圃に持ち込まないことが重要である。また、本圃においてもハダニの発生に注意し、発生初期から防除を行う必要がある。
- ユーチャリスではウイルス病が農家ハウスで蔓延しているが、発病程度と被害の関係およびアマゾンリリーモザイクウイルス(寺見ら、1993)以外に感染しているウイルスが明らかではなく、今後、これらについての研究を進める必要がある。また、灰色かび病と白絹病については、寒冷紗被覆と過繁茂が関与していると推察されるので、株の管理を十分行い、通風を良くすることが重要である。
- ユーチャリスの虫害としては、オモトアザミウマが重要であることを明らかにした。また、本種に有効な薬剤は多く、出蕾時から防除することにより高い防除効果が得られることが明らかになった。しかし、有効薬剤の多くはユーチャリスではほとんどが未登録であるので、登録促進が望まれる。
オ. 今後の考察
- イチゴの病害虫の防除については、基本防除体系で対応が可能と考えられる。しかし、沖縄県での栽培の年次は浅く、沖縄県特有の発生様相にともなう問題が生じる可能性や固有の病害虫の発生も予想されることから、今後も病害虫の防除に関してフォローアップの体制が必要と考えられる。
- ユーチャリスの病害虫についての防除対策は構築できたが、カーネーション、シンテッポウユリについては病害虫の問題の把握は十分できなかった。これらの品目についても、今後、病害虫の問題が生じる可能性も否めないので、フォローアップ体制が必要と考えられる。
カ. 要約
- ミカンキイロアザミウマの臭化メチルによる殺虫法と温湯浸漬による殺虫法を開発した。
- 沖縄県におけるイチゴ栽培で発生する主要病害虫を明らかにするとともにその基本防除体系を策定した。
- ユーチャリスの重要病害虫を特定するとともにその防除対策を策定した。
キ. 文献
- 石川成寿・田村恭志・中山喜一・大兼善三郎 (1989) イチゴ炭そ病の育苗期の雨よけ栽培による防除効果。関東東山病害虫研究会年報 36:87。
- 石川成寿・萩原廣・中山喜一・国安克人 (1990) 罹病残さの嫌気的発酵によるイチゴ炭そ病菌の不活化。関東東山病害虫研究会年報 37:111-112。
- 濱井嘉則・松田義昭・大仲裕冶・福村直樹・上原周夫 (1991) 亜熱帯地域における経済作物としてのイチゴ栽培。南方資源利用技術研究会誌 7:15-20。
- 寺見文宏・本田要八郎・福本文良 (1990) ユーチャリスEucharis grandifloraのモザイク病株より分離されたPotyvirus:Amazon Lily mozaic virus(新称)。日本植物病理学会報 59:334。
- 山口純一郎・菖蒲信一郎・御厨初子 (1999) イチゴ炭疽病の体系防除。平成11年度病害虫防除法改善連絡試験成績野菜作編(九州病害虫防除推進協議会編集)、p26-27。
