久保寺秀夫
ア. 研究目的
沖縄県に広く分布しているマージ土壌は、乾燥時の硬化性、飽水時の粘着性、降雨時の流亡性などが大きく、保水能や有効水分量が小さいなど、物理性の面で問題を有する土壌である。一般に、土壌物理性の改善には堆肥などの有機物の施用が有効であるが、沖縄県においては耕種農家への家畜ふん尿等の供給が十分ではなく、農耕地への有機物施用量は九州の他県に比べ小さい1)。また南西諸島の土壌の一部では、有機物の施用に伴う物理性の悪化(硬化性や粘着性の増大)が見られる。本課題では、限られた地域資源である有機物を最大限に活用して土壌物理性の改善を行うため、マージ土壌の物理性とくに乾燥時の硬化特性と、それに対する各種の有機物施用の影響を解析した。
イ. 研究方法
- 沖縄本島内各地の土壌保全事業調査定点から採取したマージ土壌6点(うち島尻マージ(琉球石灰岩を母材とする暗赤色土)3点、国頭マージ(堆積岩や国頭礫層を母材とする赤黄色土)3点)、長崎県諫早市の同県農試から採取した黄色土1点および宜野座村惣慶の島尻マージ1点に実験室内で10aあたり3tおよび12t相当量の牛ふん堆肥を混和し、毛管水飽和→1×1×2cm程度の角柱に整形→風乾の手順で試料を作成し、風乾時の硬化度合い(以下では硬化強度)を一軸圧縮試験で測定して、有機物混和に伴う土壌硬化促進の発生の有無を調べた(予備試験)。
- 宜野座村松田、宜野座および惣慶の各地域の農家に対し、有機物資材の施用状況を聞き取り調査するとともに、圃場から表土を採取した。この土壌試料43点に対して、硬化強度測定(前項に示した方法による)および一般理化学性の分析を行い、硬化強度に関与している要因について解析した。
- 前項の調査結果に基づいた設計により、土壌と有機物を混和した試料をガラス繊維ろ紙に包んで村内に埋設し、定期回収して理化学性分析と硬化強度測定を行って、有機物分解に伴う理化学性と硬化強度の経時変化を追跡した。
ウ. 結果
- 沖縄県各地の定点等の試料の硬化強度(風乾時の一軸圧縮強度)は、粒径組成が細粒質のもので大きく、島尻マージ細>他の試料>国頭マージ粗であった(図1)。堆肥の添加による硬化性の増大が明瞭に表れたのは、国頭マージ細および宜野座村惣慶の島尻マージの3t区のみであった。この結果は、堆肥混和に伴うマージ土壌の硬化性の増大は確かに起きうるが、それはごく限られた条件(土壌種および混和量)において発生することを示している。
- 宜野座村内の農家に対し行った聞き取り調査では、施用している有機物の種類は農協堆肥(鶏ふんおよびビールかすが原料)と鶏ふんが多く、豚ふん堆肥、牛ふん堆肥、バガスも見られた。施用量はほとんどの圃場で10aあたり年間2t以下であった。施用量と土壌の全炭素含量の間に明確な関係は見られなかった(図2)。
表1に、村内の農家圃場表層土の硬化強度と主要理化学性を、3~5段階に分けた頻度分布で示した。硬化強度は試料によって大きく異なり、最小は0.6 MPa 、最大は6.4 MPa であった。土色では、色相は7.5YRが試料の半数を、5YRと10YRが四分の一ずつを占めた。明度は5から6,彩度は6から8が主体であった。粒径組成は多くの試料で、砂含量が55 %以下、粘土含量が25 %以上、土性はHCからLiCと細粒質であった。仮比重は多くが1.2から1.5の範囲にあった。全炭素は、ほとんどの試料で16 g kg-1 以下(その多くは10 g kg-1 以下)と小さい値を示した。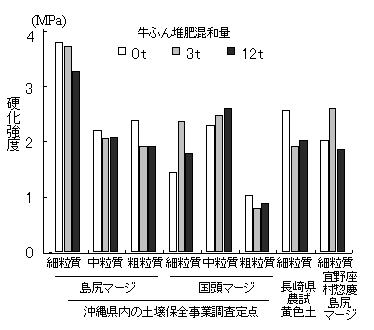
図1 牛ふん堆肥を混和した土壌の硬化強度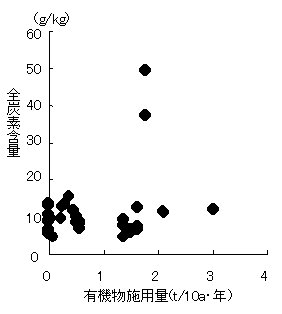
図2 農家圃場の有機物施肥量と土壌の全炭素量の関係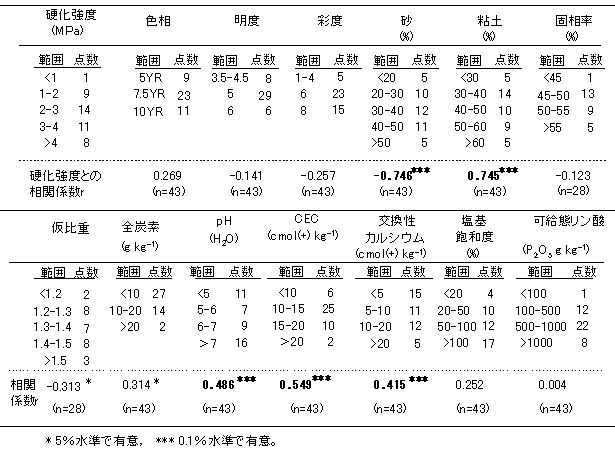
表 1村内の農家圃場表層土の硬化強度および理化学性
pH(H2O)は4以下の強酸性から7以上のアルカリ性と広い範囲にあり、隣接した圃場間や同一圃場の地点間でもpHが大きく異なる場合も見られた。交換性カルシウムは大半の試料が20 cmol(+) kg-1 以下で、pHと正の関係にあった。ほとんどの試料で交換性マグネシウムは3 cmol(+) kg-1 以下、交換性カリウムおよびナトリウムは1 cmol(+) kg-1 以下と小さい値を示した(表には数値略)。CECは大半の試料が10~20 cmol(+) kg-1 の範囲にあった。塩基飽和度は20 %以下から100 %以上と広い範囲にあり、交換性カルシウム量と密接な正の関係にあった。
これらの理化学性と、硬化強度との間の関係を、表1の下段に相関係数で示した。硬化強度に対し、特に密接な関係を持つ性質(太字で示した相関係数、0.1%水準で有意のもの)は、粒径組成、pH,CECならびに交換性カルシウム量である。これらのうち、粘土含量(以下では粒径組成の尺度として粘土含量を用いる)とCECの間、およびpHと交換性カルシウムの間には密接な正の関係があった。CECは粘土含量の多さを反映する性質であるから、硬化強度と密接な関係にある理化学性は、【粘土含量】と【pH - 交換性カルシウム】の2組にくくれる。
粘土含量、ならびにpHと、硬化強度の関係を見ると(図3)、粘土含量と硬化強度の間に密接な正の関係があることと、粘土含量が同程度の試料ではpHが高い土壌の硬化強度が大きく、特に細粒質の試料でこの差が顕著に表れることがわかる。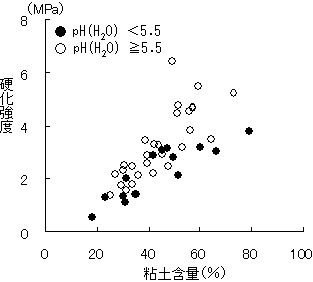
図3 村内の土壌の粘土含量及びpHと硬化強度の関係
粘土含量が大きい土壌は乾燥に伴う収縮度合いが大きかった。これが、土壌粒子間の摩擦力を大きくし、硬化強度を増大させるものと考えられた。pHの高い土壌と低い土壌の間では収縮度合いには明確な差は見られなかった。pHの低い土壌(pH(H2O)が5.0,硬化強度が2.6 MPa)にアルカリ溶液を添加してpHを7.8まで増大させると、硬化強度も4.9 MPaと顕著に増大した。また、塩化カルシウム溶液の添加により、pHを上昇させることなく全塩基置換容量に相当する量のカルシウムイオンを加えた場合も、硬化強度は4.0 MPaまで増大した。アルカリ溶液を添加した場合は、土壌の収縮度合いの増大は見られなかったが、塩化カルシウム溶液を添加した場合は収縮度合いが増大した。pHの高い土壌と低い土壌の間で、粘土鉱物組成や粒径組成の微妙な差など、硬化強度に影響しうる他の因子に関する差はなく、いずれの試料も粘土鉱物組成は2:1-2:1:1型中間種鉱物、イライトならびに0.7nmカオリン鉱物が主体、粒径は0.2-0.4μmおよび2-5μmの画分に二つのピークを持っていた。 - 前項に示したように、村内のマージ土壌の硬化強度には粘土含量とpHが強く影響している。これらに比べ、全炭素量や有機物施用量と硬化強度の関係は明瞭でないが、これは粘土含量やpHが硬化に及ぼす影響が強いため、有機物の影響はその陰に隠れていることによると考えられた。そこで、粘土含量およびpHが異なる土壌4種に各種の有機物を混和して村内に埋設し、有機物の種類およびその分解が硬化強度に及ぼす影響をより詳細に解析することを試みた。供試土壌は表2に示したようにアルカリ性と酸性の土壌で、それぞれについて粒径組成が細粒質のもの(粘土含量57~60%)とやや粗粒のもの(粘土含量31~36%)の4種類を用いた。混和する有機物は前々項の調査結果に基づき、農協堆肥・バガス・豚ふん堆肥・牛ふん堆肥と、九州沖縄農業研究センターで作成された牛ふんペレット堆肥を使用した。有機物は10t/10a相当量(仮比重1.0,作土深15cmと土壌400gに対し26.7g)を混和し、ガラス繊維ろ紙と防根シートで包んで村内に埋設し、定期回収した。有機物の分解に伴う全炭素含量の変化は、図4に示したように牛ふん堆肥と牛ふんペレット堆肥が他の有機物に比べて減少が遅かった。土壌の硬化強度(図5)を見ると、細粒質の土壌では、混和直後から埋設1ヶ月の間は硬化強度は対照(無混和の土壌)より小さかったが、経時的に硬化強度が増大し、埋設6ヶ月では多くの有機物種で対照より大きくなった。ただし埋設後12ヶ月目には硬化強度は再び減少し、ほとんどの区で対照以下に戻った。有機物種間の差は、アルカリ性土壌では明確でなかったが、酸性土壌では農協堆肥区ついで豚ふん堆肥区の硬化強度がやや大きい傾向にあった。粗粒の土壌では、有機物の施用に伴い硬化強度が若干増大する場合もあったが、元々の硬化強度が小さいこともあり、硬化強度増大は細粒土壌のように明瞭には表れず、有機物種間の差や経時変化も明確ではなかった。
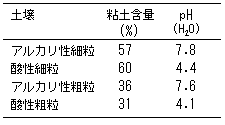
表2 ガラス繊維ろ紙法による有機物埋設試験の供試土壌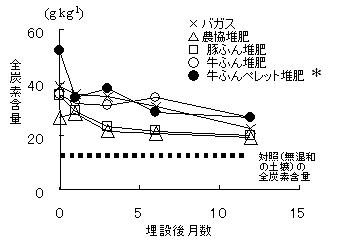
図4 有機物を混和した土壌の全炭素含量の経時変化(酸性細粒土壌)
*混和直後における牛ふんペレット堆肥区の値(52)は、混和不十分による過大値と思われる。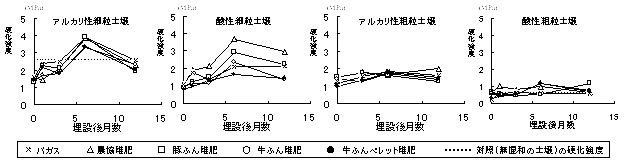
図5 有機物を混和した土壌の硬化強度の経時変化
土壌の保水能および有効水分量、可給態リン酸(Bray2-P)含量ならびに交換性カリウム含量の区間差や経時変化は、各土壌とも類似した傾向を示したので、ここでは酸性細粒土壌のデータを掲げた。土壌の保水能は、有機物の施用によって明瞭に増大し、特にバガス区で増大が顕著で、保水能の増大効果は埋設後12ヶ月以降まで持続した(図表略)。また有効水分量(pF1.7とpF4.2の含水比の差、図6)も有機物施用に伴って顕著に増大し、その効果は保水能と同様に埋設後12ヶ月以降まで持続した。有機物種別に見ると、埋設後3ヶ月まではバガス区が他に比べ大きい傾向を示したが、それ以降は有機物種間の差が小さくなった。
可給態リン酸含量(図7)は経時変化は少なく、有機物種による差が大きかった。有機物種別に見ると、豚ふん堆肥>農協堆肥>牛ふん堆肥・牛ふんペレット堆肥>バガス、の順で、バガス区では無混和の土壌よりも含量が少なかった。交換性カリウム含量(図8)は経時的に減少し、3ヶ月目で混和時の約半分、12ヶ月目では1/3から1/4まで減少した。堆肥区の中では有機物種による含量の差は小さく、牛ふん堆肥区が若干大きい値を示した。バガス区の含量は堆肥区に比べて顕著に小さく、無混和の土壌と差がなかった。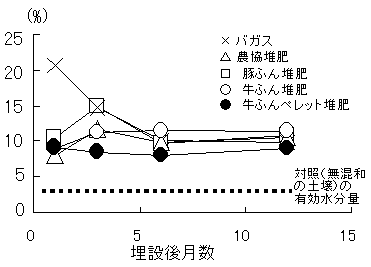
図6 有効水分量の経時変化
(pF1.7-4.2、酸性細粒土壌)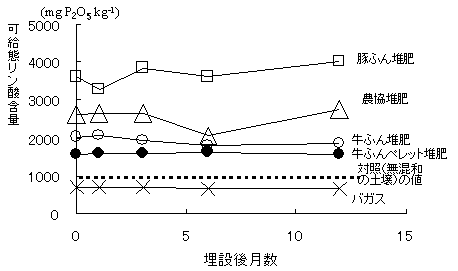
図7 可給態リン酸含量の経時変化
(Bray2-P、酸性細粒土壌)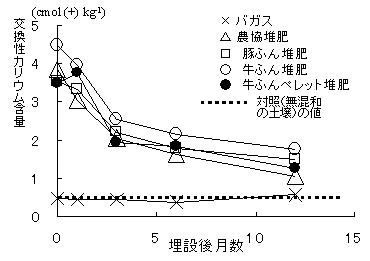
図8 交換性カリウム含量の経時変化
(酸性細粒土壌)
エ. 考察
- 村内の土壌の性質には、隣接した圃場間や一圃場内の地点間で、pHの大きく異なる土壌が分布するという特徴があった(図9,図10)。この特徴は、
- 母材(酸性の国頭マージの母材となる砂岩や礫層等、および微酸性~アルカリ性の島尻マージの母材となる石灰岩)が複雑に分布している2)、
- 傾斜地形であるため母材や土壌が崩落や侵食により移動しやすい、
- 土地改良事業により土壌が人為的な攪乱を受けている、および、
- 腐植が少なく化学的緩衝力に乏しい土壌であるため、酸性矯正や施肥に伴い土壌pHが容易に変動する、
このようなpHの差は、前述のように土壌の硬化強度に強く影響する。アルカリ性の土壌が強く硬化する原因については今後の解明が必要であるが、アルカリ条件下においては粒子表面の荷電などの物理化学的状態が、粘土粒子凝集体の構造などを介して硬化を促進し、またカルシウムイオンによる土壌の収縮促進(渡辺・小川3)はカルシウムイオンが土壌粒子間の水拘束力を増大させることをその原因としている)が更に硬化を助長していると推測される。硬化強度増大は、過剰または不必要な酸性矯正や施肥といった不適切な土壌管理によって、土壌のpHや交換性カルシウム量が過剰に上昇・増大した場合にも生じうる。本地域ではpHが大きく異なる土壌が複雑に混在することを念頭に置き、土壌の化学性を十分に把握して適切な土壌管理を行うことが、土壌の硬化促進を回避する上で重要である。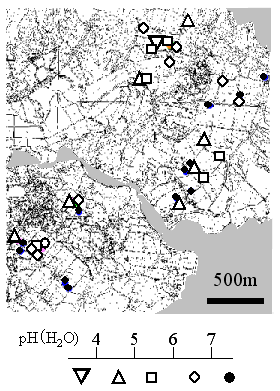
図9 宜野座村内各地の農家圃場の表層土のpH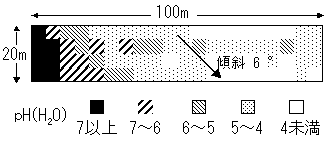
図10 ある圃場内の表土pHの分布 - 有機物の施用がマージ土壌の硬化強度および理化学性に及ぼす影響は、ガラス繊維ろ紙法による試験結果から次のようにまとめられる。
- 有機物の施用に伴い、とくに細粒質土壌で施用後6ヶ月前後に硬化強度の増大が起こりうる。有機物の種類としては、農協堆肥や豚ふん堆肥でこの傾向がやや強い。ただし施用後12ヶ月を経過すると硬化強度の増大は緩和される。
- 保水能や有効水分量は有機物施用により顕著に増大する。施用後数ヶ月については、特にバガスの効果が大きい。保水能や有効水分量の改善効果は12ヶ月以上持続するので、土壌物理性改善のためには、硬化を促進せず保水能等の向上を期待できる分解の進んだ(施用12ヶ月以降の)有機物を土壌中に増やすことが有効と考えられる。よって、長期的に有機物を継続施用することが土壌物理性改良の上で重要である。
- 給態リン酸、塩基など養分供給の面では、堆肥とくに豚ふん堆肥と農協堆肥の効果が大きく、逆にバガスは養分供給源としては期待できない。
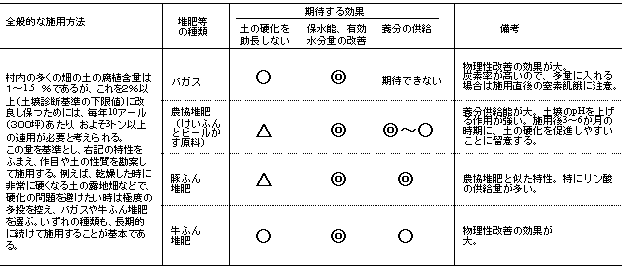
表3 目的別に見た有機物施用の指針
オ. 今後の課題
土壌の硬化機構、特に高pH条件下における硬化促進の機構や有機物施用後6ヶ月前後に見られる硬化強度増大の機構について解明する必要がある。
カ. 要約
宜野座村に分布するマージ土壌は乾燥時の著しい硬化など、土壌物理性の面で問題を有する。土壌物理性の改良には一般に有機物の施用が有効であるが、マージ土壌では有機物の施用により乾燥時の硬化が促進される場合がある。硬化促進を回避しつつ有機物施用による土壌物理性の改善を行うため、マージ土壌の乾燥に伴う硬化の特性および硬化に対する有機物の影響を調べ、以下のことを明らかにした。
- マージ土壌は細粒のものほど、またpHの高いものほど乾燥時に強く硬化する。人為的にpHを上昇させた場合も硬化が促進されることを、土壌管理の上で留意すべきである。
- マージ土壌に堆肥などの有機物を混和した場合、当初は硬化が緩和されるが、細粒質土壌では混和後6ヶ月前後に硬化の促進が生じる場合があり、特に農協堆肥(鶏ふん+ビールかす)や豚ふん堆肥でこの傾向が強い。硬化の促進は混和12ヶ月目ではほとんど見られなくなり、一方、保水能や有効水分量の改善効果は12ヶ月以降も持続した。このことから、有機物施用による土壌物理性改善には、長期的な連用により分解の進んだ状態の有機物を土壌中に増やすことが重要と考えられる。物理性の改善を主眼とする場合はバガスや牛ふん堆肥の施用が適切である。
キ. 文献
- 九州沖縄地域各県農試土壌保全事業担当研究室(1995):九州・沖縄地域における土壌の実態と変化 -定点調査結果からみた土壌の変遷- ,九州農政局生産流通部農産普及課編
- 沖縄総合事務局名護統計情報出張所編(1995):宜野座村の農業と漁業、p.3,沖縄農林水産統計情報協会
- 渡辺治郎・小川和夫(1984):重粘性土壌の易耕性要因に及ぼす石灰施用の影響、北海道農試研報、140,23~31
