持田秀之
ア. 研究目的
沖縄・南西諸島地域の主要畑土壌である国頭マ-ジ土壌は、強度の大きい降雨によって土壌侵食を受けやすく、大量の土砂が圃場外へ流出し、海洋汚染の原因となっている。これまでに、植生や資材による土壌表面の被覆が土砂流出量の低減に対して効果が高いことが指摘され1~3)、農家に受け入れ容易な方法として、斜面下端に被覆作物を栽培する方法4、5)や前作の刈り株や残さを利用してパインアップルを不耕起栽培する方法5)が提案されている。しかしながら、国頭マージ土壌において、植生被覆の程度や作付体系と土砂流出防止効果との関係を定量的に明らかにしたものは少ない。本課題では、降雨強度が自在に設定できる人工降雨実験装置を用いて、植生被覆の程度を変えた場合の土砂流出の推移や地下部による土砂流出防止効果を明らかにし、土砂流出防止のための植生の適正管理に関する基礎資料を得ようとした。また、緑肥のすき込みと作付体系が土砂流出との関係が深い保水性に与える影響について検討した。
イ. 研究方法
- 植生とその地下部が土砂流出防止効果に与える影響
国頭マ-ジ土壌を土壌枠(長さ150cm,幅50cm,深さ5cm)に充填し、裸地区と植生被覆区を設けた(写真1)。植生被覆区には、牧草のセタリアグラスとシグナルグラスを3段階の播種量(少:1.125g,中:2.25g,多:3.375g/枠)で散播した。播種後2~3ヶ月目に土壌枠を人工降雨実験棟に持ち込み、3%の角度を付けて40mm/時間の降雨を90分間降らせ、植生による土壌表面の被覆程度(以下被度と略す)と流出水量及び流出土量との関係を調査した。供試した人工降雨実験装置は、5~100mm/時間の降雨を微細管雨滴形成の雨滴自由落下方式によって発生させるもので、植物体に与えるエネルギーを自然降雨状況と同じ状態で、高さ約14mの位置から7.5cm×6cm間隔で雨を降らせることができる(写真2)。被覆作物として用いたセタリアグラスとシグナルグラスは、株型で雑草化しにくい特性を有している。施肥は、N-P2O5-K2O=10.5-10.5-8.4kg/10a相当の化成肥料を全面施用した。被度は、降雨試験開始前に土壌枠全体を写真撮影し、その画像をデジタルデータとしてコンピュータに取り込み、画像解析によって求めた。また、地下部単独の土砂流出防止効果をみるために、地上部を刈り取り、残った地下部に人工降雨を降らせて土砂流出量を計測した。 - 緑肥のすき込みと作付体系が土壌の保水性に与える影響
緑肥作物(クロタラリア、ギニアグラス)、バレイショ及びサトウキビの輪作試験において、各々の作付けが土壌の保水性に与える影響を調査した。各作物の栽植様式は、クロタラリア(C.juncea(ジュンシア)・C.spectabilis(スペクタ)・C.breviflora(ブレビ))とギニアグラス(品種ナツカゼ)は散播で、播種量は各々5~10kgと2kg /10aとした。バレイショ(品種デジマ)は畦間65cm、株間20cmの7.7株/m2、サトウキビ(品種F177)は、条間140cmで植え付けた。保水性は、各試験区の土壌におけるpF1.7とpF4.2の含水比の差を作物が利用できる有効水分として示した。その他の栽培管理については、慣行にしたがった。
ウ. 結果と考察
- 植生とその地下部が土砂流出防止効果に与える影響
植生被覆と表面流去水量及び土砂流出量との関係を調べたところ、セタリアグラスでは、表面流去水量は時間の経過とともに直線的に増加し、裸地に比べて播種量が多くなるほど流去水量が少なくなる傾向を示した(図1)。シグナルグラスでは、そうした傾向は明らかでなかった(図2)。単位容積当たりの土砂流出量の指標となる濁度は、セタリアグラスの播種量を多くした場合に低くなる傾向を示し、降雨開始20分後が最も高くその後緩やかに低下すること、裸地区との差は降雨開始後40分まで大きいことがわかった(図3)。シグナルグラスにおいても、播種量が多いと濁度は低く経過したが、裸地区との差は時間の経過と関係なく一定であった(図4)。この結果、積算土砂流出量の推移をみると、セタリアグラスの土砂流出量は被度が小さいシグナルグラスより少なく、降雨開始90分後における被度66.3%の流出量は裸地の半分以下に抑えられた(図5、6)。以上のことから、植生による土壌表面の被覆は表面流去水量を減少させるとともに、雨滴の衝撃をやわらげ降雨開始後40分までの濁度を抑制し土砂流出量を少なくするものと推察される。また、地下部による土砂流出防止効果を調べたところ、土砂流出量低減に対する地下部単独の影響は極めて小さく、土砂流出防止効果の大きい播種量多区でもその寄与度は約3%程度に留まった(表1)。このことは、2~3ヶ月程度の栽培期間では地下部によって土砂流出量は減少しないことを示しており、土砂流出効果を得るためにはさらなる根系の発達が必要であると考えられる。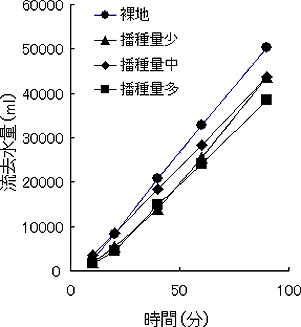
図1 表面流去水量の推移(セタリアグラス)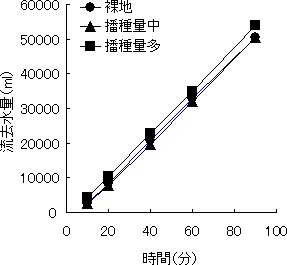
図2 表面流去水量の推移(シグナルグラス)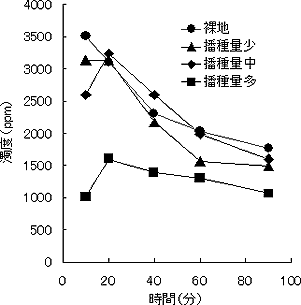
図3 植生帯の播種量と濁度の推移(セタリアグラス)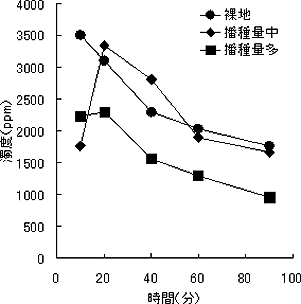
図4 植生の播種量と濁度の推移(シグナルグラス)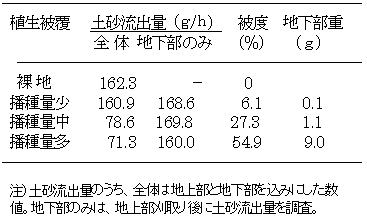
表1 土砂流出防止効果に与える地下部の影響 - 緑肥の種類や作付体系が土壌の保水性に与える影響
緑肥作物をすき込むと、土壌中の有機物が増加して団粒構造が発達し、土砂が流れにくくなることがわかっており、保水性はその一つの指標である。前作の緑肥作物や輪作体系が保水性に与える影響は小さかったが、緑肥作物では、ブレビ<スペクタ=ジュンシア=ギニアの傾向が認められすき込み量が多いほど保水性が改善することがわかった。また、輪作体系では1年2作と3年4作がほぼ同じで、2年3作が若干小さくなる傾向を示した(図7、8)。このことから、緑肥の種類や作付体系が土壌の保水性に与える影響は小さく、それらによって大幅に保水性を改善することは難しいと言える。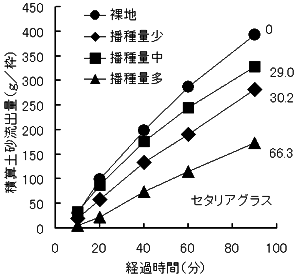
図5 積算土砂流出量の推移注)図中の数字は被度(%)を表す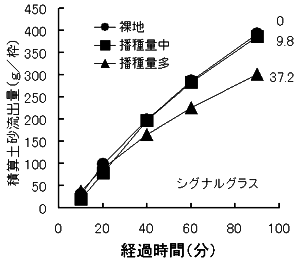
図6 積算土砂流出量の推移注)図中の数字は被度(%)を表す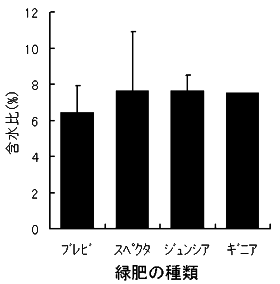
図7 緑肥の種類が保水性に与える影響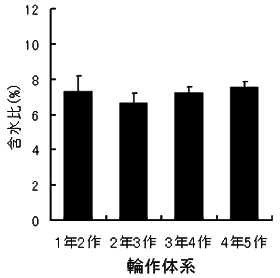
図8輪作体系が保水性に与える影響
注)1年2作:緑肥作物-バレイショ
2年3作:緑肥作物-バレイショ-サトウキビ1作
3年4作:緑肥作物-バレイショ-サトウキビ2作
4年5作:緑肥作物-バレイショ-サトウキビ3作
写真1 土壌枠

写真2 人工降雨実験棟
エ. 今後の問題点
植生の地下部による土砂流出防止効果については、永年牧草などを長期間生育させると根系が発達するため、根張りによって土砂流出が抑えられる効果も無視できなくなる可能性がある。今後、根系発達の程度と土砂流出防止効果との関係を検証していく必要がある。
オ. 要約
被度が高まるほど土砂流出量は少なく、降雨開始後40分までの濁度の差が被度によって大きく異なること、土砂流出防止に対する地下部の影響は地上部の被覆に比べて小さいこと、緑肥のすきこみや輪作によって大幅に保水性を高めることは難しいことがわかった。
カ. 文献
- 生駒泰基・須崎睦夫:国頭マ-ジ土壌での土壌表面被覆が土砂流出に及ぼす影響の解明(第1報)不織布マルチによる土砂流出防止効果.日作九支報.59.67~69.1993
- 生駒泰基・須崎睦夫・持田秀之:国頭マ-ジ土壌での土壌表面被覆が土砂流出に及ぼす影響の解明(第2報)不織布のマルチ方法および不織布と被覆作物との組合せによる土砂流出防止効果の検討.日作九支報.61.67~69.1995
- 生駒泰基・持田秀之・須崎睦夫:国頭マ-ジ土壌での土壌表面被覆が土砂流出に及ぼす影響の解明(第3報)綿屑シ-トと被覆作物との組み合わせによる土砂流出防止技術.日作九支報.63.73~75.1996
- 小林真・寺内方克・中野寛・江川宣伸:石垣島におけるパイナップル圃場の土壌保全を目的とした芝草類の畦間被覆作物としての利用技術芝草研究.26.65.1998
- 菅原和夫:石垣島のパイナップル畑における土壌浸食の発生実態と軽減対策.農業技術.52.294~298.1997
