持田秀之、渡辺輝夫、久保寺秀夫、松永俊朗
ア. 研究目的
南西諸島、沖縄地域における基軸畑作物のサトウキビは、その生育期間が1年から1年半と長く、しかも畦幅が130~140cmと広いことから、土地利用率が低い。そのため、1日当たりの家族労働報酬が甘しょの85%程度に留まる等収益性が低い。しかも、初期生育が遅く土壌表面が長期間露出するため、強度の大きい降雨に遭遇することにより圃場から大量の土砂が流出し、土壌生産力の低下や海洋汚染を招いている。そこで、土地利用型の冬作バレイショ、サトウキビ及び緑肥作物を輪作することによって土地利用率を高めるとともに、輪作の持つ病虫害抑制、雑草害低減などの有用機能を利用した冬作バレイショの持続的生産技術を定着させる必要がある。
沖縄本島北部における本土出荷のための冬作バレイショ生産の歴史は浅く、土壌病害を中心とする連作障害の発生はこれまで問題化していなかった。しかしながら、最近バレイショの連作が増加するとともに、青枯病、そうか病など土壌病害の発生が甚だしく、本島北部では産地の維持が難しくなっている。また、冬作バレイショを始め露地野菜の安定生産を目指すには、土壌中の有機物含量を高く維持するための有機物管理が極めて重要である。本課題では、新規野菜・花き導入のために開発した体系化技術について高収益複合営農システムのプロトタイプを構築するため、南西諸島、沖縄地域の基幹畑作物であるサトウキビ、バレイショ、緑肥作物クロタラリアを組み合わせた実証試験を沖縄本島北部の宜野座村において行い、冬作バレイショを主軸作物とした持続生産型高収益輪作体系の確立を図ることを目的とする。
イ. 研究方法
- 耕種概要
供試品種としては、バレイショはデジマとメイホウ、緑肥作物はクロタラリア(C.juncea(以下ジュンシアと略す)・C.spectabilis(以下スペクタと略す)・C.breviflora(ブレビと略す))とギニアグラス(品種ナツカゼ、以下ギニアと略す)、サトウキビはF177を用いた。バレイショ品種デジマは暖地における青果用の主力品種であるが青枯病に弱く、メイホウは青枯病に対する圃場抵抗性を有している。クロタラリアのうち、ジュンシアは生育速度が速く草丈が高い、スペクタは初期生育はジュンシアより劣るが生育は旺盛、ブレビは初期生育が遅いが倒伏しにくいなどの生育特性を有している。各作物の耕種概要は、表1に取りまとめた。
供試圃場は、沖縄県国頭郡宜野座村の松田地区の国頭マージ土壌畑を用いた。設定した作付体系は、緑肥作物ーバレイショ1年2作のバレイショ連作体系、緑肥作物ーバレイショーサトウキビ1作の2年3作体系、緑肥作物ーバレイショーサトウキビ2作の3年4作体系、緑肥作物ーバレイショーサトウキビ3作の4年5作体系のバレイショ輪作体系の4種類で、試験期間は1998年から2002年までの合計5年間である(表2)。バレイショ品種デジマと緑肥作物はすべての体系に組み入れ、メイホウはバレイショ連作となる1年2作体系にのみ導入した。表1以外の栽培管理については、沖縄本島北部における畑作物の栽培指針に準じて実施した。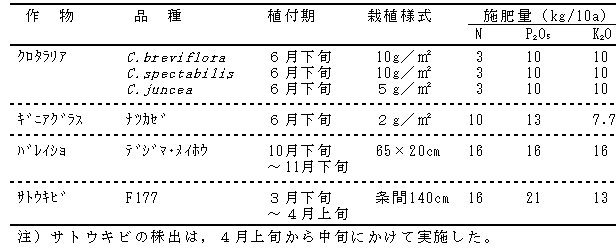
表1 各作物の耕種概要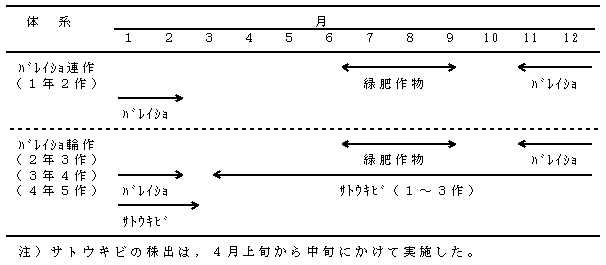
表2 作付体系の概要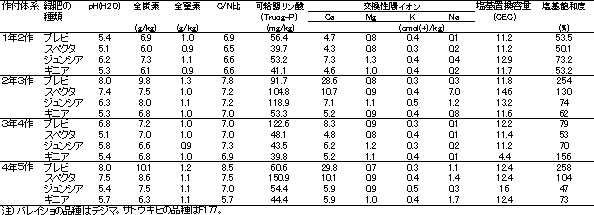
表3 現地試験開始時の土壌の化学性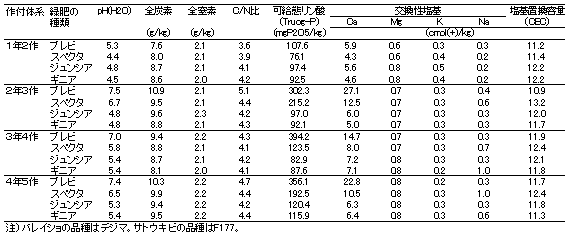
表4 現地試験終了時の土壌の化学性 - 調査
緑肥作物の調査は、播種後約90日後に1区4m2を2反復坪刈りし、地上部重、草丈などを調査し、その一部について乾物率を測定した。バレイショの収穫調査は、植付け後約100日目に1区3m2を2~3反復で収穫し、地上部重、上いも重(40g以上)、上いも数(40g以上)、乾物率、罹病塊茎率、澱粉価を調査した。病害調査は、現地圃場で頻度高く発生している青枯病、そうか病、粉状そうか病、塊茎えそ病を対象に実施した。サトウキビは3月下旬から4月上旬にかけて1区3m2の3反復で刈取り、原料茎重、Brixなどを調査した。土壌の理化学性の変化をみるため、バレイショ植付け前に土壌の三相分布を調査するとともに、作土から土壌を採取し、pH(H2O)、全窒素、全炭素、可給態リン酸、交換性塩基、CEC及び塩基飽和度を定法により測定した。また、ベルマン法により線虫を分離し、ネコブセンチュウとネグサレセンチュウを計数した。
ウ. 結果と考察
- 緑肥作物のすき込みと輪作が土壌環境に与える影響
緑肥作物の生育特性として草丈と地上部乾物重について述べる。草丈は、ブレビ<スペクタ<ジュンシアとなり、ジュンシアはギニアグラスとほぼ同様な値を示した(図1)。緑肥作物の地上部乾物重は、1年2作体系の連作区では、ブレビ<スペクタ<ジュンシア<ギニアとなり、マメ科のクロタラリアに比べてイネ科のギニアグラスのすきこみ量が多くなることがわかった。また、連作区は、クロタラリアのうちブレビ、スペクタにおいて雑草の発生量が多く、特にブレビでは雑草との競合が甚だしかった(図2)。一方、2年3作体系の輪作区では、スペクタのすきこみ量が最も多く、ジュンシア、ブレビ、ギニアの順となり、雑草量は連作区に比べて少なかった(図3)。
緑肥作物のすき込みが土壌の物理性に与える影響をみるために、三相分布を調べたところ、すき込み量が多いほど固相率が小さく気相率が大きくなり、ギニアグラスをすき込んだ場合には気相率が40%を超えた(図4)。液相率にはすきこみの影響はなく、固相率の低下が気相率を増加させた原因である。気相率の向上は、バレイショの塊茎肥大にとってギニアすき込み区の物理性が好適であることを示している。土壌化学性に対する緑肥すき込みの影響を1年2作の連作区と2年3作の輪作区でみると、連作区の可給態窒素は、ギニア<ブレビ<スペクタ<ジュンシアとなり、すきこみ量が多いギニアグラスでは、C/N比が大きいため少なくなったと推察される。また、連作<輪作の傾向が認められ、輪作区でもギニア跡の可給態窒素含量が最も少なかった(図5)。
5年間の緑肥のすき込みと輪作が土壌化学性に与える累積的な影響をみたのが、表3と表4である。この表によると、全窒素と全炭素はいずれの作付体系でも増加するが、全炭素に対して全窒素が増加する割合が高く、C/N比は小さくなった。特に、緑肥としてギニアを組み入れた場合にその傾向が認められた。また、pHは,試験開始時の値が高かったため苦土石灰による酸度矯正を特に実施しなかった。5年後の試験終了時には、可給態リン酸は増加しているが、pHは、試験開始時の圃場内の値にばらつきが認められるものの、1年2作や2年3作などサトウキビの作付頻度が少ない体系で低下する傾向がみられた。バレイショと緑肥を主体とした作付体系では土壌の酸性化が進むことから、定期的な酸度矯正が必要であると言える。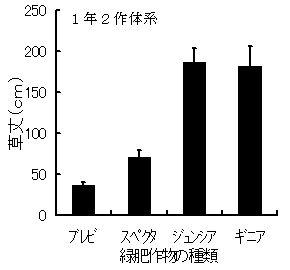
図1 緑肥作物の草丈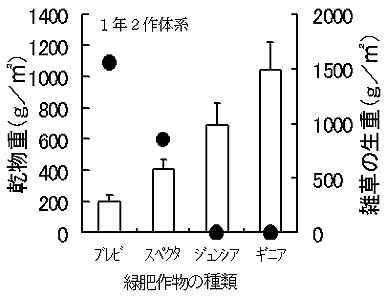
図2 緑肥作物のすき込み量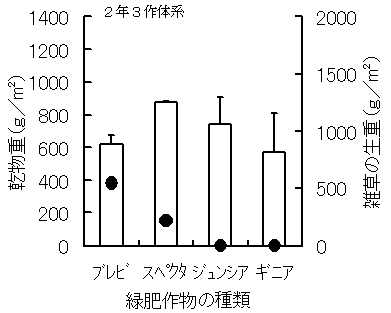
図3 緑肥作物のすき込み量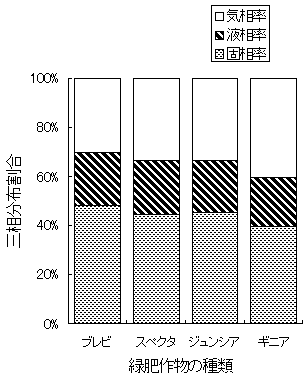
図4 緑肥すき込み後の三相分布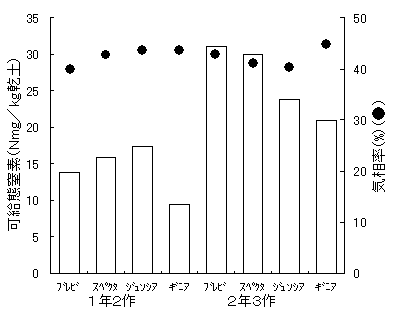
図5 緑肥すき込みと土壌の理化学性
注)緑肥作物のすき込み2ヶ月後に調査。 - 各種作付体系におけるバレイショの生育収量
地上部生育に対する緑肥すき込みの効果をみると、塊茎肥大始期(1月17日)の地上部生育には前作による明らかな差は認められなかったが、収穫期(2月9日)にはジュンシア>ブレビ=スペクタ>ギニアとなり、塊茎肥大始期以降に地上部の差が現れた(図6)。2000年度におけるデジマの上イモ収量は、緑肥作物-バレイショの1年2作区では、すき込み量の最も多いギニア跡と少ないブレビ跡において低収で、クロタラリアの中ですき込み量が最も多かったジュンシア跡で多収となった(図7)。デジマでは青枯病の罹病塊茎率が高く収量に影響していると考えられるため、抵抗性のメイホウについても検討した。この結果、メイホウでは、ブレビ跡=スペクタ跡<ギニア跡<ジュンシア跡の順に多くなり、すき込み量の最も多いギニアグラスはジュンシアに及ばなかった(図8)。これは、すき込み有機物のC/N比が影響しているとみられ、ギニア跡では同比が高く、土壌中の有機態窒素の有効化が抑えられたものと推察される。緑肥のすき込みがバレイショ収量に与える影響は、沖縄本島においてブレビ跡で堆肥施用に匹敵する増収効果を認めているが1)、本試験ではすき込み量に比例してスペクタ跡、ジュンシア跡の方が増収効果が高いこと、イネ科のギニア跡では作物体の分解が進まず低収に留まること2)が示された。また、2002年度における2年3作、3年4作、4年5作などサトウキビを組み入れた輪作区では、クロタラリアの中ですき込み量が多かったスペクタやジュンシアの区でバレイショ収量が増加する傾向を示し、上いも数より1個重の増加がそうした増収に寄与していることがわかった(図9)。澱粉価は、1年2作のバレイショ連作で2000年度、2002年度ともにジュンシア跡で高くなる傾向を示したが、2年3作、3年4作、4年5作など輪作区では一定の傾向が認められなかった。ギニア跡では、連作、輪作に関わらず低くなる傾向を示した(図10)。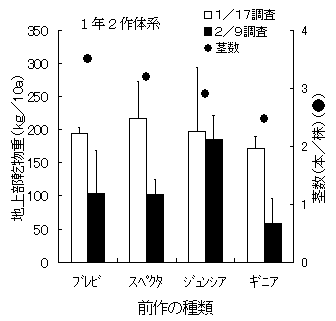
図6 前作が地上部生育に与える影響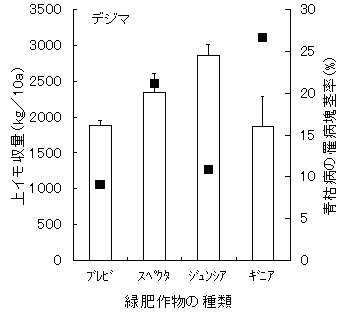
図7 緑肥作物の種類とバレイショ収量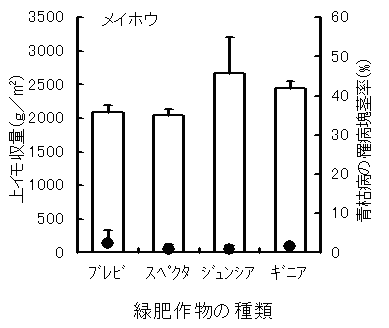
図8 緑肥作物の種類とバレイショ収量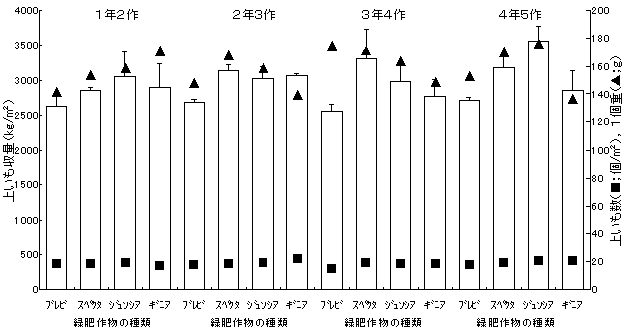
図9 緑肥作物の種類と作付体系がバレイショ収量に与える影響(品種デジマ)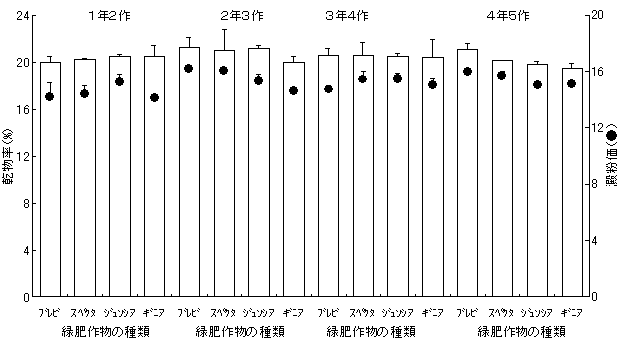
図10 塊茎の乾物率と澱粉価 - 各種作付体系におけるバレイショの病虫害
青枯病は、暖地バレイショの安定生産にとって大きな阻害要因であり、上いも収量と罹病塊茎率との間には有意な負の相関が認められた(図11)。主産地の長崎県でも耕種的に被害を回避することは難しく、気温が高い時期の早植えを避ける3)、あるいは短期輪作を行うことが耕種的対策となっている4)。ところが、沖縄本島北部地域では、冬季でも気温が比較的高く湿潤であるため青枯病が多発し、バレイショの安定生産を脅かしている(表5)。1年2作のバレイショ連作では、青枯病に抵抗性のメイホウはデジマより青枯病とそうか病の罹病塊茎率が小さく、特に減収の主要因である青枯病の罹病塊茎はほとんど見られない(表6)。一方、デジマでは、クロタラリア跡で輪作期間が長くなるほど青枯病、そうか病、粉状そうか病が減少する傾向を示し、4年5作の輪作では、メイホウと同程度の水準まで青枯病の発生が抑えられることがわかった(表7)。メイホウの連作では、粉状そうか病が連作のデジマと同様に多発しており、輪作による病害発生の抑制は、沖縄本島地域におけるバレイショの土壌病害の回避に一定の効果を持つものと推察される。一方、ギニア跡では輪作でも青枯病が多発する場合があり、病害抑制のためには前作の緑肥の選択も重要と考えられる。また、線虫密度は、試験開始時と試験終了時に調査したが、乾土20g当たりネコブセンチュウは0頭、ネグサレセンチュウは10頭以下に留まり、線虫害も生じなかった。線虫による加害は病害を助長することが知られているが、こうした結果は、線虫害が土壌病害に影響を及ぼしていないことを示すものと言える。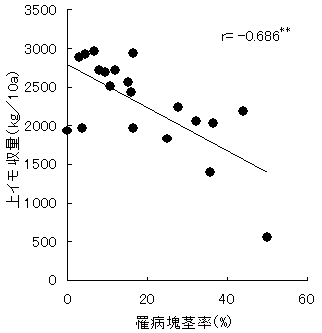
図11 青枯病の罹病塊茎率とバレイショ収量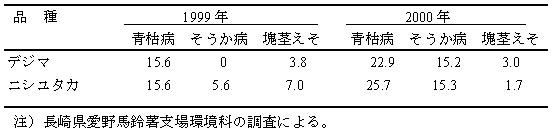
表5 冬作バレイショにおける病害の発生程度(単位%)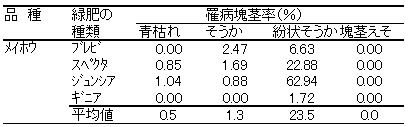
表6 緑肥の種類と罹病塊茎率との関係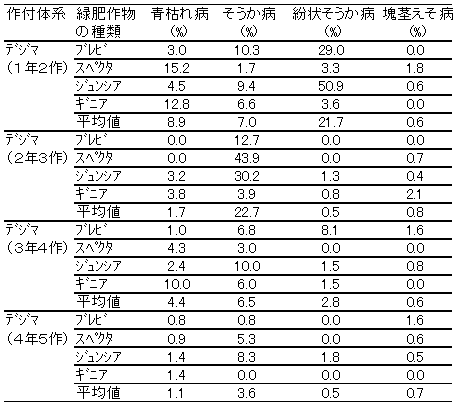
表7 緑肥の種類と罹病塊茎率との関係 - サトウキビの生育収量
サトウキビについては、栽培体系が異なるため同一年の収量比較はできないが、株出2年目が若干低収であることを除けば、新植、株出1年ともに、沖縄本島北部地域の平均的な収量やBrixと遜色のない値を示した(表8)。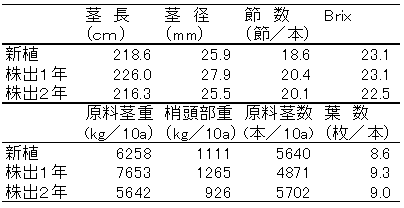
表8 サトウキビの生育収量 (2001年度)
エ. 今後の課題
緑肥のすき込みや作付体系の影響は累積的効果を持つので、冬作バレイショの持続的生産を図るにはさらに年次を重ねて長期試験を行う必要がある。また、青枯病の抑制のためには抵抗性品種の選択や育成も重要であり、そうした対策と組み合わせて土壌病害の防止に努める必要がある。
オ. 要約
- 緑肥では、気相率の向上にはすき込み量が多いギニアグラスが優れていること、可給態窒素の向上にはジュンシアのすき込みが有効であり後作バレイショの収量、澱粉価の増加に結びつくことがわかった。サトウキビとの輪作は、可給態窒素を増加させバレイショが多収となるとともに、pHの低下を生じないなど土壌の化学性において有益であることがわかった。
- 連作障害の主要因の土壌病害では、サトウキビと長期輪作を組むことによって青枯病の被害を抵抗性品種と同程度に抑制できること、青枯病以外の病害についても輪作は抑制効果を持つことがわかった。また、ギニア跡のように輪作でも青枯病が多発する場合があり、病害抑制のためには前作の緑肥の選択も重要であることが示唆された。
カ. 文献
- 持田秀之:センチュウ対抗植物の利用-クロタラリア-.農業技術体系(土壌施肥編)第5-(1)号、226の15の2~5.1999
- 茶谷正孝・田淵尚一・小村国則:緑肥作物の導入によるバレイショ連作畑の地力維持.九農研機構55,48.1993
- 片山克己・木村貞夫:ジャガイモ青枯病の発生生態と防除に関する研究第2報各種防除法とその体系化.長崎総農林研報15,29~57.1987
- 後藤孝雄・泉省吾・片山克己・西山登・鶴内孝之:短期輪作によるジャガイモ青枯病の防除.九農研機構55,81.1993
- 持田秀之:沖縄本島における冬作バレイショ栽培.平成12年度いも類研究会.資料集.2000.
キ. 謝辞
本課題は、沖縄県農業試験場名護支場、長崎県総合農林試験場、現地農家など多くの方々の協力によって実施されたものである、沖縄県農業試験場名護支場には、各作物の播種植付け、中間調査、収穫調査など圃場試験全般にわたり多大な協力を賜った。長崎県総合農林試験場愛野馬鈴薯支場には、バレイショ品種の選定、罹病塊茎の調査などに協力と指導を頂いた。現地農家の嘉手納良一氏には、試験研究の内容をよく理解し行き届いた作物管理をして頂いた。ここに記して謝意を表する。
