相原貴之
ア. 研究目的
さとうきび生産及び糖業は今後も沖縄県の主要産業として重要であるが、さとうきびの価格低下と機械化を機軸とした集積・大規模化はますます進展していくものと予想される。そのとき、過剰となった農業労働力は、本島中南部では他産業への就業機会があるが、それ以外の地域ではやはり農業を中心に位置づけていかざるを得ない。その意味で、集約作物導入による産地形成の問題は重要になってくる。
本課題では、高収益作物として沖縄での栽培試験が進められている作物からイチゴ「さちのか」を対象に、実証栽培を行っている農家、役場、量販店、沖縄県農業試験場園芸支場野菜研究室等で聴き取り調査等を行い、沖縄におけるイチゴ作導入のために求められる流通システムを明らかにする。
イ. 研究方法
- 沖縄県におけるイチゴ流通の実態把握
卸売市場、量販店(生協を含む)の聴き取り調査及び数量・価格・品質(等階級)データ、家計調査年報データの分析等を通じて、沖縄県におけるイチゴ流通の実態を把握する。 - 生産規模ごとに求められる週通システムの提示
沖縄県にイチゴ生産が導入された場合を想定し、生産規模ごとの流通販売方策を提示する。 - 導入初期段階のイチゴ生産・流通・販売システムの策定
実証栽培農家、直売所等の聴き取り調査を中心に、特にイチゴ生産導入初期段階で求められる生産・流通・販売システムを策定する。
ウ. 結果
- 沖縄県におけるイチゴ流通の実態
県内の大手量販店3社(生協1社、スーパー2社)のイチゴ取扱量は、月によっては沖縄県中央卸売市場の入荷量に匹敵する。しかし、市場経由率は低く、福岡県、熊本県等の九州の流通業者が主に航空便で流通センターに納入している。卸売市場を経由しているものは、県内の仲卸業者が納入している。小売価格は仕入コストとあまり連動せずに、498・398円が中心になっている。価格高騰時には小売価格は580円や598円に設定されるが、それ以上は消費者が購買しない価格帯になるため、原価割れで販売することもある。また、県内中央卸売市場の入荷量は年間約400t(1パック=300gとして、以下同様)であり、入荷量は3月、単価は12月がピークになっている。規格は2Lが中心で、価格形成はLは2Lから10円程度、Mは40~50円程度下がる。SはMからさらに50円程度低くなる。
沖縄県の生食用イチゴの市場規模は、卸売市場の取扱量400tを基準に、宮古・八重山地方や離島地域に送られる荷のほとんどが本島(卸売市場または量販店の流通センター)を経由していること、大手量販店の聴取調査から推定すると量販店の市場外流通量は150~200tになること、家計調査年報のイチゴの一世帯当たり購入量から沖縄県の消費量を推計すると560~630tになることから、600t程度であると推定できる。また、ケーキ、菓子等の加工用は、200t程度であるといわれている。
沖縄県内に流通しているイチゴはほぼ100%県外からの移入品であり、航空便での輸送で最短収穫2日目販売、通常3日目販売になる。船便での輸送は3~5日目販売になる。量販店の多くは航空便を利用しているが、航空便では空港及び飛行機内でコールドチェーンが途切れるとともに、頻繁な荷物の積み替えがあるため荷傷みする。そのため、店舗での販売日数は1日または2日となっており、棚持ちの悪い商品になっている。その点、県内産であれば、当日または2日目販売が可能になり、県外産並の味と外観が確保できれば、鮮度の良い県内産は、量販店にとって魅力ある商材になり得る。 - 生産規模ごとのイチゴ流通システム
実証試験農家からの聴き取り調査の結果、家族2人雇用なしでの上限と言われる30a規模はもちろんのこと、10a規模もすぐに現れることは考えにくく、できるだけ小さな規模(2~2.5a程度)の規模からの導入を目指す必要があることが明らかになった。
この結果に従い、生産規模を2.5a農家/10a農家/30a農家/3ha産地(30a農家10戸)に分類し、販売形態、流通システムを提示した(表1)。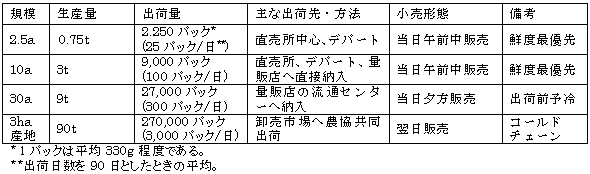
表1 想定されるイチゴの生産規模別流通形態の概要 - 導入初期段階のイチゴ生産・流通・販売システム
2.5aが1戸程度という段階では、例えば宜野座村「未来ぎのざ」のような直売所で鮮度を最優先した販売が有効であると考えられた。収穫最盛期になり収穫量が増えてくると、量販店へ直接納入することも可能になる。実際、農家からの直接納入制度が整備されている量販店もある。
また、一定の品質が確保できればデパートでの販売が有効ではないかと思われたが、例えば那覇市に出荷する場合、宜野座産他作物との混載出荷で運賃が節約できたとしても、当日朝の収穫・出荷では時間的にきついことが明らかになった。
エ. 考察
- 「さちのか」の市場性
「さちのか」は、量販店によっては「とよのか」等他の品種よりパック当たり100円程度高く販売されており(いずれも九州産、2001年12月時点)、市場性が高いと判断される(表2)。味や香りだけでなく、果実硬度が高いため荷傷みしにくいことも評価されていると思われる。
また、「さちのか」は現在のイチゴ品種の中では最も沖縄での栽培に適しているとされている。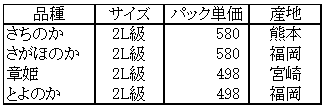
表2 ある量販店おけるイチゴ販売価格 - 鮮度をセールスポイントとするための収穫・出荷・販売方式
以下では、導入初期段階の規模と想定される2~2.5aを前提に考察する。
県産イチゴの最大のセールスポイントは鮮度の良さにある。従って、本土産イチゴとの差別化のため、鮮度を最優先とし、特に小規模生産段階においては収穫日の午前中に販売開始できるような収穫・調製・出荷方式が必要である。また、この規模で予冷庫を導入するのは経費的に不可能であり、この面からも収穫後ただちに調製・出荷するよう務めなければならない。図1は2003年1月25日の収穫直後及び直売所に並べられたイチゴの状況である。収穫からディスプレイまで約2.5時間であった。
図1 収穫直後及び販売時のイチゴ
鮮度最優先のため、生産地近くの直売所等での販売を中心とし、さらに、収穫日・時刻を表示する等新鮮さをアピールすることが重要である。この方法として、パックのフィルムに図2のようなシールを貼ることとしている(通常は「今朝7時収穫」になる)。
図2 収穫時刻表示シール
未来ぎのざでは屋根付きではあるものの屋外売り場に陳列されるので、特に3月下旬以降等気温が高くなる時期は、例えば上面が透明蓋になっている保冷ケースでの販売等を実施する等販売時間中の鮮度保持にも努めることが重要である。 - 出荷量の調整
直売所での販売で極力避けなければならないことは売れ残り、絶対行ってはならないことは前日収穫品の販売である。従って、収穫当日販売可能な量だけを出荷し万一売れ残りが発生した場合には、必ず翌日の販売開始までに回収するとともに出荷量の調整が必要になる。このため、1戸の農家が出荷する直売所等は1ヶ所程度とすべきである。幸い沖縄県には、事前の契約により農家からの直接買い入れを行っている量販店があるので、直売所分とこの量販店分を振り分けて出荷することが可能である。宜野座村であれば名護市の店舗に農家が搬入する。 - 導入規模
鮮度とともに果実品質も重要な要素である。沖縄産のイチゴは端緒を開こうとしているときであり、報道等によるイメージ過熱の感もあるものの、まだ県内での知名度は低い。最初の段階で本土産に大きく劣る品質のイチゴを出荷すると、その後の販売に大きな打撃になるであろう。
すでに形成されているイチゴ産地もなく栽培技術習得環境にも制約がある。従って最初からハウス設置等の投資を行い、専作的に栽培することははリスクが高い。
このため、野菜・花き等用のハウスを所持している農家が、なるべく小さな規模(2~2.5a)から導入することが適当である。合わせて、先発農家が栽培技術を習得しある程度の産地が形成されるまでは、例えば九州沖縄農業研究センター野菜花き部あるいは沖縄県農業試験場園芸支場等の公的機関が技術指導に赴くか希望者を技術講習生等として受け入れるという支援体制が必要なる。
オ. 今後の課題
- 苗供給に関する課題
イチゴの育苗は長期間にわたる上、短日夜冷処理作業等の理由により、当面、苗は経営外部から購入しなければならない。このときミカンキイロアザミウマの沖縄県への侵入を防ぐため、県内で苗が供給できる体制づくりが必須である。沖縄県農業試験場園芸支場と沖縄県経済連の野菜・花き種苗の生産販売を行っている協同会社で共同研究が開始されるという情報があり、これが実施されれば第一歩を踏み出したといえる。その場合の問題は販売価格である。現在販売されている最も安い苗は単価80円程度(送料別)であり、沖縄県農業試験場の自家生産苗コスト試算でも単価81.2円となっている。
他方、例えば宜野座村では種苗費の25%を補助する制度があり、これがイチゴ苗へも適用されること等も望まれる。 - 経営評価に関する課題
現在は、収穫量のピークを軽減するため短日夜冷処理苗(12月から収穫可能だが、一番果(頂果房につく果実)二番果(第一次えき果房につく果実)の間があく)と自然分花苗(1月以降の収穫だが、とぎれることなく収穫できる)を組み合わせている。しかし、短日夜冷処理のコストや12月の品質・価格を考慮した最適な作型組合せを再検討しなければならない。
少量生産段階では、鮮度に優る県産イチゴは本土産より高値で販売可能である。しかし将来産地化が進むと高値販売という有利性は次第になくなってくるであろう。従って本土産と同じ価格水準での収益性評価も行っておく必要がある。 - 品質安定に関する課題
気温が上昇してくる3月以降糖度が上がらなくなることが多い。これは気温が高くなると早く熟するので、酸抜け及び糖度上昇のための日数が少なくなるためであるが、栽培技術あるいは新品種育成等で改善できないものか。現状では3月の販売時に理由及びコンデンスミルク等と組み合わせて食する方法の説明を掲示することが求められる。
さらに、今シーズンは味が薄い果実が発生している。沖縄県農業試験場園芸支場によると原因は不明とのことであるが、購買者にとって酸味以上に大きなマイナス評価となるので、早急な解決が必要である。
カ. 要約
沖縄県農家がイチゴ「さちのか」の栽培を始める場合、栽培技術習得環境の制約等のため、最初からハウス設置等の投資を行い専作的に栽培することははリスクが高い。このため、野菜・花き等用のハウスを所持している農家が、なるべく小さな規模(2~2.5a)から導入することが適当である。また、この規模では、鮮度を最優先することによって本土産イチゴとの差別化を図ることが重要である。このため、生産地近くの直売所を主な出荷先とし、当日朝収穫午前中販売開始ができるような収穫・調製・販売システムを組まなければならない。直売所へは当日販売可能分だけを出荷し、万一売れ残った商品は翌日までに必ず回収することが必要である。収穫量が多いときは、直売所分と農家からの直接搬入を認めている量販店分に振り分けることも考える。
イチゴ生産普及のためには、県産苗供給体制の整備が必須である。ミカンキイロアザミウマの侵入を防ぐため、県外からの苗購入は絶対に行ってはならない。
沖縄県に小規模段階のイチゴ生産・販売のイメージを図3に示す。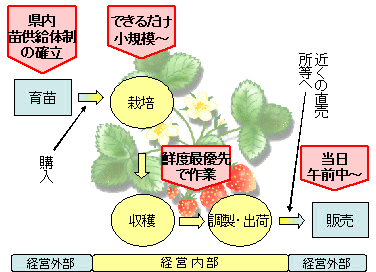
図3 導入初期段階におけるイチゴ生産・販売イメージ
キ. 文献
- 相原貴之・河野恵伸(2001):沖縄県における高収益集約作物導入のための流通システムの解明、九州農村生活研究会個別研究報告
- 相原貴之(2003):小規模生産段階のイチゴ流通」、新規野菜・花き栽培技術マニュアル
