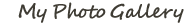研究職 (試験区分:工学(機械系))
2020年度採用
北海道農業研究センター
寒地畑作研究領域スマート畑作グループ
Y.M. 東北大学工学部(学士)
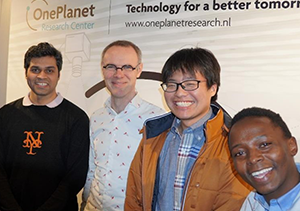
北海道のデータ駆動型農業の研究
北海道の大規模な畑作の体系の中で圃場のセンシングシステムの開発をしています。北海道に赴任して驚きましたが、既にトラクタの自動操舵システムや衛星画像データなどを農家の方が購入して活用しており、データ駆動型農業の最先端を走っている地域と言えます。しかし、この北海道にも労働者不足やフードロス、圃場内収量の極端なバラツキ等の課題が存在します。私は収穫適期の予測や収量のバラツキの原因を推定に役立つデータを取得するために、ドローンを使った撮影に加えて収穫機やトラクタによる新たなセンシング方法を研究開発しています。特に私の所属する芽室拠点では北海道の栽培体系に合わせて小麦、バレイショ、テンサイ、ソバ、タマネギやキャベツなどを栽培しているので、試作したシステムを様々な対象で試験することができます。
仕事をしていて、一番嬉しかったこと
協力してくださる農家の方の圃場で開発したシステムが上手く稼働したときは、緊張から解放された安心感と充実感で一杯になります。入構してから2年目の際には、バレイショの収穫に適切な地温になる日時を予測するモデルの検証のために、数地域のバレイショ農家の畑において、自動で収穫時の地温と位置情報を紐づけて記録し、マップ化するという課題に取り組みました。現地でシステムを稼働させる際には、工場のような安定した稼働環境ではないので不安もありましたが、配線や現場に詳しい先輩方が一緒にプロジェクトを進めてくださいました。上司や技術支援部の方が手取り足取り配線方法を教えてくださったので、3年目には1人で現地に赴くこともありましたが無事に配線ができています。
農研機構を選んだ理由
私は学生時代に深層学習を使った画像の拡大について研究していました。卒業後は学生時代に学んだ知識を活かしつつ、現場で実際にシステムを開発する応用研究をしたいと考えていました。キャベツの自動収穫機などの開発した自動制御システムを全国各地の圃場で試験できる農研機構は非常に魅力的でした。現在は自動運転や制御の課題は担当していませんが、その認識は変わらず、思いついたアイデアを直ぐに圃場で試験することができる環境だと思います。また、入構後に実感したことになりますが、グローバルな活動についても積極的な組織だと思います。研究グループ内でも英語で話す機会があり、国際学会はもちろんのこと海外の大学との共同研究や国際標準化活動に若手が取り組める機会があるのは農研機構の魅力だと思います。
現在、就職活動をしている学生にアドバイス
農研機構についていえばインターンシップがベストだと思います。しかし、それに限らず学会やホームページの問い合わせなどを使って、是非、興味のある研究グループの者と一度コンタクトを取ってみてください。きっと就職する上で気になる質問に親身に答えてくれます。農研機構以外の企業や機関の方にもコンタクトを取った後、その数ある候補の中から選んでいただけましたら幸いです。お待ちしております。