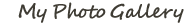研究職 (試験区分:農業科学)
2022年度採用
植物防疫研究部門
作物病害虫防除研究領域病害虫防除支援技術グループ
H.S. 東京大学大学院農学生命科学研究科(修士)
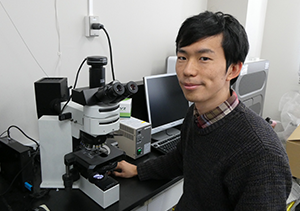
現地と連携しながら植物病害の防除に取り組む
植物病理を研究するグループに所属していて、サツマイモ基腐病の研究を行っています。サツマイモ基腐病は5年ほど前に日本に侵入した新病害で、サツマイモの育苗から収穫後までのあらゆる生育段階で感染するため、総合的な防除対策が求められています。グループ全体で研究を分担して進めるなかで、私はとりわけ病原菌の感染生理を担当しており、まだ研究途上のこの病原菌がどのような生育特性をもっているのか調べています。普段は茨城県つくば市で勤務していますが、発生地である九州南部には年に数回出張に行き、九州沖縄農業研究センターの担当者と研究の情報共有をしたり、発病状況を見学させてもらったりしています。
仕事をしていて、一番嬉しかったこと
学生時代にやっていた実験手法を使うことで、現在オリジナリティーのある実験をできていることです。大学院での研究内容はシロイヌナズナを使った栄養欠乏に関する研究で、今の研究と植物種も研究分野も違います。しかし、研究する上での個々の実験手法には共通点があり、これまでの知識を活かして現在の研究を発展的に進められています。例えば、学生時代は組み換え体を使ったGFPの蛍光観察をよく行っていましたが、そのときに学んだ顕微鏡観察の技術が現在の病原菌の観察にも役立っています。農研機構では研究課題ごとの大まかな目標は決まっていますが、細かなアプローチは研究者個人の裁量によるところが大きいです。たとえ異なる分野でも、自分なりの着眼点に基づいて研究を進められることは自信につながっています。
農研機構を選んだ理由
私は修士に進学するときに研究テーマを変えたのですが、その際に1つの分野を深く研究するよりも複数の分野を広く研究したいと思うようになりました。修士から博士にはそのまま進学しましたが、新しい研究分野への思いが強まり、自身の研究テーマが一段落した時期に就職先を探していました。農研機構は農業分野の研究を総合的に行っていて、幅広い研究分野に触れる機会が多い場所です。また、公的な研究機関として実用的な研究を進めるため、大学では感じづらかった現場の感覚にも触れられるだろうと考えました。そういった動機で農研機構を受け、縁があって入社することになりました。実際、職場では若手職員の集まりを通して他の研究分野を知ることができますし、現場を考えながら研究計画を立てることが多くなりました。
現在、就職活動をしている学生にアドバイス
私自身の就活を振り返ってみると、就活自体の情報収集や知り合いの動向よりも、自分のやりたいことや得意不得意をベースに活動していた印象があります。楽観的ではありますが、まわりの様子を見つつも、自分がここに就職したらこういう仕事ができそうだ、こんな生活がありそうだというイメージを大事にしてほしいと思います。皆さんにとって納得のいく就活になりますように。