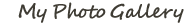研究職 (試験区分:農業科学)
2022年度採用
農業環境研究部門
気候変動緩和策研究領域革新的循環機能開発グループ
T.M. 立命館大学大学院生命科学研究科(修士)

微生物のはたらきを利用して農地から発生する温室効果ガスを削減する
ダイズ根粒から発生するN2O(一酸化二窒素)削減技術のポットスケール評価を行っています。ダイズは、土中の根粒菌と共生し根粒を形成しますが、収穫期になると老化した根粒の崩壊過程でCO2の約300倍もの温室効果をもつN2Oが発生します。一部の根粒菌はN2OをN2に還元する酵素をもつため、それら根粒菌を利用したN2O削減技術の確立を目指しています。
無色透明なガスをサンプリングする際、本当に採取できているのか今でも不思議に思いますが、人の目に見えないものを測定し、定量的に評価することに面白味を感じます。そして、目には見えないからこそ、データを通じて第三者に説明する重要性も強く意識するようになりました。博士号取得もこれからの駆け出しの身ですが、気候変動対策の一端を担えることに気が引き締まる思いです。
仕事をしていて、一番嬉しかったこと
農研機構に入構してからは、視野の拡がりを実感する連続で、そんな時、少しでも成長できているかなと嬉しく思います。たとえば、思うような試験結果ではなかったとき、少し落ち込みますが、考察のために論文や専門書を読んでいくうちに、次はこうしてみようと新しいアイデアが生まれます。上司や先輩の方と研究計画についてお話するときには、興味をただ追究するだけでなく、現場への普及・還元しやすさを軸とした「出口」を意識された意見をいただきます。学生の頃にはなかった国研ならではの視点が得られ、これまでの見方が実際に変わった経験も多くあります。自分で視野を拡げることはなかなか難しいので、「農業」という一つのキーワードを中心に、多様な経歴を持った方々とつながりができる農研機構で働けることにも喜びを感じています。
農研機構を選んだ理由
学生時代、中山間地域での課外活動に取り組む中で、激しい過疎化・高齢化に伴う地域の生産基盤の弱体化や自然環境の荒廃などに対して問題意識を持つようになりました。同時に、大学院では研究成果が実際の農地で活かされているのを目にして、社会実装に向けた研究開発にも興味を持つようになり、地域や農業現場の課題解決に取り組んでいる農研機構に研究職員としての入構を志しました。研究という仕事は自分に向いていないと勝手に決めつけていた頃もありましたが、試料分析やデスクワーク、屋外でのサンプリング、調査など、想像以上に多岐にわたる農研機構での仕事は、非常に刺激的で楽しく仕事に取り組めています。また将来的には、研究推進や広報などの業務機会もあり、さまざまな角度から農業研究に関わることができると思ったのも決め手の一つです。
現在、就職活動をしている学生にアドバイス
私は農研機構が第一志望でしたが、出身大学OBの方がおられず、コロナ禍もあり説明会はウェブ開催のみだったので、情報収集に難航しました。その為思い切って、採用担当の方に何度も問い合わせたり、他大学の友人に頼み込んでなんとか職員の方につないでもらったりもしました。直接お話を伺えたことで、機構で働くビジョンを明確にでき、より強い意志と自信をもって選考に臨むことができたと思います。ぜひできるだけ多くの方と接点をもって、志望動機をブラッシュアップしてください。