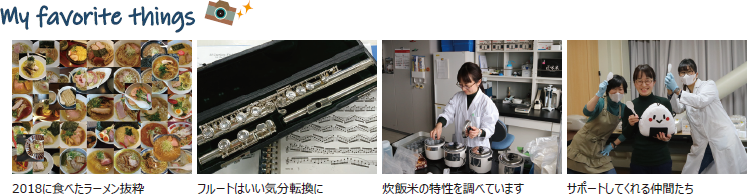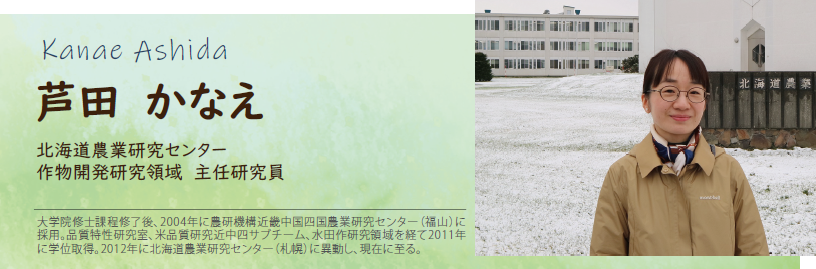
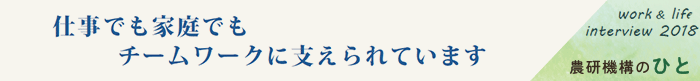
食べることが大好き、実験が大好き
高校の授業でニンジンの組織を取って増やして個体まで再生する組織培養をしました。その時、一つの細胞からまた食べ物になるなんてすごいな!と単純に感動して、それで農学部に行くことにしました。食べることが大好きなので(笑)。大学の実験が好きだったので研究をもう少ししたいと思い、修士課程に進学しました。将来のことを考えた時、大学の指導教官から「公務員になって(当時は奨学金をもらっていたので)お給料をもらいながら研究してはどうか」と農研機構を薦められました。その後、公務員試験を受けて晴れて採用となりました。
大苦戦の採用1年目
近畿中国四国農業研究センター(現 西日本農業研究センター)に採用されましたが、正直1年目が一番しんどかったです。大学の時にやっていた研究とは全く違うところに来て、お米のことを全然わからなくても研究テーマを自分で探さないといけなくて。研究室に配属されると、室長から「はい、これ読んで勉強して」って「RICE」っていうぶ厚い英語の本をボーンと渡されました。その本は今でも持っています。育種や栽培の研究室に行き、そこでお米について教わりました。すると今度は「田んぼを自分で作りなさい」と言われて、困って業務科へ聞きに行きました。でも「芦田さんに言われた通りにやるよ」と言われてしまって(笑)。それでまた育種や栽培の部屋に聞きに行って...という感じに、所内の部屋をあちこち訪ねていました。誰にも聞けなかったら煮詰まってイヤになっていたんだろうなと思います。
手探りの2年間を経て論文執筆
研究テーマが見つかったのは、突然変異育種の研究者から「このお米はタンパク質の組成が変わっているんだけど、他は分からないので調べてみないか」と言われたのがきっかけでした。タンパク質の組成が変わったお米について、澱粉やアミノ酸などに影響がないか調べたり、タンパク質の構造がどうなっているか電子顕微鏡で調べたりしました。結果を室長に報告したところ、「じゃあそれを論文にしなさい」と論文の書き方を教えてくれました。その論文が始まりで、他にも粉質変異といって粒の中が粉状になるお米を米粉パンに使えないか調べたりしていくつか論文を書き、学位を取りました。採用から論文を書くまでの2年間はよく分からない!という手探り状態でしたね。でも論文が出た時は達成感があったし、やっぱりうれしかったです。
お米の新しい可能性を
高アミロース米「北瑞穂」の今までにない使い方を考えています。米粉の粘度を調査していた時に、普通のお米は測定缶の中で固まらないけど北瑞穂は固まっているのに気づいたんです。これは面白いかも!と調べてみると、北瑞穂を米粉にして水を加え加熱するとゲル状になることが分かりました。それをゼリーのような形で菓 子や介護食にできないかと考えています。普段の実験の中で「ちょっと違うな」と気づくことと、頭の片隅にある日常生活の中の「こういうことに使えないかなぁ」を結びつけることが大事だと思います。
家庭と仕事の両立は夫のおかげ
今、家庭と仕事が両立できているのは夫のおかげです。朝食と夕食はほとんど夫が作っています。私は私で作れないストレスがありますが、そうは言っていられません。定時で仕事を終わらせて2歳と4歳の子どもを迎えに行き、帰宅したら18時。急いで晩ご飯を食べさせて19時にはお風呂に入って、20時にはお布団に入って、21時までには寝かしつけ、翌朝6時には起床、という慌ただしい毎日です。定時に帰るために時間内に仕事の段取りをつけて終わらせるようにしています。自分の中である程度のところでここまで、と線引きをして見切りをつけることが大事だと思っています。子どもの病気など突発的に休むこともあるので、色んなことを締切日より早く終わらせるように心がけています。できていないことも多いですが。
頼もしい存在の研究支援要員
出産後に研究支援要員の雇用経費補助制度*を利用しました。支援要員の方には私がいなくても実験できるようになってもらっています。はじめに手順書を作って教えるのは大変でしたが、子どもの熱で休む時にも続きの実験を分担してくれて、とても助かっています。先輩ママでもあり地元の方なので、子連れで行くおすすめの場所とかもいろいろ教えてもらっています。実は同じ誕生日なんです。履歴書を見て、この人だ!って思いました。縁ですね。