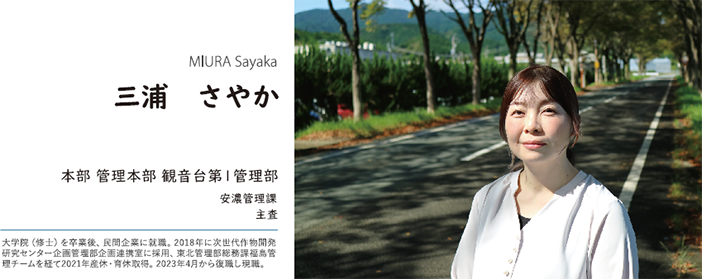

一見、敷居が高い農研機構
もともと地元の農業関係の会社に勤めていました。農研機構の話をよく耳にしており、その存在自体は知っていましたが、国の研究機関ということで、どこか敷居が高い印象を持っていました。転職を考えたのは、今の会社でこの先一生働けるのかと悩んだとき。自分の親の介護も視野に入れると、今の仕事を続けながら介護をするのは難しいと感じました。農業が好きだったので、新たに農業関連の仕事を探していたところ、農研機構が中途職員を募集しているのを見つけて応募しました。応募期間ギリギリでのエントリーでした。
農研機構は暦通りの働き方で、給料や手当も充実していて、ここなら一生安心して働けると感じました。農研機構は格式ばったところだと思っていましたが、実際はみなさんとても優しくて親しみやすい方ばかりでした。当時は結婚のことを考えていなかったので、一人で生活できるようになりたいと思っていました。前職では主に野菜を扱い、圃場での作業が中心でしたが、農研機構での仕事は全く異なりました。最初の配属先は、茨城県つくば市にある次世代作物開発研究センター(当時)の企画管理部でした。研究所内の事務系のポジションで、外部資金の管理を担当しました。研究者とのやりとりや、成果発表の調整を行う業務に取り組んでいました。
仕事のやりがいについて
現在、厚生の仕事を担当しています。助成金や共済の給付に関する相談が多いのですが、給付対象かどうかに関係なく、まずは相談しやすい雰囲気作りを心がけながらお話を聞き、その後に制度の紹介をするようにしています。個人的な相談が多いのですが、私自身も機構の様々な制度を利用してきたので、そういった相談を受け、役立てたと感じた時はとても嬉しい気持ちになります。どんな仕事をしていても、誰かの役に立つ部分が必ずあると常に思っています。
研究資金についても、外部資金を多く持つ研究者と話す際、残額や課題についての情報を共有し、こちらから予算執行について提案することもありました。外部資金研究を円滑に進めるためには、研究者から相談を受ける前に自ら調査し、状況を把握しておくことが大切です。
福島研究拠点にいた時は、職員数は50人ほどで、直接顔を見て話す機会が多かったのですが、安濃野菜研究拠点では、職員数は100人近くになり、まだ直接話したことのない方も沢山います。仕事を通じて、今後もこの拠点にいる方々との関わりを大切にしたいと思います。安濃野菜研究拠点に長くいる方は拠点内のことに詳しいため、困った際にはその方に聞けば解決策が見つかります。また異動を経験した方は、他の研究拠点のやり方や本部の考え方を持ち込んでくれるので、いろんな経歴の方がいると働きやすいと感じます。
子育てと仕事のリアル
夫は滋賀県で働いています。2人の出会いはつくばでしたが、知り合ってすぐに私が福島へ異動になりました。その後、結婚の話が進んで入籍しましたが、当初は別居婚として福島と滋賀でそれぞれ生活していました。福島の勤務中はつわりがひどく、具合が悪くなって早退し、そのまま1か月間の病欠となってしまったこともありましたが、上司や同僚のサポートのおかげで何とか業務を回すことができました。その後、産前産後休暇・育児休業を経て、安濃野菜研究拠点に異動になりました。現在は、滋賀県草津市に住んでおり、そこから通勤しています。
今、子どもは2歳で保育園に通っています。お互いの実家が遠いため、私たちは完全に二人で育児を行っています。子どもが熱を出した時のお迎えは、夫の担当です。私は勤務時間が決まっているので、休暇の日数が足りなくなってしまうのではないか心配でした。一方、夫は裁量労働に近い働き方をしており、ある程度フレキシブルに対応できるため、育児の多くを任せています。そのため、住まいも夫の職場に近い滋賀県にしました。通勤は車で1時間半かかりますが、一人車内で好きな音楽を聴いたり、四季折々の景色を楽しみながら、家庭⇔仕事の気持ちを切り替える時間として、いい気分転換になっています。
育児休業復帰当初は、育児短時間勤務を利用して毎週火曜日と金曜日を休みにしていましたが、育児の状況に応じて、現在は毎日出勤するスタイルに変更しました。育児時間※の制度によって勤務時間が短いため、朝食や身支度など、子どもとの時間を持つことができています。周囲の方々も非常に協力的で、勤務時間内に業務が終えられるよう配慮してくれているため、残業はほとんどありません。休暇制度も、周囲の目を気にせず使える雰囲気があります。子育てと仕事を両立させるために、寝かしつけの後に家事を済ませたり、収納場所に何が入っているか、夫にもわかるようにラベルを貼るなどの工夫もしています。
農研機構を目指す人へのメッセージ
農研機構は、働きやすい環境が整っており、制度もとても充実しています。重要なのは、働く企業の雰囲気が自分にフィットするかどうかです。学生時代には人との関わりを大切にし、同学年やアルバイト仲間だけでなく、社会に出た際には年齢や考え方が異なる多様な人々と接する機会が増えることを意識しておくと良いと思います。こうした環境に身を置くことで、新しい発見や驚きが得られます。特に学生時代に異なる年代の人々と交流することは非常に重要です。私自身も、もっと多くの先生と話すべきだったと感じています。コミュニケーション能力を磨くためには、何でも気軽に話し合うことが大切です。学生のうちにこの経験を積んでおくことで、社会に出た時に驚きや違和感を感じることなく、円滑に職場に馴染むことができると思います。
最後に...
これまで私に関わってくださった農研機構の皆さまに心から感謝いたします。つわりで長期病休した時、産休や育休中、短時間勤務の期間中、私の業務分の負担をかけてしまって申し訳なく思っています。皆さまの温かいサポートに感謝し、将来は自分が誰かをサポートする側に回れるよう、より一層努力していきたいと思います。 本当にありがとうございました。
※育児時間
小学校就学前の子どもを養育するため、1日30分~2時間以内で必要な時間勤務しないことが可能。

