
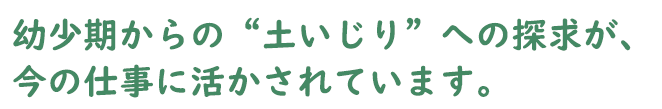
植物の形態変遷に魅せられて
実家の周囲には水田が広がっており、幼少期から植物や生き物が身近に存在する環境に恵まれていました。その中でも特に植物への興味が芽生えました。図鑑を手に取り「この植物は何だろう」と探求する日々が続きました。硬い石のような種が土に埋められ、いつの間にか芽を出し、子葉を広げぐんぐん成長し、最後には綺麗な花を咲かせることが、不思議でたまりませんでした。そして、実が実り、それを自分たちが食べるという体験は、とても印象深いものでした。植物だけでなく、蝶やイモムシといった虫にも親しみを持ち、自然界の多様な生命と触れ合うことができました。田んぼでおたまじゃくしを捕まえたり、ザリガニを釣ったりしたことは、楽しい思い出として今も心に残っています。中学・高校時代は部活動に没頭し、自然との接点が減ってしまいましたが、大学進学を考える際、改めて植物への愛着を思い出し、農学部への進学を決意しました。生物資源学科に所属し、園芸学や作物学を学びながら、植物を育てることで効率的な農業のあり方について探求しました。実習を通じて花や野菜を育て、土に触れる楽しさを再発見し、「やっぱり楽しいな」と心から感じる瞬間がありました。学生時代には特に熱帯果樹の栽培に注力し、その花粉についての研究にも取り組んでいました。熱帯果樹を選んだ理由は、これまで食べたことのない果物たちに対する好奇心からでした。私が育てたドラゴンフルーツは、成長した株を引き継いだものでしたが、自ら種を蒔くことにも挑戦し、芽が出る過程を見守りました。大学生活を経て、就職を考える際には、「土いじり」ができる職場で働きたい、という強い思いが芽生えました。
学部卒の挑戦
就職活動中、農業関係の仕事を希望していましたが、「土いじり」ができる職場はなかなか見つからずにいました。そんな中、農研機構の説明会に参加する機会があり、そこで先輩職員から種苗管理センターの技術職について詳しい説明を受けることができました。自分で植物を育てながら栽培試験に携われるという話を聞き、胸が高鳴りました。私のまわりの学部卒は営業職での就職が一般的でした。その中で農研機構に出会えたことは、私にとって幸運でした。農研機構が研究機関であることは知っていましたが、技術職があることを知らず、「研究職になるつもりはないけれど...」と軽い気持ちで参加したのです。しかし実際に話を聞いてみると、「自分がやりたい仕事がここにある!」という確信を持つことができました。この出会いが私のキャリアを大きく変えるきっかけとなりました。
新たな土地での土いじり
採用後、本所(つくば)での3ヶ月間の研修を経て、その後、沖縄農場へ異動し、沖縄の美しい自然に囲まれた環境で遺伝資源業務を担当しました。ここでは、サトウキビや、柑橘類、ヤマノイモ、キャッサバなど多様な植物の栄養繁殖を行い、毎日が新しい発見でした。沖縄に来た当初は、家族や友人と離れ、孤独を感じることもありました。特にコロナ禍で実家に帰りづらく心細さが募りましたが、農場の仲間が大きな支えになりました。着任初期にいた主任の女性職員や2期上の先輩のおかげで孤独感は和らぎ、観光地に連れて行ってもらったり相談したりするうちに馴染むことができました。3ヶ月後には同期も増え、職場は賑やかになりました。地元の技術支援職員にも大変お世話になりました。
その後、本所に戻り、1年半、バジルの栽培試験を担当しました。温室はバジルの香りに包まれ、プレッシャーを感じながらも周囲のサポートに助けられました。バジルは3月に播種し、6月から8月に調査、9月に報告書提出という短いスパンで進める必要があり、文献を読みながら前任者の作業記録を参考にして植物の成⻑に寄り添いました。毎年新しい品種が出願され、その特性や栽培方法に違いがあるため、特に注意が必要です。出願品種と既存品種を比較し、特性を確認することが重要で、常に緊張感を持って取り組む日々でした。現在は、⻄日本農場でシクラメンの栽培試験を担当しています。シクラメンは涼しい環境を好み、夏の暑さには弱いため遮光などの対策を行っています。夏季は成⻑が止まったりすることもあり不安になりますが、無事に育ち、花が咲き、調査を迎えられると植物に心から感謝したくなります。出願品種は5品種あり、全体で15品種のシクラメンを栽培し、類似品種との比較を行っています。シクラメンは他殖性(他個体の花粉で受精・結実する性質)が強く、種子繁殖性品種は株ごとのばらつきが大きいです。そのため同じ品種内で花の色や葉の模様が違うことがあり、均一かどうかを評価するため、過去のデータを参考にしながら正確な判断を下す必要があります。昨年の冬に初めて調査を行い、報告書を提出しました。次回もシクラメンを担当する予定ですが、将来的には他の植物の経験も積みたいと考えています。さまざまな植物に触れることで、技術やアイデアを広げていきたいです。
また、体調が優れない時などで仕事を休む場合、チームの存在が心強いです。シクラメンを見守ってくれる仲間がいるので、お願いもしやすいし、みんなが状況を把握してくれています。逆に、他の方からお願いされた場合は、少し緊張しながらも、責任を持って慎重に見守るようにしています。
心を豊かにする趣味
岡山県内で毎月行われる植物の観察会に参加しています。倉敷の博物館友の会の一環で、山に生える植物を観察しています。参加者は植物や生き物に興味がある方が多く、豊富な知識を持っているので、たくさん教えてもらっています。観察会で覚えた植物を農場で見かけると、今まで認識できていなかったことに驚くことがあります。友の会のメンバーは様々な年齢層で構成され、皆が植物を愛する仲間です。観察会では植物の種類についての議論が起こることもあり、その様子を楽しんでいます。まだその議論に参加するほどの知識はありませんが、いつか詳しくなりたいと思っています。また、⻄日本農場の若手職員と月に1回バドミントンを楽しんでおり、仲間は約10名です。書道にも挑戦してみたいと思っており、字をきれいに書きたいという願望があります。休日にはアニメを見たり、漫画を読んだりするのが好きです。このように、趣味に費やす時間を確保できるのも、農研機構の良いところと思います。

