
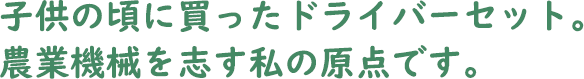
心躍る分解の軌跡
自由な雰囲気の家庭に育ち、機械やおもちゃの分解に夢中でした。構造への好奇心は尽きず、お小遣いで手に入れたドライバーセットを手にした瞬間、「これで何でもできる!」と心躍らせました。小学生の頃は、ゼンマイのおもちゃを分解しては元に戻せなくなったり、クリスマスツリーの電飾がなぜ点滅するのか知りたくて、とことん分解していたらいつの間にかショートさせてしまったり...。そんな私を家族は温かく見守ってくれました。大人になってからも、動かない時計を見つけて、「このギヤがこうなって...」と考えるうちに、再構築できずに手をこまねいてしまったりと、相変わらずです。就職後には、ある展示会で前日に突然、機械が故障する事態となりました。この時も急いで分解・調整し、当日は何事もなかったかのように実演ができました。「何が良かったのかな?」と自問自答しながらも達成感に浸りました。現在も仕事として機械やセンサーの組立や分解をしています。
センサーの構造を深く理解していることがエラー発生時の助けになるのはもちろんですが、実のところ分解を楽しんでいたりします。
農学と工学の間隙を突く
高校時代は農学を志していました。当時、DNAやタンパク質に関する研究が流行っていましたが、実験室にこもって作業するスタイルは自分には合わないと感じていたので、農学部の中でも工学寄りの農業環境工学科に入学しました。勉強や研究で行き詰まると、友達の研究室に遊びに行ったり、キャンパス内で飼育されている牛や羊をフェンス越しに眺めて過ごしました。フィールドワークができ、栽培試験を行いながら測定できる研究室を選び、植物工場で使用する生育状況モニタリングの精密化に取り組みました。熱電対やひずみゲージを駆使して、自作したセンサーを植物に取り付け、茎の太さや水分、重量の日変化を測定しました。植物は面白く、夜中に水分を吸収し太くなり、昼にはほっそりとします。このリズムを繰り返すことで茎が太くなるトレンドの周期変化を、博士号を取るまで探求し続けました。
自分の意見ははっきりと言う
学生時代に参加した農業機械系の学会では、農研機構の職員をよく見かけました。知り合いも多く、指導を受けた教員の一人が農研機構の出身で、自分の所属する研究室からも多くの農研機構職員が輩出されていました。そのような背景から、農研機構は自然と身近な存在となっていました。採用後、⻄日本農業研究センター(⻄農研)に配属されると女性職員の数は少なく、特に農業機械の分野では、⻄農研での女性採用は私が初めてでした。当時、女子トイレが古く、整備も遅れていたので、女性職員や女性の⻄農研所⻑(当時)と共に声を上げ、改装や新設を実現しました。農業機械の分野では、作業はだいたい4人1組で行われることも多く、大きな機械を扱う際には、手伝ってくれる年上の同僚・業務科担当者に指示を出すこともあります。大学院時代には担当教授へ指示を出すこともありました。そのため、作業に責任を持って、はっきり意見を言うことが求められます。依頼し合う関係は持ちつ持たれつ。農研機構においても円滑に仕事を進めるのに役立っています。
中山間地域で進むロボット活用
中山間地域は耕地面積と農業産出額で約4割を占め、食料生産や豊かな自然・景観の保全に貢献しています。しかし、傾斜地や不整形な圃場が多く、大区画化や大型農機の導入が難しいため、生産性向上は平地と比較して難しく、人口減少や高齢化による担い手不足も相まって、営農条件は厳しい状況です。私たちは中山間の農業現場という過酷な環境を想定して機械開発に取り組んでいます。現在は、手軽にスマートフォンで遠隔操作できる草刈機を開発中です。また、畦畔管理の省力化を目指して、草刈り作業の適否判定や作業時間の推定などを行うアプリケーションを開発しています。草刈機の機種ごとに作業にかかる所要時間や作業量を、広島県内の圃場で調査して、データセットを作成しています。近い将来、これをAIで解析することで、どのような作業計画が最も効率が良いか、といったデータが整理されてくると考えています。リモコン式草刈機については、私たちもプロジェクトの成果報告を通じて技術的課題を提起してきていますが、これに対応した機械が増えてきていると思います。農業機械の業界では、業界全体でガイドラインの作成が進められていますが、ロボットトラクター(ロボトラ)が中山間地域の複雑な地形や狭い公道を走行できるようになるまでには、まだ少し時間がかかると考えられます。RTK測位※が普及すれば、中山間地域の不整形圃場でもロボット農機の活用が期待できるでしょう。中山間地域で使用できる小型のロボット農機は、小さな凹凸などに弱く、スタックする可能性がありますが、農地や畦畔のちょっとした凹凸を取り除くことで、ロボットがスタックしにくくなるだけでなく、人間にとっても優しい環境になります。
中山間地域の将来像としては、精密な測位に基づくロボット農機の運用に加え、例えば電動農機や電動車両のための共用充電ステーションの設置なども考えられます。スマート農機の導入を前提とした基盤整備や設計により、農地の正確なマップの整備が進むことで、農作業の自動化・効率化の相乗効果が得られることが期待されます。
家事の機械化を楽しむ
今年8月に結婚し、忙しくも充実した日々を送っています。地元の方と結婚したことで、新しいスポットや遊び方を知り、驚くことも多いです。家事に関しては、手間を極限まで減らすために機械を積極的に導入しています。食器洗い機や衣類乾燥機はもちろん、ロボット掃除機も購入しました。お約束のように、バッテリー位置やセンサー種類など、機体構造を確認する楽しみもあります。また、特殊な波⻑のLEDが搭載された冷蔵庫など、最近実用化された家電を夫と一緒に見て回るのも楽しみの一つです。これからも、より快適な生活を目指して、仕事と家事の効率化を進めていきたいと思っています。
※RTK (Real Time Kinematic )測位
衛星測位システム(GPS等)を使用した単独測位では数メートル単位での誤差が生じるが、RTK-GNSSでは垂直・水平方向にcm単位の正確な測位が可能になる。

