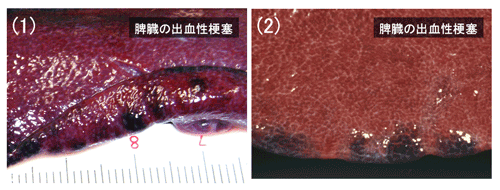豚熱は死亡率が高いが、特徴的な臨床症状や病変を示さない。はじめ、発熱、食欲不振、うづくまり、群飼いの場合には豚房の片隅に体を寄せ合うパイルアップ、嗜眠など元気消失がみられる(写真1(1)~(3))。通常発熱期に一致してウイルス血症及び白血球減少が起こる。ついで結膜炎による目やに(写真1(4))やリンパ節の腫脹、呼吸障害、中には便秘に次ぐ下痢(写真2(1))がみられるようになる。後躯麻痺(写真2(2))・運動失調・四肢の激しい痙縮などの神経症状もみられるようになり、やがて起立困難となって、奇声を発して遊泳運動(写真2(3))を示しながら、死亡するものがでてくる(写真2(4))。この間、およそ1週間ぐらいである。それを過ぎても生きながらえると皮下出血による紫斑が皮膚の薄い耳翼、尾、腹部、内股部に目立つようになる。一般的に発症から死亡するまでの期間が10~20日以内のものを急性豚熱(図7)といい、発症回復を繰り返した後に削痩(ヒネ)て30日程度で死亡するものを慢性豚熱(図8)という。この経過の違いは月齢や品種、免疫状態など豚側の要因にも影響を受け、ただ単にウイルスの株の違いだけに依存しているわけではない(表4)。中には経過がもっと長くなって死亡する場合や回復する場合、はじめから不顕性に終わる場合もある。急性豚熱では抗体が産生される前に死亡してしまうが、一方、慢性豚熱となったものは感染抗体を産生している場合が多い。妊娠豚に感染すると垂直感染、つまり胎仔感染も起こし、その結果、死流産も起きる。ウイルスの病原性や感染時の胎齢によっては感染豚が正常に娩出される場合がある。感染豚は豚熱ウイルスに対して免疫寛容となっており、ウイルス血症を起こしているにもかかわらず抗体が産生されない。こうした豚は先天性持続感染豚と呼ばれ、牛のBVDでいう持続感染(PI)牛に相当する。経過期間は様々で長いものもでは半年以上に及ぶこともあるが、やがて臨床症状を呈して死亡する。これを遅発性豚熱といい、持続感染豚が新たなウイルスの感染源となるため、持続感染豚の摘発は重要である(表5)。なお、BVDウイルスが豚に感染した場合、そのほとんどが不顕性感染に終わり、水平感染も起こらない。しかし、胎仔感染が起きた場合には豚熱と区別できない臨床症状を生じたとの報告もあり、注意を要する。
経過が長くなってくると、発症豚の体内では主に充出血性病変が現れてくる(表6及び写真3)。膀胱粘膜の点状出血(写真4)やリンパ節の髄様腫脹と充出血(写真5)は比較的早期から出現する。腎臓の点状出血も出現頻度は高く、激しく出血点が現れたものはその様子から「ターキーエッグ(七面鳥の卵)」とも呼ばれる(写真6)。割面を入れると腎盂斑状出血(写真5(2))も確認されることもしばしばある。こうした出血性病変は細菌感染による敗血症やクマリン(抗凝血性殺鼠剤)中毒でもみられるが、まずは豚熱を強く疑うべきである。また、脾臓の辺縁に出血性梗塞(写真7)や回腸粘膜面にボタン状の潰瘍がみられることもあるが必ずしも出現頻度は高くはない。
写真1.豚熱の臨床症状
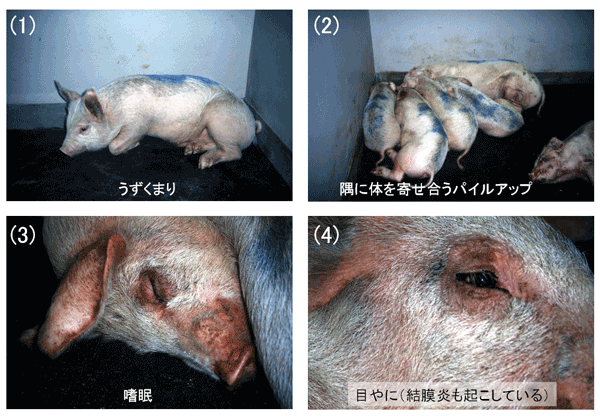
写真2.豚熱の臨床症状
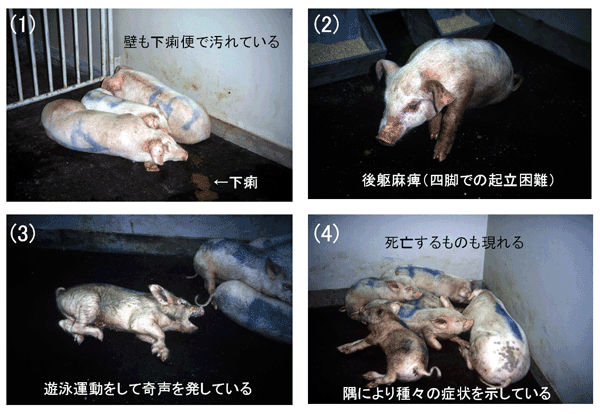
図7.豚熱ウイルスによる急性感染
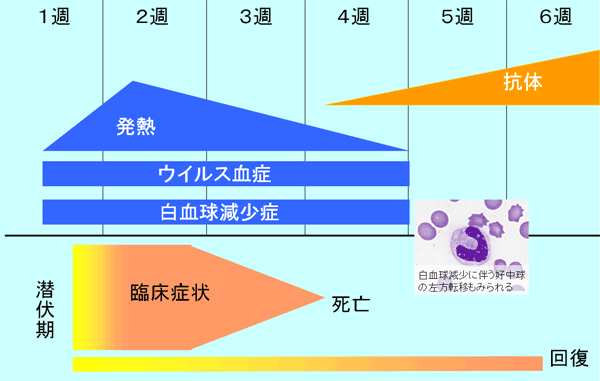
図8.豚熱ウイルスによる慢性感染
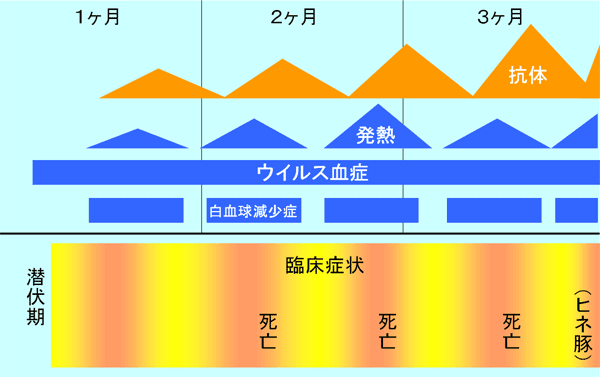
表4.豚熱の病態に及ぼす要因
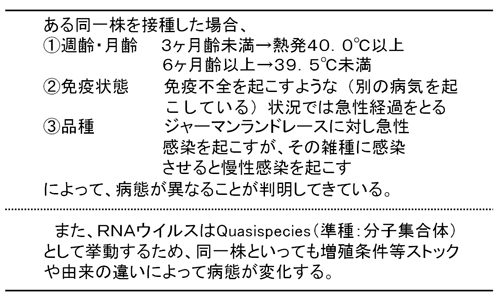
表5.豚熱の病態による型(個体レベル)
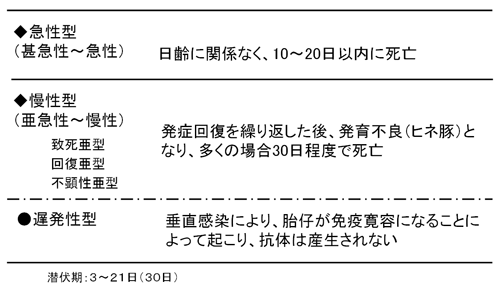
表6.豚熱の肉眼病変の出現頻度(実験感染)
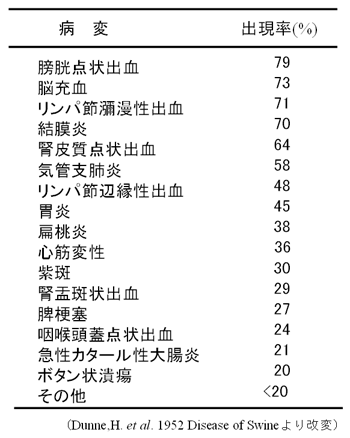
写真3.豚熱の肉眼的病変
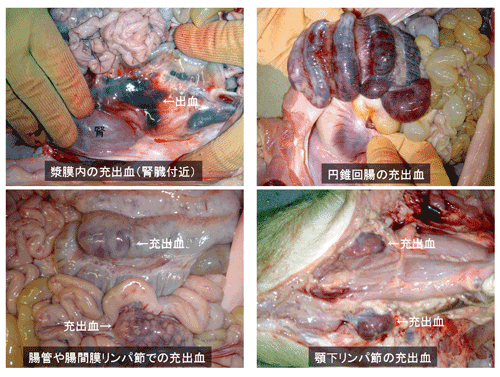
写真4.豚熱の肉眼的病変
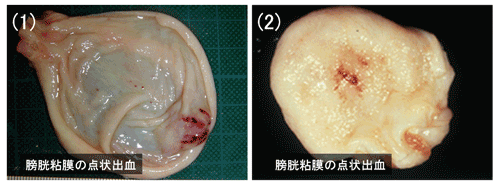
写真5.豚熱の肉眼的病変
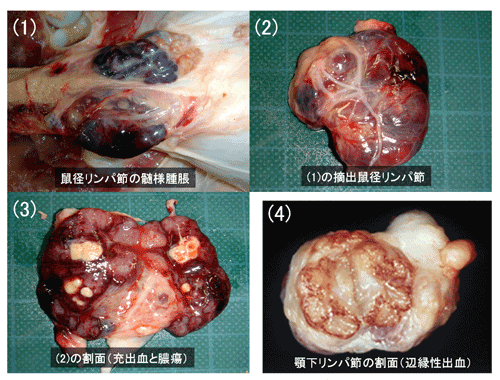
写真6.豚熱の肉眼的病変
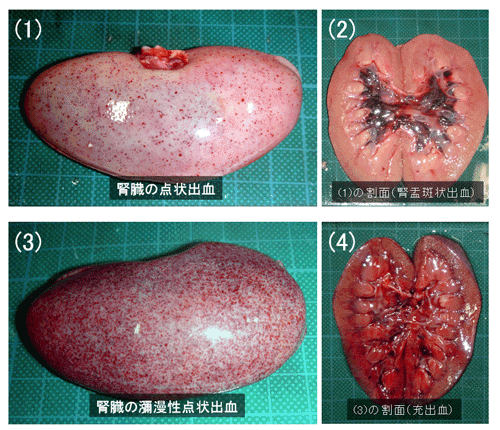
写真7.豚熱の肉眼的病変