なお、動画のコメント欄からのお問い合わせにつきましては、原則として個別の回答は行っておりません。
農業が育む生物多様性

(画像をクリックすると動画が再生されます)
農村は農業などの人間活動でつくられる「二次的自然」です。そこには多様な生き物が生息しています。
本動画では農業により維持される豊かな自然環境や生物多様性を研究成果から分かり易く解説します。「農村における生物多様性の特徴」、「有機農業と生物多様性」、「ヴィンヤードにより育まれる生物多様性」の3部で構成されていて、最後に、それらの環境を守るために私たちができることを紹介します。
西日本に広がる水稲乾田直播

(画像をクリックすると動画が再生されます)
水稲乾田直播栽培とは、乾いた畑状態の田んぼに種をまいてイネを育てる技術です。苗作りや代かき、田植えが省けるので労働時間を大幅に削減できます。乾田直播栽培の導入が、大規模水稲作の担い手が直面する切実な課題の解決に貢献することが期待されます。
操作は簡単!「ノビエ防除支援システム」~乾田直播栽培での雑草防除~
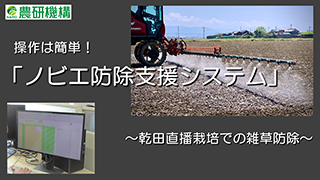
(画像をクリックすると動画が再生されます)
水稲の乾田直播栽培では、生育初期における乾田期間に雑草が生育しやすく、生産現場では除草剤による防除適期を逃して雑草が繁茂する事例が多く発生しています。そこで農研機構では、日平均気温から防除適期の目安となる雑草(ノビエ)の葉齢を推定し、指定した日付のノビエ葉齢が簡単な操作で確認できる「ノビエ防除支援システム」を開発するとともに、このシステムの利用方法を標準作業手順書に取りまとめました。本システムを活用して適期に除草剤散布を行うことで雑草の繁茂が効果的に抑えられ乾田直播栽培における雑草防除の安定化につながることが期待されます。本動画では、「ノビエ防除支援システム」の利用方法をわかりやすく紹介しています。
どうする!?荒廃農地-最新フレールモアで放牧地に復活させてみた-
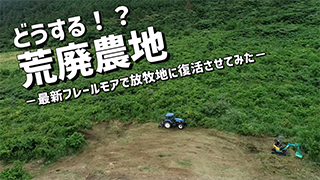
(画像をクリックすると動画が再生されます)
私たちはフレールモア(ハンマーナイフモア)という機械を使って、荒廃農地を放牧地に再生する現地実証を進めてきました。この動画では、3種類のフレールモアの特徴を紹介します。 耕作放棄された土地に樹木が侵入してしまい、「再生困難な荒廃農地」となって問題になっています。荒廃農地は、高齢化や労働力不足が発生の主な要因とされていて、その解消は食料自給や農村活性化のための喫緊の課題です。
一方、放牧を取り入れた畜産は、飼料費の大幅削減が期待できることから、省力的で高収益な営農手段として注目されています。放牧は傾斜地でも可能で、野草などもそのまま利用できるため、荒廃農地の解消手段としても有力です。
なが~く放牧してコスト削減

(画像をクリックすると動画が再生されます)
私たちは条件の不利な地域でも収益を確保できる生産方式として「放牧を活用した肉用牛の子牛生産」を推進しています。牛を牛舎で飼う場合には、牧草の収穫、給与、糞尿の処理を人の手で行う必要がありますが、放牧ではこれらの作業が不要で、牛は自分でエサを食べるので手が掛からず低コストです。
本動画では、できるだけ長い期間放牧するために、寒地型牧草と暖地型牧草を上手に組み合わせて、春から秋までの牧草生産量を一定に保つ技術を紹介しています。
農研機構 西農研 市民講座「生物多様性と農業の深ーい関係!」

(画像をクリックすると動画が再生されます)
生物多様性を一言で表現すれば「生命のにぎわい」といわれています。私たち人間は生物多様性からたくさんの恩恵を受けて生活が成り立っています。とくに農業と生物多様性はお互いに良い影響も悪い影響も与えあう深い関係にあります。身近に存在する水田、雑木林、ため池、水路等の自然環境と生き物を繋がりを整理しながら、さまざまな農業により育まれる生物多様性をわかりやすく紹介していきます。農業と生物多様性の関係を見つめることで、自然と共生する新しい農業のあり方を皆さまと考えたいと思います。本セミナーが皆さまの持続的な社会構築に向けてライフスタイルを考えるヒントになれば幸いです。
※この動画は2022年11月15日に開催した農研機構 西農研市民講座の映像を再編集したものです。
農研機構 西農研 市民講座「もち麦をおいしく食べよう♪」

(画像をクリックすると動画が再生されます)
健康志向が高まるなか注目される "もち麦" の特長、農研機構 西日本農業研究センター育成のもち麦品種「キラリモチ」を紹介しています。この動画を参考に、もち麦クッキングを楽しんでください。
※この動画は2022年11月15日に開催した農研機構 西農研市民講座の映像を再編集したものです。
