 今年も梅雨の季節がやってきました。じめじめして、雨が降って、 時には洪水にもなりかねません。
今年も梅雨の季節がやってきました。じめじめして、雨が降って、 時には洪水にもなりかねません。
でも逆に、雨がまったく降らなくても大問題です。
私たち人間はもちろん、植物も、他の動物も、 みんな生きるためには水が必要です。
この季節の雨は、「恵みの雨」でもあるのです。
多すぎても困る、少なすぎても困る、そんな水の問題に田んぼが役に立っています。
情報公開日:2007年6月14日 (木曜日)
 今年も梅雨の季節がやってきました。じめじめして、雨が降って、 時には洪水にもなりかねません。
今年も梅雨の季節がやってきました。じめじめして、雨が降って、 時には洪水にもなりかねません。
でも逆に、雨がまったく降らなくても大問題です。
私たち人間はもちろん、植物も、他の動物も、 みんな生きるためには水が必要です。
この季節の雨は、「恵みの雨」でもあるのです。
多すぎても困る、少なすぎても困る、そんな水の問題に田んぼが役に立っています。
日本全国各地にひろがる田んぼは、お米を育ててくれるほかに、「環境保全機能」をもっています。その機能は水、土、大気、景観など、様々な方面にはたらいているのですが、ここでは、特に水に関するはたらきをあげてみましょう。
1度にたくさんの雨が降ると、川が増水したり、建物が水に浸かったりと、洪水を起こすことがあります。そんなとき、田んぼはその土深くに雨水を貯めて、川への水の流れをゆるやかにしてくれます。
特に、山の斜面につくられる棚田は、その機能がすぐれています。

上記のように、雨が多かったときの水を貯めておけば、雨が降らず水が不足するときには、貯めておいた水を使うことができます。さらに、雨水を少しずつ地下に浸透させることで地下水にもなります。田んぼは長い間水を張るので、その分多くの地下水を貯めることができます。
水が地上から地下に浸透していく途中で、その汚れが大気に蒸発したり、土にくっついたりするので、しみ出てくる地下水がきれいになります。
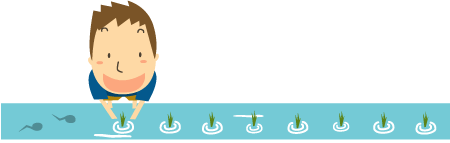
(独)農研機構 農村工学研究所では、農村の「豊かな環境の形成と多面的機能向上」のために、 田んぼの洪水防止機能や地下水について研究しています。
他にも、「台風豪雨や大きな地震にも強い画期的なため池の整備技術」を開発したり、 実際に豪雨災害や地震がおこった現場にかけつけて現地調査を行なったりしています。
![]()
熊本県熊本市圏約100万人の住民は、生活用水のほとんどに地下水を使用しています。それは地下水の源となる「かん養域」に白川中流域があり、そこの特殊な水田「ザル田」が非常に水を染みこみやすいため、多くの水を地下に貯蔵できるからです。
ところが貴重な「ザル田」は減反やさまざまな理由によって年々減少し、地下水もまた減少しています。 そこで、地下水を増やすために転作田に水張りをする「地下水涵養事業」が平成16年度から始まりました。
その中で疑問にあがったのが、水張りをすることで養分が流れてなくなってしまうのではないかということです。 その疑問に答えるべく、 (独)農研機構 九州沖縄農業研究センターの土壌環境指標研究チームは、実際に水張りをすることでどのような影響があるかを調べました。

実際に水張りをした転作田と水張りをしない転作田の経年比較等で調べた結果、
ということがわかり、熊本市圏での転作田の水張りは地下水にとっても、転作田にとっても良い仕組みであるということが証明されたのです。
参考資料 : ニンジン畑に水を張る理由~熊本市圏100万人の飲料水をつくる農業~[PDFファイルへ]
![]()
このように、田んぼは色々な力を秘めています。
そんなことにも思いをはせながら、もう1度、身近にある田んぼを眺めてみてください。