中日本農業研究センター
所長室より -年頭の挨拶-
情報公開日:2018年1月 4日 (木曜日)
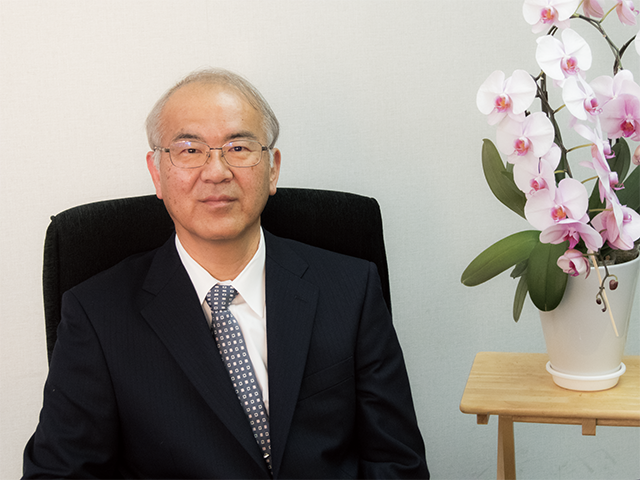
新年あけましておめでとうございます。
第4期中長期計画期間より、中央農業研究センターは、農研機構のフロントラインとして、関東東海北陸地域の農業が抱える技術的課題の解決に取り組むという役割を担うことになりました。これに沿って、私たちは、昨年、様々な取り組みを進めてきました。
研究面では、新品種「つきあかり」や「はねうまもち」の普及に向けた取り組みに加え、雑草イネや「バンカーシート利用マニュアル」に関するプレスリリース、イネ縞葉枯病の総合防除マニュアルの公開、ジャガイモそうか病PH測定法の紹介などを行い、また、農林水産省の行政部局や全農、日本農業法人協会等と連携した取り組みも進めています。特に、昨年度は、病害虫分野の海外レビューと国際シンポジウム、あるいは、「雑草イネ」に関する国際シンポジウムの開催など、国際交流に関わる積極的な活動を実施しました。そして、NARO-Research Prize 2017や、SATテクノロジー・ショーケース2017「ベスト産業実用化賞」、学会賞の受賞などの評価を得てきました。
研究成果の広報・普及面では、東海・関東・北陸の3ケ所のマッチングフォーラムを通して合計約350名もの参加者を得るとともに、アグリビジネスフェアや成果発表会の開催、現地実証研究等を通じて、研究成果の広報・普及を図ってきました。2回の知財セミナーや、民間企業等との共同研究、各種の協定研究も開始するとともに、北陸拠点での「食と農の科学教室」の開催や、一般公開など、地域住民との交流も積極的に実施してきています。
一方、将来に向けた研究シーズの醸成に向けた活動も進めており、目的基礎研究では合計14の課題を、昨年度より設けた所内公募研究については8課題を実施するなど、次期につながる興味深い研究も行われています。今後も、このような社会実装につながる研究と、基礎研究を車の両輪として実施していきたいと思います。
総務、企画、連携広報、リスク管理、技術支援部門における研究支援面での活動については、第4期も2年目に入り、事業場の管理に加え、労働安全衛生やリスク管理面でも意欲的な取り組みが実施されています。
現在、大課題推進においても計画-実行-評価-改善というPDCAサイクルに沿った対応が求められていますが、これは、本来は企業の経営改善活動を意味するものであり、研究所の業務推進においても、このようなPDCAサイクルを回していく必要があることは言うまでもありません。この点では、職場の中でのコミュニケーションを深めながら、組織運営における問題点を見出し、改善事項についてはできるだけ早期の対応が図れるよう工夫をしていきたいと思います。
さて、このような研究所の業務推進に加えて、今後の日本農業の方向や、私たちの組織の社会的使命といった点についても考えを述べたいと思います。
中央農業研究センターの前身となる農業研究センターは、昭和56年10月に発足しました。この農業研究センターは、農事試験場の筑波移転や、農業技術研究所の改組といった大きな再編によりもたらされた組織のため、そのあり方、方向性については活発な議論がなされました。その中核となった概念は「総合研究」です。これは、専門分化した農業研究を農業現場に即した総合的な研究として改めて体系化していこうとする試みであったと思います。そのため、総合研究チームの創設など、様々な取り組みが実施されました。農業研究センターは、当時で言えば農林水産省所管の農業試験場の中核組織としての役割を果たしてきたのであり、また、関東東海北陸地域を対象とする地域農業研究センターとして、さらに、土地利用型農業及び環境保全型農業に関する専門研究所としての機能を発揮してきました。この点は今日も変わるものではありません。そして、このような組織ミッションのもとで多くの研究成果を創出してきました。
一方、この農業研究センター-の設立から36年が経つわけですが、日本農業は、若い人たちに魅力ある産業として、また、国際的にも競争力のある産業として展開し得ているでしょうか。あるいは、私たちは国民への食料の安定供給を可能とする技術的基盤を十分提供できているでしょうか。
このような問題意識から、昨年、私が経営調査を継続して実施しているある水田作経営の約30年間の作物収量や労働時間、農業所得などの推移を整理してみました。この経営は、労働力2名で、水稲、小麦、大豆、野菜類を中心に約30haの耕作を実施してきた経営です。それによると、水稲の品種構成は多収性品種から良食味品種に変わりましたが、水稲単収は昭和60年に達成した10a当たり600kgという水準から大きく変わっていません。大豆の収量もほぼ同水準で推移しており、小麦についてはむしろ減少しています。10a当たり労働時間も、この20年はほとんど変化していません。農業所得は1戸当たり600万円から1000万円と年によって変動がありますが、基本的には横ばいであり、大きな変化はありません。しかし、その構成を見ると、米価下落を受け米販売代金が大きく減少し、代わりに、助成金・交付金の割合がかなり高くなってきています。
この間、農業政策は、「80年代農政の基本方向」による米・牛肉・みかん等の輸入自由化要求への対応や、「新政策」と呼ばれる効率的安定的経営体の育成を中心とする経営政策の推進、民主党政権下では食料自給率の向上を主な目標とする施策の実施、さらに、近年は、農業競争力強化に向けた取り組みなどが実施されてきました。
このように、様々な対策が講じられ、また、私たちも多くの技術開発を行い、科学的知見を公表してきたわけですが、しかし、現実の農業は、30年を超える年月を経ながらも、それほど大きな変化・発展は見せていないように思います。先ほどはある水田作経営の事例で述べましたが、日本農業全体について統計で確認しても同様であり、作物の収量性や作業効率、あるいは、技術体系そのものに基本的な変化はありません。わが国の食料自給率も向上してはいないのであり、むしろ、国内生産量の減少から、平成28年度の食料自給率は38%と、平成5年の大冷害年を除くと戦後最低という水準にまで低下しています。
これに対して、海外の農作物の収量性の推移、また、労働生産性という観点から他の産業の動向を見てみると、わが国の農業とは異なり、海外の農業や他産業では着実な生産性向上を達成しており、技術進歩という点で日本農業は明らかに遅れているというのが実態です。
もちろん、担い手の経営規模は近年、急速に拡大しており、様々な経営戦略が講じられるようになってきていることは事実です。6次産業化など事業の多角化も進められ、これまで見られなかった新しいタイプの経営も成立してきています。技術面でも、多様な品種開発が進められ、また、持続型の農業生産システムへの期待が高まるとともに、今日ではICTやRTに関わる技術革新も現実味を帯びるようになってきました。ただ、農業生産の基本である土地生産性や労働生産性に大きな変化が見られないということについては、そこに内在する問題点を改めて考えてみる必要があるように思います。
このような、いわば生産性の停滞といった問題は、もちろん、研究開発、技術開発という側面だけで解決できるものではありません。日本の制度、社会構造に起因している問題もあると思います。しかし、全体の雰囲気として、基本的な問題の解消を少しずつ先送りしてきているのではないかとも危惧されます。
少子高齢化社会のもとで、日本の社会構造は大きな転換期を迎えています。高齢化社会を先導する農村において、日本農業の姿も大きく変わっていこうとしています。このような中で、農研機構のビジョンステートメントにある「農研機構は、皆さまと共に食と農の未来を創ります」という責務を果たすにはどのような取り組みを実施していくべきか、今一度、深く考えていく必要があるように思います。
この1年、また気持ちを新たにし、職員と一緒に、農研機構のビジョンの達成に向けて努力して参りたいと思います。
本年もどうかよろしくお願い致します。
平成30年1月
農研機構 中央農業研究センター所長
梅本 雅
