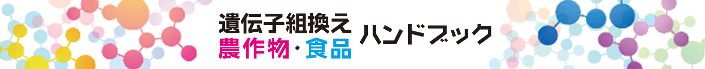あ
RNA干渉
【略語・別称】RNAi
【英語表記】RNA Interference, Ribonucleic Acid Interference
【用語説明】RNAiともいう。細胞に二本鎖RNAを導入した場合、それと同じ配列をもつ遺伝子の発現(タンパク質の合成)を抑制する現象のこと。
1998年、線虫で初めて観察され、その後、単細胞生物から植物、動物でも確認され、研究などで広く用いられた。真核生物において、標的遺伝子(mRNA)を破壊(分解)することにより遺伝子発現を制御するものであり、ウイルスに対する防御反応と類似した現象である。遺伝子解析の有効な方法として基礎研究で利用されているほか、将来の医療分野などへの応用も期待されている。
アガロース・ゲル電気泳動
【英語表記】Agarose Gel Electro-phoresis
【用語説明】DNAを分子量の大きさごとに分離する方法。
DNAはマイナス電荷を持つので電解質の中で電圧をかけると、プラスの電極側に移動する。その際の担体としてアガロース(寒天)を用いる。アガロースはゲル状で大きな網目構造(スポンジみたいな構造)をもつため、均一な「ふるい」の効果をもつ。
このため、短いDNAほどアガロースの孔を通過しやすいので移動が速く、長いDNAほど移動が遅くなるので、移動距離にバラつきが出る。この方法によりDNAを長さごとに分離できる。
アグロバクテリウム
【英語表記】Agrobacterium
【用語説明】土壌中にいる細菌で、この細菌の細胞の中にはプラスミドがあり、その一部にT-DNAと呼ばれる部分の遺伝子がある。
アグロバクテリウムは、接触した植物の細胞に、自分の遺伝子の一部であるT-DNA遺伝子を送り込む性質がある。
T-DNA遺伝子を組み込まれた植物は、腫瘍であるこぶ状の塊(クラウンゴール)や無数の根などを生じ、アグロバクテリウムの生存に必要な栄養素(アミノ酸)を作る。このようにアグロバクテリウムのT-DNA遺伝子は、遺伝情報に従い、接触した相手の植物にアミノ酸と植物ホルモンを合成させる働きがある。
この性質を利用し、アグロバクテリウムが持つプラスミドのT-DNA遺伝子の代わりに発現させたい目的の遺伝子を組み込み、このアグロバクテリウムを感染させて目的の遺伝子を植物に導入するという方法で、植物の遺伝子組換えが行われる。近年では、イネやトウモロコシ、コムギなどの単子葉植物の遺伝子組換えにも利用されている。
アデニン
【英語表記】Adenine
【用語説明】DNAやRNAなどの構成成分である。
DNAはリン酸、糖(D-デオキシリボース)、塩基からなるヌクレオチドがいくつもつながったものである。その塩基成分にはアデニン(A)・チミン(T)・グアニン(G)・シトシン(C)の4種類が存在するが、アデニンはそのうちの1つであり、遺伝子設計図の元となる化学物質の1つである。
また、このヌクレオチドには、ピリミジンという塩基を含むものとプリンという塩基を含むものがあり、アデニン(A)はプリン塩基を持っている。 DNAの二重らせんの中では必ずチミン(T)と結合している。
アミノ酸
【英語表記】Amino Acid
【用語説明】生物体の源となる栄養分。筋肉や皮膚等、生物の体を作っている成分はタンパク質で、そのタンパク質を構成しているのがアミノ酸である。
20種類のアミノ酸(バリン、ロイシン、イソロイシン、アラニン、アルギニン、グルタミン、リジン、アスパラギン酸、グルタミン酸、プロリン、システイン、スレオニン、メチオニン、ヒスチジン、フェニルアラニン、チロシン、トリプトファン、アスパラギン、グリシン、セリン)から自然界のタンパク質が構成されており、どのアミノ酸もアミノ基(-NH2)とカルボキシル基(-COOH)をもつが、その他の構造が変わることにより、アミノ酸の種類も変わってくる。タンパク質は、その種類によってアミノ酸の結合順序が異なり、生物がタンパク質を形成するときは、アミノ酸を一定の結合順序でつなげていくシステムが必要になる。この一定の結合順序は、タンパク質の設計図である遺伝子の配列に由来する。
また、動物の体内で変換できないアミノ酸を必須アミノ酸、変換できるものを非必須アミノ酸という。
必須アミノ酸として、トリプトファン、メチオニン、リジン、フェニルアラニン、ロイシン、イソロイシン、バリン、スレオニン、ヒスチジンの9種類がある。
アレルギー
【英語表記】Allergy
【用語説明】ある種の抗原に感作した生体に、もう1度同じ抗原が入った場合に過剰な反応を起こし、自己に障害を与えること。
気管支ぜんそく、花粉症、ソバアレルギーなどが代表的である。
アレルゲン
【英語表記】Allergen
【用語説明】アレルギーを起こす物質の総称。
アレルゲンは、一部の人において免疫機構により「異質なもの」または「危険なもの」と認識される物質で、多くの人においては何の反応も引き起こさない。
一般的なアレルゲンとしては、ある種の接触物(化学物質や植物など)、薬品(抗生物質類、血清など)、食物(小麦、そば、卵、乳、落花生など)、感染因子(バクテリア、ウイルス、動物の寄生生物など)、吸入物(ホコリ、花粉、香水、煙など)が挙げられる。
アレルゲンタンパク質
【用語説明】Allergic Protein
アレルギーを起こす可能性のあるタンパク質のこと。
アレルギーを起こす原因物質をアレルゲンといい、タンパク質からなるアレルゲンを指す。
農業や食品などの分野では、アレルゲンタンパク質の解析などが行われ、バイオテクノロジーを応用した除去・分解法を用いて、低アレルゲンの食物を作ろうという研究も進められている。
い
一塩基多型
【略語・別称】SNP, SNPs
【英語表記】Single Nucleotide Polymorphisms
【用語説明】DNA(遺伝子の本体)の塩基配列の中でたった1つの塩基の違いのこと。
英語の頭文字をとりSNP(スニップ)またはSNPs(スニップス)とよぶ。お酒に強い弱いや、薬が効きやすいかどうかなどの個人差を生む。
ヒトゲノム30億塩基対のうち、一塩基多型は約300万個(500~1,000塩基対に1個の割合)存在し、特定のタンパク質が作れなかったり、他人と違うものを作ったりして個人差(体質)、人種差などの違いをもたらしている。
ヒトにおける遺伝子の個人差の研究では、一塩基多型を解析して、病気に対する感受性や薬物への応答を調べ、その人にあった副作用の少ない薬を投薬するようなオーダーメイド医療が可能になるといわれ、一塩基多型の解析の研究が進められている。植物であれば、植物が本来持っている病気や害虫に対する抵抗性の仕組みを解明し、その機能を高めたりすることができる。
遺伝
【英語表記】Inheritance, Heredity
【用語説明】カエルの子はカエル、ヒトの子はヒトといわれるように、顔や手足の形、皮膚や目の色、くせや行動など、親と似た子供ができる。このように、それぞれの生き物がもつ形や性質を「形質」といい、親から子に「形質」が伝わる現象を一般に遺伝という。
この現象の本体は遺伝子でありDNAにより構成される。
遺伝暗号
【英語表記】Genetic Code
【用語説明】生き物の設計図である遺伝情報は、4種類の化学物質である塩基、アデニン(A)・チミン(T)・グアニン(G)・シトシン(C)で書かれている。この並び方をもとに生物の体の構成成分であるタンパク質が形成される。この塩基3つが1セットで、その順列の組み合わせを遺伝暗号(コドン)という。
タンパク質を作っているアミノ酸は20種類で、それぞれに対応する塩基の並び方があり、3つの塩基から成る遺伝暗号が1つのアミノ酸を指定している。
遺伝形質
【英語表記】Genetic Character
【用語説明】生物のもつ様々な形質のなかで遺伝性のあるもの、後世に遺伝する形質のこと。
生物のもつ形質には、色、形、大きさなど、外見的なものから、体の中にある物質の合成能力や、寒さや暑さに強いなど内面的なものと多々ある。
遺伝子
【英語表記】Gene
【用語説明】親からの形質(顔、皮膚や目の色など)の受け継ぎを決めるものが遺伝子である。遺伝子はDNA(デオキシリボ核酸)という物質でできている。生物の持つDNA配列上には、体を構成するタンパク質を作るための設計図のような情報がいくつか並んでおり、この設計図にあたる部分が遺伝子である。
その並び方は、1つの遺伝子で1種類のタンパク質というふうに、1本のDNAの中に種類の違うタンパク質の遺伝情報がいくつも格納されている。そして、細胞内ではこの遺伝子の情報からタンパク質が作られている。
遺伝子組換え
【英語表記】Gene(tic) Recombination
【用語説明】ある生物から目的とする遺伝子を取り出し、改良しようとする生物に導入することにより新しい性質を生物に組み入れること。
生物から有用な遺伝子を見つけ、DNA鎖を切断する作用をもつ制限酵素で有用な遺伝情報が含まれているDNA部位を分離する。分離されたDNA断片を改良しようとする生物の細胞の中に導入し、その生物のDNAに組込ませ、タンパク質を合成させる。その結果、有用な遺伝子の形質を付加した新たな性質の生物が完成する。
遺伝子組換え技術
【略語・別称】組換えDNA技術
【英語表記】Gene(tic) Recombination Technology
【用語説明】組換えDNA技術のこと。ある生物が持つ有用な遺伝子を、改良しようとする生物のDNA配列に組込むことにより新たな性質を加える技術。
植物にDNAを組込む方法としては、アグロバクテリウムという植物に寄生する細菌を利用する「アグロバクテリウム法」と、DNAを金やタングステンの粒子に付着させ、DNAを導入したい細胞に直接打ち込む「パーティクルガン法」などがある。
遺伝子組換え技術は農業分野やその他の分野において、様々な改良のために利用されている。
例えば、栄養成分や機能性成分(抗がん、ワクチン効果など)に富む農作物、日持ちする農作物など消費者のニーズにあった作物や、農薬使用量の減少のための害虫抵抗性やウイルス抵抗性、除草剤耐性などの性質を持たせた農作物が開発されている。その他、環境浄化微生物、生分解性プラスチックや医薬品の生産など様々な分野で遺伝子組換え技術が応用されている。
遺伝子組換え食品
【英語表記】Genetically Modi? ed Food
【用語説明】遺伝子組換え農作物および遺伝子組換え農作物を加工して作られた食品のことをいう。
例をあげると、遺伝子組換えダイズそのもの、あるいは遺伝子組換えダイズを加工して製造した味噌、納豆などの加工品も遺伝子組換え食品に含まれる。
遺伝子組換え食品を国内で販売するには、国における安全性審査と承認が必要となる。
遺伝子組換え生物
【略語・別称】GMO, LMO
【英語表記】Genetically Modi?ed Organism, Living Modi?ed Organism
【用語説明】遺伝子組換え技術により改変された生物のこと。
一般的には、遺伝子組換え生物はGMO(Genetically Modi?ed Organism)の用語が用いられることが多いが、カルタヘナ議定書では、遺伝子組換え生物と、科を超える細胞融合も含めた現代のバイオテクノロジーの利用によって作出された生物をLMO(Living Modi?ed Organism)として規制対象としている。
イネゲノム研究
【英語表記】 Rice Genome Project
【用語説明】イネの染色体上にある有用遺伝子の位置や全塩基配列を調べる研究のこと。
イネの塩基配列を解読するとともに、その中にある遺伝子の構造やその機能を解明しようというのが、イネゲノム(=イネの全遺伝情報)研究。
1991年度からわが国で始まった国家プロジェクトで、1998年には、日本が中心となって米国、中国、欧州など10カ国のコンソーシアムで、全塩基配列解読を分担して進めることになった。イネゲノム研究で明らかになったゲノム情報は、病害虫や環境ストレスに強い植物や機能性作物の開発、効率的な育種法の開発に役立てることができる。
2002年12月に、ほぼ全塩基配列が解読され、当時の小泉純一郎首相によりイネゲノム全塩基配列解読の終了が宣言された。
【関連項目】 ゲノム、染色体、遺伝子
う
ウラシル
【英語表記】 Uracil
【用語説明】RNAは、リン酸と糖(D-リボース)と塩基が1つずつ結合してできたヌクレオチドがいくつもつながり形作られる。その塩基の成分にはアデニン(A)・ウラシル(U)・グアニン(G)・シトシン(C)の4種類が存在するが、ウラシル(U)はそのうちの1つである。
また、ウラシル(U)はDNA中のチミン(T)の部位で、DNAの遺伝情報がRNAに転写される際に置き換わる。
え
塩基
【英語表記】Base
【用語説明】DNAやRNAの構成成分であり、弱アルカリ性の化学物質。
DNAやRNAは塩基、糖、リン酸という3種類の化学物質が1つずつ結合したものが最小単位になっている。DNAの塩基ではアデニン(A)・チミン(T)・グアニン(G)・シトシン(C)の4種類がある。RNAはチミン(T)の代わりにウラシル(U)が存在している。
この4種類の塩基配列の並び方は、遺伝情報として生体に伝えられる。例えば、ヒトでは遺伝情報は30億個の塩基からできているといわれている。
塩基対
【略語・別称】BP
【英語表記】Base Pair
【用語説明】DNAの二本鎖の間は、塩基と塩基が頭をつきあわせてアデニン(A)とチミン(T)、グアニン(G)とシトシン(C)というように決まった組になって、水素結合により、対合している。この組を塩基対という。
RNAではアデニン(A)とウラシル(U)、グアニン(G)とシトシン(C)が対合する。
塩基配列
【英語表記】Base Sequence
【用語説明】DNAやRNAにおける、塩基の並び方のこと。
DNAの塩基ではアデニン(A)・チミン(T)・グアニン(G)・シトシン(C)の4つあり、この並び方、つまり塩基配列が、タンパク質の情報(遺伝情報)を担っている。