純白で茎伸長性に優れた小輪ギク新品種「キクつくば1号」
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
「キクつくば1号」は、日本に自生する野生種イソギクとスプレーギクとの種間雑種である。純白緑芯で花形が整い、茎の伸長性に優れ、フラワーアレンジメントにも利用可能な新しいタイプの小輪ギクである。
- キーワード:スプレーギク、イソギク、種間雑種
- 担当:花き研・生理遺伝部・遺伝育種研究室
- 連絡先:電話029-838-6814、電子メールwww-flower@naro.affrc.go.jp
- 区分:花き
- 分類:技術・参考
背景・ねらい
イソギク(Chrysanthemum pacificum Nakai)は関東から東海にかけての太平洋沿岸に自生するわが国固有のキク属野生種である。花き研究所の前身である旧農林水産省野菜試験場で開発されたイソギクとスプレーギクとの種間雑種は、1980年代後半に新しいタイプの小ギクとして沖縄を中心に普及した。しかし現在はその後の品種変遷により種間雑種品種はほぼ姿を消しつつある。そこで、新たなイソギク系統を素材とした高品質で多収性を有する小ギク品種を育成する。
成果の内容・特徴
- 「キクつくば1号」の種子親はスプレーギク品種「セイライム」、花粉親はスプレーギク品種 「ホワイトブーケ(きく農林6号)」に花き研究所で保存中のイソギク系統8706を交雑して得られた種間雑種系統2000-29である(図1)。
- 花色は鮮明で純白に近く(JHSチャート3101)、花盤が緑芯で花粉の量が少ない。花径が45mm程度の小輪で、15枚程度の花弁は整然と並び、咲き進んでも外側に反り返らない(図2、表1)。
- これまで普及したイソギク雑種品種「沖の白波」を上回る優れた茎伸長性を有している(図3)。また、「沖の白波」と異なり、葉柄が短く、葉が剛直になりにくい。
- 自然開花期は11月上旬の秋ギクである。
成果の活用面・留意点
- 現在の小輪ギクは主に仏事用に利用されるが、フラワーアレンジメントなどにも適する小輪ギクである。
- 全国のキク生産地に適応すると考えられるが、生態型としては秋ギクタイプであるので、温暖地における夏季出荷には適さない。
- 冬季低温期に開花遅延・不開花を引き起こしやすいことから、沖縄等における露地栽培では年末出荷までが適しており、彼岸出荷には向かない。
- 栽培管理によっては下葉が枯れやすい傾向がある。
具体的データ
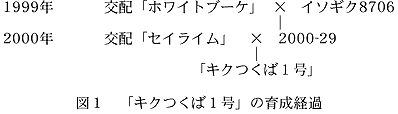

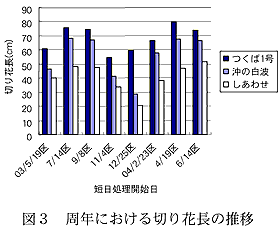
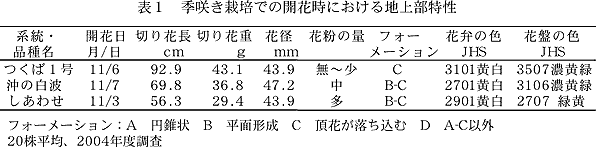
その他
- 研究課題名:多収性キクの新育種素材・品種の開発
- 課題ID:10-01-02-01-01-04
- 予算区分:超省力園芸
- 研究期間:1997~2004年度
- 研究担当者:谷川奈津、小野崎隆、池田 広、柴田道夫
