潮風害を受けたウンシュウミカンの光合成産物の分配特性に基づく樹勢回復法
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
潮風害を受けたウンシュウミカンの果実を残した場合、光合成産物は果実に多く蓄積され、他の器官への分配が低下する。また細根の呼吸活性及び量とも低下する。したがって、被害後直ちに摘果するほうが樹勢の早期回復には有利である。
- 担当:果樹試験場・カキ・ブドウ支場・栽培生理研究室
- 連絡先:成果情報のお問い合わせ
- 部会名:果樹
- 専門:生理
- 対象:果樹類
- 分類:指導
背景・ねらい
1991年の台風の襲来により西日本のカンキツ栽培地帯は大きな被害をうけた。したがって潮風害後の樹勢の早期回復技術の確立のために樹体の回復時の生理 機能を解明し、それに基づいた技術を開発する必要がある。そのために、潮風害後のウンシュウミカンの着果の有無が光合成産物の転流特性並びに細根の活性や 量に及ぼす影響を明らかにして、樹体の早期回復のための技術確立に資する。
成果の内容・特徴
- 秋季における潮風害再現処理後の樹体に残された果実が各器官への光合成産物の分配率に及ぼす影響をみると、着果樹では果肉への分配が最も大であり、また被害が大きいほど果肉分配率が高い(図1)。
- 被害後全摘果した樹における分配率は、新葉で最も高く、2~3年生枝、根、旧葉などでも比較的高い。新葉での分配率は被害の著しいものほど大である(図1)。
- 器官別の乾物重当たりの13C吸収量では着果樹、摘果樹とも新葉、旧葉、1年枝などで高く、摘果樹の被害甚樹では新葉での吸収量がきわだって多い。着果樹では果皮においても吸収量が比較的高い(図2)。
- 根の活性(呼吸速度)は着果樹では処理後10日目には処理前と比べ約20%低下したが、摘果樹ではほとんど変わらなかった。また、細根量(長さ1cm当たりの乾燥重)は着果樹では処理前の30%に減少したのに対し、摘果樹では処理前の約70%にとどまる(図3)。
- これらのことより、着果樹では果実への分配率、吸収量が多くなり、他の栄養器官への蓄積が減少するため、樹体の早期回復を図るには摘 果が有効であると判断された。また、着果樹では潮風害により根の脱落・腐敗が増加し、残存した細根の活性と量が低下したことから、潮風害後の早期摘果が、 細根量の確保ならびに根の活性の保持につながる。
成果の活用面・留意点
これまで、潮風害後のアマナツなどで明らかにされた摘果指針を転流・分配の生理面から裏付けた成果であり、潮風害後の樹体の取扱の指針を強化する基礎的データである。また、他の気象災害を受け、早期に樹勢回復を図る必要がある場合においても参考にすることができる。
具体的データ
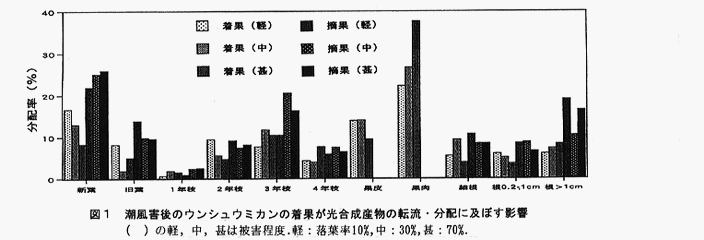
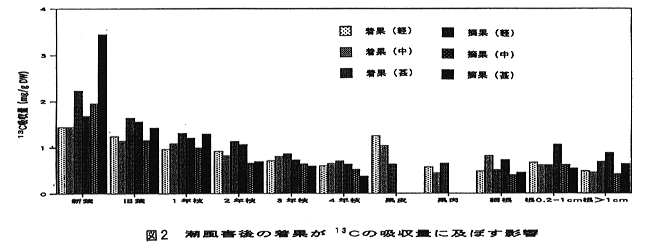
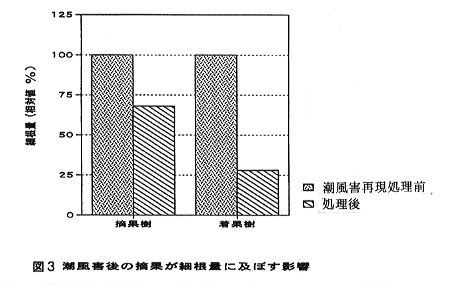
その他
- 研究課題名:果樹に対する潮風害の影響解析及び早期樹勢回復技術の開発
- 予算区分 :地域営農合理化
- 研究期間 :平成8年度(平成4年~8年)
- 発表論文等:ウンシュウミカン樹における潮風害後の光合成産物の転流・分配及び根の
呼吸活性に及ぼす着果の影響、園芸学会中四国支部要旨、第35号、1996。
