リンゴゆず果病の病原ウイロイドの確認とその検定法
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
リンゴゆず果病の病原体はリンゴゆず果ウイロイド(AFCVd)である。本ウイロイドの検定は電気泳動法により2~3日で、被検樹に指標植物の NY58-22(クラブリンゴの1種)を高接ぎして果実病徴を観察する生物検定法により1~2年で可能である。
- 担当:果樹試験場・リンゴ支場・病害研究室
- 連絡先:成果情報のお問い合わせ
- 部会名:果樹
- 専門:作物病害
- 対象:果樹類
- 分類:指導
背景・ねらい
リンゴゆず果病は小金沢ら(1989)により報告された接ぎ木伝染性果実異常症で、成熟果(果面凹凸、斑入り、果肉褐変)あるいは枝 幹部(粗皮)に病徴を発現し、果実の商品価値を著しく低下させる。本病の伝染手段は主に接ぎ木であることから、防除には無毒の穂木及び台木(中間台含む) の使用が不可欠であるが、病原未知のため、これまで実用的な検定法がなかった。そこで、本病病原の探索と検定法の開発を行った。
成果の内容・特徴
- ゆず果病罹病樹の樹皮より核酸を抽出し、5%ポリアクリルアミドゲルによる二次元電気泳動(1回目は未変性条件,2回目は変性条件)を行ったところ、いずれの罹病樹からも特異的なウイロイド様RNAが検出され、健全樹からは検出されなかった。
- 純化した本ウイロイド様RNAはリンゴ実生に対して感染性を示し(表1)、本ウイロイド様RNAがウイロイドであることが明らかとなった。
- 本ウイロイドはリンゴさび果ウイロイド(ASSVd)より分子サイズが大きく、 ASSVdの cDNA プローブと反応しないことから、別種のウイロイドであることが明らかとなった。
- 本ウイロイドのリンゴ樹に対する病原性を調べたところ、いずれの接種樹にもゆず果病特有の病徴が発現し、発病樹からは本ウイロイドが再検出された(表2)。
- 以上の結果より、本ウイロイドがゆず果病病原であることが明らかとなり、リンゴゆず果ウイロイド(AFCVd)と呼称した。
- AFCVd の検出は、樹皮より核酸を抽出して二方向ポリアクリルアミドゲル電気泳動を行うことにより2~3日(図1)で、また、指標植物 NY58-22(クラブリンゴの1種)の穂木を1被検樹当たり数本高接ぎして果実病徴を観察することにより1~2年で可能であった。
成果の活用面・留意点
AFCVd のリンゴ樹体内における濃度は極めて低いので、電気泳動後のゲルは銀染色する。また、生産現場等の電気泳動を行う設備がない場所では、ウイルス及びウイロイドフリーの NY58-22 (リンゴ支場保存)を用い、なるべく花芽を持つ穂木を接ぐ。
具体的データ
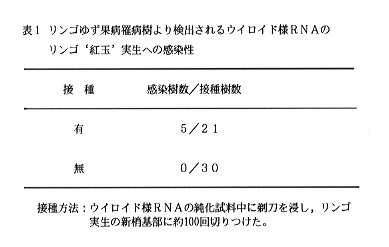
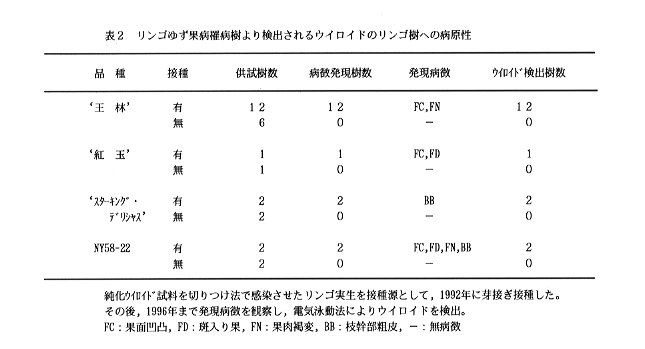
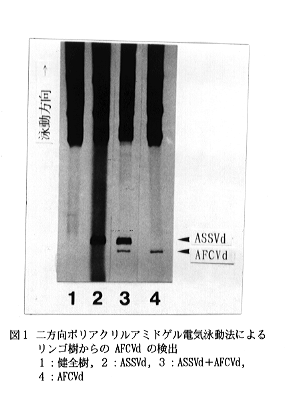
その他
- 研究課題名:リンゴ接ぎ木伝染性病害の病原究明ならびに迅速診断法の開発
- 予算区分 :経常
- 研究期間 :平成8年度(平成6~平成10年)
- 発表論文等:Detection of a viroid associated with apple fruit crincle disease. Ann. Phytopath.
Soc. Japan 59:520-527.1993.
リンゴ接ぎ木伝染性果実異常症の早期検定植物の探索(予報)、東北農業研究、
44、1991。
