リンゴ腐らん病菌り病樹皮におけるペクチンの可溶化
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
腐らん病に侵されたリンゴ樹皮から抽出したペクチンは可溶化されており、可溶化されたペクチンは分子量が減少し、陰イオン交換体に吸着されやすい。腐らん病の病斑においてみられる樹皮の軟化は、ペクチンの分解・可溶化によって引き起こされることが示唆される。
- 担当:果樹試験場・リンゴ支場・病害研究室
- 連絡先:成果情報のお問い合わせ
- 部会名:果樹
- 専門:作物病害
- 対象:果樹類
- 分類:研究
背景・ねらい
植物組織の軟化には、ペクチンの分解・可溶化が関係していると考えられている。リンゴ腐らん病はリンゴ樹の枝幹に発病し、その病斑が 伸展する際には、樹皮の速やかな褐変及び軟化をともなう。そこで、リンゴ腐らん病病斑部の樹皮(以下、病斑)及び病斑部周辺の健全な樹皮(以下、健全樹 皮)からペクチンを分別抽出し、その性状を比較することによって腐らん病の病徴発現に関与する要因を知るてがかりとする。
成果の内容・特徴
- 健全樹皮及び病斑からペクチンを分別抽出し定量すると、病斑においては水溶性ペクチンが増加し、不溶性ペクチンが減少した。なお、健全樹皮から水溶性ペクチンは抽出されなかった(図1)。
- 水溶性ペクチンの分子量は、不溶性ペクチンの分子量と比較し、より小さい側に分布していた(図2)。
- 抽出されたペクチンの陰イオン交換体に対する吸着性では、水溶性ペクチンはそのほとんどが吸着された。不溶性ペクチンにおいては、健全樹皮由来のものは吸着されない成分が多くみられたのに対し、病斑由来のものはほとんどが吸着された(図3)。
- ペクチンの性状変化が腐らん病菌の作用によることを確認するため、腐らん病菌をペクチンを加えた培地上で培養した。その結果、培養ろ液中のペクチンにおいて分子量の減少及び陰イオン交換体に対する吸着性の増大がみられた。
- Cup-plate法(酵素基質を含んだ寒天平板に開けた小孔に酵素液を入れて活性を検出する方法)において、病斑にはペクチナーゼ活性がみられたが、健全樹皮にはみられなかった(図4)。腐らん病の病斑においてみられる樹皮の軟化は、本試験の結果、ペクチンの分解・可溶化によって引き起こされることが示唆された。
成果の活用面・留意点
試験の結果、腐らん病菌によって樹皮に含まれるペクチンが可溶化されることが明らかになった。今後、菌の生産するペクチン分解酵素を単離し、その性状を明らかにする必要がある。
具体的データ
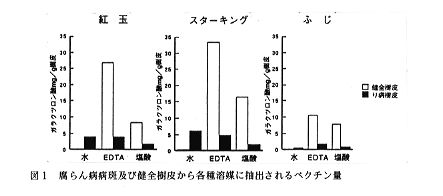
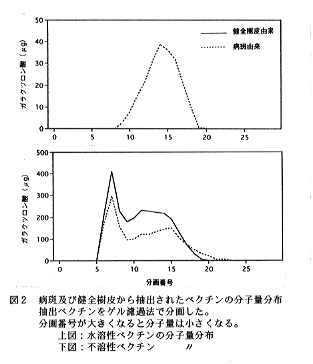
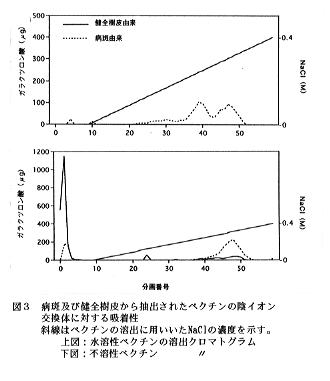
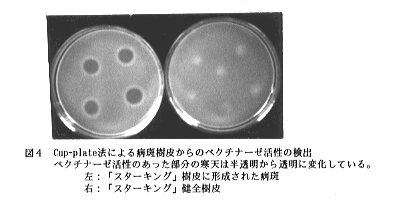
その他
- 研究課題名:リンゴ腐らん病菌の生産する生理活性物質と病徴発現機構
- 予算区分 :経常
- 研究期間 :平成8年度(平成8年~12年)
- 発表論文 :リンゴ腐らん病り病樹皮と健全樹皮におけるペクチン質含量の差異、
日本植物病理学会報、62巻6、1996。
