ミカンを多く摂取するヒトにおける酸化ストレスと血清脂質の変化
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
154名のボランティア被験者の血液分析により、ミカンを多く食べる人ではミカンシーズン期において酸化ストレスや血清脂質等の疾患マーカーがあまり食べない人に比べて有意に改善される。
- キーワード:ウンシュウミカン、血液分析、疾患マーカー、β-クリプトキサンチン
- 担当:果樹研・カンキツ研究部興津・品質機能研究室
- 連絡先:成果情報のお問い合わせ
- 区分:果樹(栽培)
- 分類:科学・参考
背景・ねらい
これまでの断面調査法による疫学的研究結果は、ウンシュウミカンの摂取が糖尿病・高血圧・心臓病・痛風等の生活習慣病に対して予防効果のある可能性を示唆する。自記式アンケート調査による疫学研究の結果を踏まえ、ヒトレベルでウンシュウミカンの健康維持・増進効果を解明するため血液生学的分析を行った。
成果の内容・特徴
- 50才以上の男女154名のボランティア被験者について、10月~2月におけるウンシュウミカンの摂取頻度を調査するとともに、ミカンオフシーズンの9月・シーズン期の1月・シーズン後の4月の計3回にわたり、ウンシュウミカン中の重要な機能性成分であるβ-クリプトキサンチン(β-CRX)の血清中濃度及び各種疾患の指標となる尿中・血液中における診断マーカーを測定した。
- 酸化的ストレスの指標となる尿中8-OHdG(8-ハイドロキシデオキシグアノシン)及び過酸化脂質は、ウンシュウミカンを毎日摂取しているグループではミカンシーズンである1月の検査時には有意に低下しており、ウンシュウミカンの摂取で酸化ストレスが軽減される(表1)。
- 糖尿病の指標となる血液中フルクトサミンについて、正常値を示した被験者のみを抽出した場合、ウンシュウミカンを毎日食べているグループでは1月の検査時に有意に低下していたことから(表1)、ウンシュウミカンの摂取は糖尿病予防への有効性が推察される。
- 痛風の指標となる血液中尿酸値は摂取頻度に依存して低く、1月の検査時には摂取頻度2以上のグループで有意な低下が認められたことから(表1)、ウンシュウミカンの摂取は痛風予防への有効性が推察される。
- LDLコレステロール・アポBタンパクは9月の検査時では血清中β-CRX濃度と有意な正の相関が認められていたが、1月には相関が無くなり、逆にHDLコレステロール・アポA1タンパクは1月の検査時に有意な正の相関が認められたことから(表2)、ウンシュウミカンを多く摂取するミカンシーズンにおいて脂質代謝が改善される。
成果の活用面・留意点
- ウンシュウミカンを食べることが生活習慣病の予防につながる可能性が示唆されることから、健康増進効果の面で果実消費拡大に有効な資料となる。
- 今回の調査結果は健常者を対象にしたものである。
具体的データ
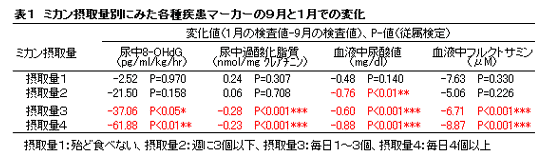
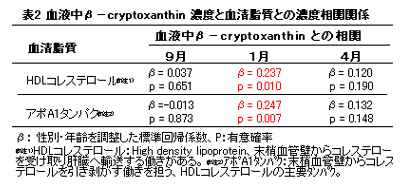
その他
- 研究課題名:日本産カンキツの健康増進効果‐ヒトでの実証
- 予算区分:グリーンフロンティア食品成分の生体調節機能の解明と利用技術の開発
- 研究期間:2000 ~ 2002 年度
- 研究担当者:杉浦 実、松本 光、矢野昌充
- 発表論文等:1)杉浦ら (2002) 治療 84:142-144.
2)杉浦ら (2002) 柑橘 1月号:26-32
3)杉浦・矢野 (2000) 第5回JSoFF学術集会要旨集:26
4)杉浦・矢野 (2001) 日本薬学会第121年会要旨集IV:175
5)矢野ら (2001) 第6回JSoFF学術集会要旨集:37
6)松本ら (2001) 第6回JSoFF学術集会要旨集:38
