核の形態の特徴からウメ品種をグループ分けできる
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
ウメの核の輪郭を2方向からデジタル画像処理により抽出し、楕円フーリエ記述子により定量化して得られた主成分得点と、核の縦径、 横径、側径を計測してそれぞれの積および比を算出して得られた数値には大きな品種間差異がある。この差異を統計処理することで、ウメ品種を核の形態の特徴 が似ているグループに分けられる。
- キーワード:ウメ、核、形態特徴、楕円フーリエ記述子
- 担当:果樹研・遺伝育種部・核果類育種研究室
- 連絡先:成果情報のお問い合わせ
- 区分:果樹・育種
- 分類:科学・参考
背景・ねらい
現在、梅干し製品には原料原産地表示が義務づけられている。しかし、この表示の正否を確認する手法が確立されておらず、判別技術が 求められている。ウメの核の形状や大きさは同一品種内では変異が少なく、品種間で差異が大きいことが知られている。梅干し製品の核から品種名を判別できれ ば、原料原産地を推定することも可能となる。そこで核の形状と大きさを計測して定量的に評価することで、品種間の差異を数値化した。この数値の統計処理に 基づき、ウメ品種を核の形態の特徴が似ているグループに分類する。
成果の内容・特徴
- 日本および中国のウメ64品種・系統の核について、それぞれ10個ずつ側面および横面からデジタルカメラで撮影し、 得られた輪郭形状を楕円フーリエ記述子により、様々な楕円の形に類型化する。得られた数値を主成分分析し、最も品種を見分けやすい数値の構成(主成分得 点)をPC1、それに次ぐ構成をPC2として楕円を描く(図1)。
- 品種・系統の核の縦径、横径、側径をデジタルノギスで計測し、それぞれの積と比を算出する。
- この主成分得点と2で得た数値を統計処理(Ward法によるクラスター解析)すると、64品種・系統は7つのグルー プに分けられる。中国の品種はグループAに属し、日本の品種はBからGまでのグループに属する。小ウメと呼ばれる10g程度未満の品種はグループBに、核 の大きな品種はグループCとDに属する。「白加賀」など核の細長い(図1のPC1の+2SDの形)品種はグループEに、「南高」など核の丸い(図1のPC1の-2SDの形)品種はグループGに属する。グループFにはグループEとGの中間の形の核の品種が属する。(表1)。
成果の活用面・留意点
- 品種間差異についてさらに検討することにより、梅干し製品の核から品種名を判別する手法の開発が可能となる。
具体的データ
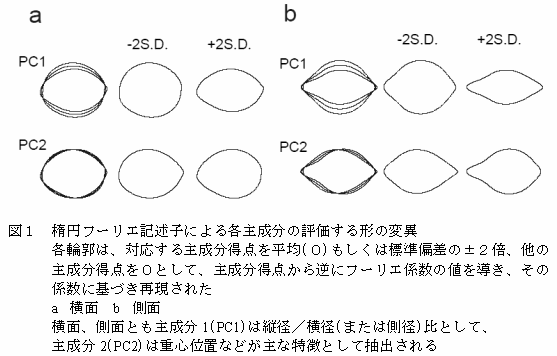
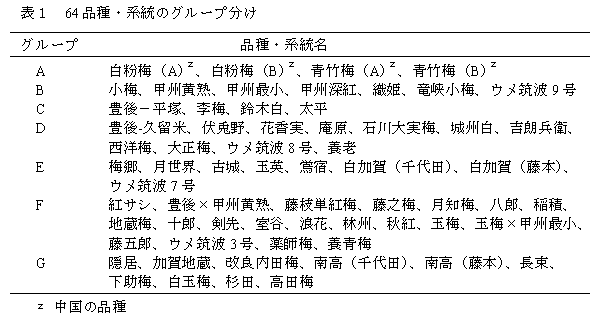
その他
- 研究課題名:ウメ果実の形状解析による品種識別技術の開発
- 課題ID:09-02-04-*-10-04
- 予算区分:高度化事業
- 研究期間:2002∼2004年度
- 研究担当者:八重垣英明、岩田洋佳(中央農研)、末貞佑子、土師岳(現東北農研)、山口正己
- 発表論文等:八重垣ら(2006).果樹研報告.5:29-37
