ミカンをよく食べる人では肝機能障害のリスクが低い
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
ウンシュウミカンをよく食べ、血清中β-クリプトキサンチン濃度が高い人では飲酒が原因による血中γ-GTPの上昇及び高血糖が原因となる肝機能障害のリスクが低い。
- キーワード:ミカン、β-クリプトキサンチン、肝臓、飲酒、高血糖
- 担当:果樹研・カンキツ研究部・品質機能研究室
- 連絡先:成果情報のお問い合わせ
- 区分:果樹(栽培)
- 分類: 科学・参考
背景・ねらい
過度の飲酒がアルコール性肝炎や脂肪肝、また肝硬変の原因となることはよく知られている。また、高血糖状態では酸化ストレスが増大 しており、このような高血糖による酸化ストレスも肝細胞に対して障害を与えることが考えられる。一方、これまでに当研究室ではウンシュウミカン(ミカン) をよく食べる人ほど血清中β-クリプトキサンチン濃度が著しく上昇し、ミカン摂取量を極めて良く反映することから、ヒトレベルでミカンの健康機能性を評価 する際の有効な指標であることを明らかにしている(平成15年度成果情報)。そこでミカン摂取が肝機能に及ぼす影響を血清β-クリプトキサンチン濃度と血 中肝機能指標(γ-GTP, AST及びALT値)との関連を解析することで検証する。
成果の内容・特徴
- アルコール性肝機能障害の指標の一つである血中γ-GTP値は、飲酒量が多い人ほど高いが、毎日25g(ビール大瓶 1本相当)以上のエタノールを摂取していても、血清中のβ-クリプトキサンチンレベルが高い人(ミカンのシーズンに、毎日およそ2,3個以上のミカンを食 べている人)ではγ-GTP値が低い(図1)。(肝疾患を有さない男性266名を対象)
- 肝機能障害の指標とされるASTとALT値は、血糖値が高い人では正常な人に比べて高いが、血清中のβ-クリプトキサンチンレベルが高い人ではこれらの指標値が高血糖でも正常とほぼ変わらないレベルである(図2)。(過度の飲酒歴やウィルス性肝炎等の肝疾患を有さない男女857名を対象)
- 日本人はβ-クリプトキサンチンをミカンから摂取しているので、ミカンをよく食べる人では肝障害のリスクが低いこと を示唆する。ミカンにはβ-クリプトキサンチンに加え、食物繊維をはじめさまざまな機能性成分が含有されているため、ミカンの摂取が正常な肝機能を維持す るのに有効である可能性がある。
成果の活用面・留意点
- ミカンを食べることが肝疾患予防に役立つ可能性が示唆されることから、今後、ヒトレベルでの研究を進める際に役立つ資料となる。
- 本調査結果は横断研究の結果であり、結果と原因との時間的な関係を考慮出来ていないため、より因果関係を明らかにするためには追跡研究が必要である。
具体的データ
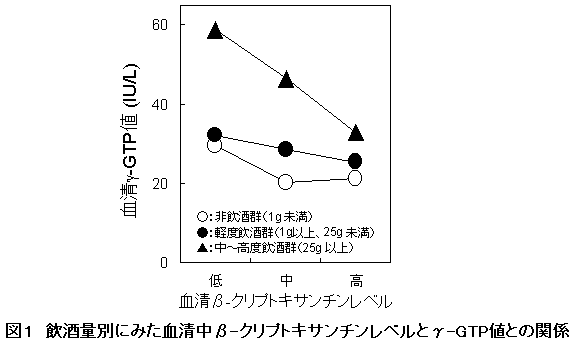
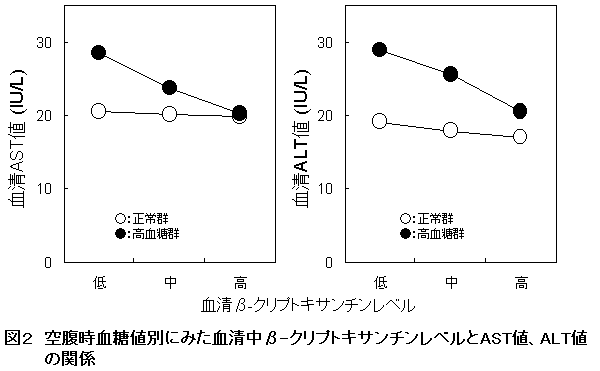
その他
- 研究課題名:果実の生体調節機能と他の食素材との組み合わせ効果の解明
- 課題ID:09-02-06-*-14-05
- 予算区分:食品
- 研究期間:2002∼2005年度
- 研究担当者:杉浦実、小川一紀
- 発表論文等:
1) Sugiura et al. (2006) Diabetes Res. Clin. Pract. 71: 82-91
2) Sugiura et al. (2005) J. Epidemiol. 15: 180-186
