捕食性昆虫コヒメハナカメムシはナミハダニをよく食べる
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
コヒメハナカメムシは、ナミハダニを餌として飼育すると発育率が高く、未成熟および成虫ステージのいずれでも高い捕食能力を示す。
- キーワード:ハナカメムシ類、ナミハダニ、捕食性昆虫天敵
- 担当:果樹研・省農薬リンゴ研究果樹サブチーム
- 連絡先:成果情報のお問い合わせ
- 区分:果樹・病害虫、東北農業・果樹
- 分類:研究・参考
背景・ねらい
近年、ナミハダニが大発生しているリンゴ園においてコヒメハナカメムシが飛来し、ナミハダニの急激な密度低下が観察された。本種はリンゴハダニの捕食者として知られ、また、市販の天敵タイリクヒメハナカメムシと同様に、スジコナマダラメイガ卵を利用して大量増殖が可能である。本種のナミハダニ捕食能力が高ければ、天敵製剤としての利用が期待される。そこで本種のナミハダニ捕食特性を調査し、捕食者としての能力を評価する。
成果の内容・特徴
- コヒメハナカメムシ雌成虫は、ナミハダニ雌成虫を1日あたり20頭捕食する(表1)。直接の比較はできないものの、本種の捕食能力は、ミヤコカブリダニ(1日あたりナミハダニ卵17個(25°C))やケナガカブリダニ(1日あたりナミハダニ卵9個(20°C))よりも高い。
- 本種雌成虫は1日あたり5卵を産下し、産卵期間28日間に約150卵を産する(表1)。
- ナミハダニを餌として飼育すると89%がふ化し、ふ化個体の95%が成虫になる(表2)。
- 産卵されてから羽化までに要する発育期間は、20°Cで31日、25°Cで21日である(表3)。卵以外のすべての未成熟ステージが捕食可能であり、発育期間中、 144頭(20°C)または125頭(25°C)のナミハダニ雌成虫を捕食する。
成果の活用面・留意点
- 農生態系で観察される本種の近縁種として5種が知られ、外観的には判別が困難であるが、雄の交尾器とDNAマーカーで同定できる。本種は、近縁種の中でも樹上生息性が高い種として知られる。
- 気温が低いと活動が低下し、北東北では8月下旬から休眠に入ると考えられる。
- 大量増殖した個体の放飼・定着技術を開発する必要がある。
具体的データ
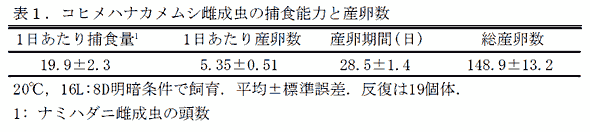
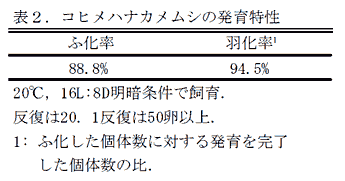
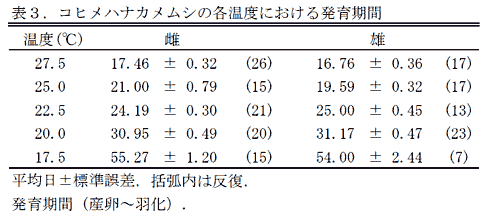
その他
- 研究課題名:フェロモン利用等を基幹とした農薬を50%削減するりんご栽培技術の開発
- 課題ID:214-o
- 予算区分:生物機能
- 研究期間:2004~2006年度
- 研究担当者:豊島真吾
- 発表論文等:Toyoshima (2006) J. Acarol. Soc. Jpn. 15(2): 151-156.
