20℃で貯蔵することによりリンゴ果実の冷蔵における貯蔵性を短期間で評価できる
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
早生から晩生までのいずれのリンゴ品種でも、20℃貯蔵での果肉硬度および酸含量の変化は、0℃貯蔵よりそれぞれ8.9倍、3.7倍速いことから、20℃貯蔵で果実品質の変化を調査することで、短期間で冷蔵による長期貯蔵性を評価することができる。
- キーワード:リンゴ、貯蔵、硬度、酸含量、回帰式、予測
- 担当:果樹研・リンゴ研究チーム
- 代表連絡先:成果情報のお問い合わせ
- 区分:果樹・育種
- 分類:研究・普及
背景・ねらい
収穫した果実がどれくらいの期間貯蔵できるかを明らかにするには、貯蔵中の果実を調査し、いつ品質がある一定レベルを下回るかを確認する必要がある。リンゴの場合、果肉が軟らかくなることと酸味が減少することが貯蔵中の品質劣化の大きな要因であるが、普通冷蔵でも長期間貯蔵可能であることから、定期的に貯蔵中の果実をサンプリングし果実品質を調査するには、多くの果実と労力が必要となる。そこで、貯蔵性の試験の効率化を図るため、冷蔵貯蔵中の果肉硬度と酸含量の変化を短期間で予測する方法を開発する。
成果の内容・特徴
- 果肉硬度および酸含量は、冷蔵貯蔵(温度0°C湿度99%)では緩やかに減少するのに対し、温度20℃湿度85%の貯蔵条件では急激に減少し、収穫後20日目までにはほとんどの果実の品質は不良となる(図1A、図2A)。
- 早生から晩生までの20品種を用いて比較すると、20℃で軟化が見られる品種については、20℃貯蔵の貯蔵期間を8.9倍に引き延ばすと、品種によらず、20℃貯蔵と0℃貯蔵の硬度変化が一致する(図1B)。すなわち、20℃貯蔵の軟化速度は、0℃貯蔵より8.9倍速い。同様に、20℃貯蔵の貯蔵期間を3.7倍すると、いずれの品種でも、20℃貯蔵と0℃貯蔵の酸含量の変化が一致する(図2B)。これは、20℃貯蔵で10日目の果肉硬度および酸含量の値は、冷蔵貯蔵では、それぞれ89日目、37日目の値となることを意味する。
- 20℃での貯蔵性の品種間差と冷蔵での貯蔵性の品種間差とが一致することから、品質変化の大きい20°Cでの貯蔵性を評価することで、短期間で冷蔵での貯蔵性を評価することが可能である。
成果の活用面・留意点
- 必ず冷蔵貯蔵果と同一時期に収穫した果実を20°Cで貯蔵して品質変化を調査する。
- 20℃貯蔵では品質の変化が激しいため、長くとも5日ごとに調査する必要がある。
- 果肉硬度は、マグネステーラー硬度計で果実の陽光面と反対面の2か所を測定した平均値を用いる。
- ほとんどの品種は、軟化することで品質が不良となることから、硬度変化を調査することで貯蔵性を評価できる。
- 「ふじ」のように冷蔵貯蔵中の硬度減少が非常に緩やかな品種は、20℃貯蔵では脱水により果肉がゴム質化し、見かけ上は軟化がほとんど起こらない。このような品種は、軟化するよりも先に酸の減少による食味の変化で品質が劣化することから、20℃貯蔵で軟化の見られない品種については、酸含量の減少程度から貯蔵性を評価する。
具体的データ
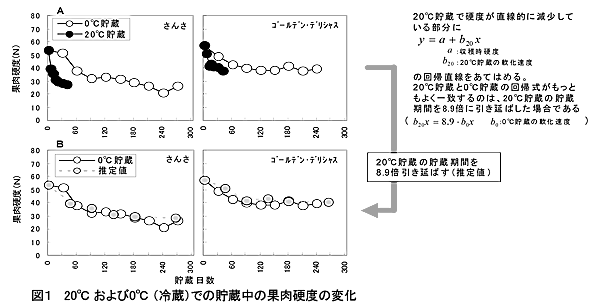
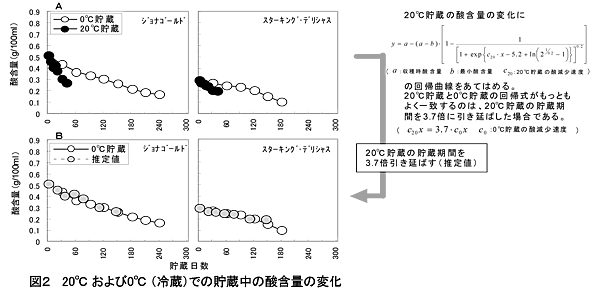
その他
- 研究課題名:高収益な果樹生産を可能とする高品質品種の育成と省力・安定生産技術の開発
- 課題ID:213-e.4
- 予算区分:基盤研究費
- 研究期間:2006~2008年度
- 研究担当者:岩波 宏、森谷茂樹、古藤田信博、阿部和幸
- 発表論文等:Iwanami et al. (2008) HortScience 43:655-660
